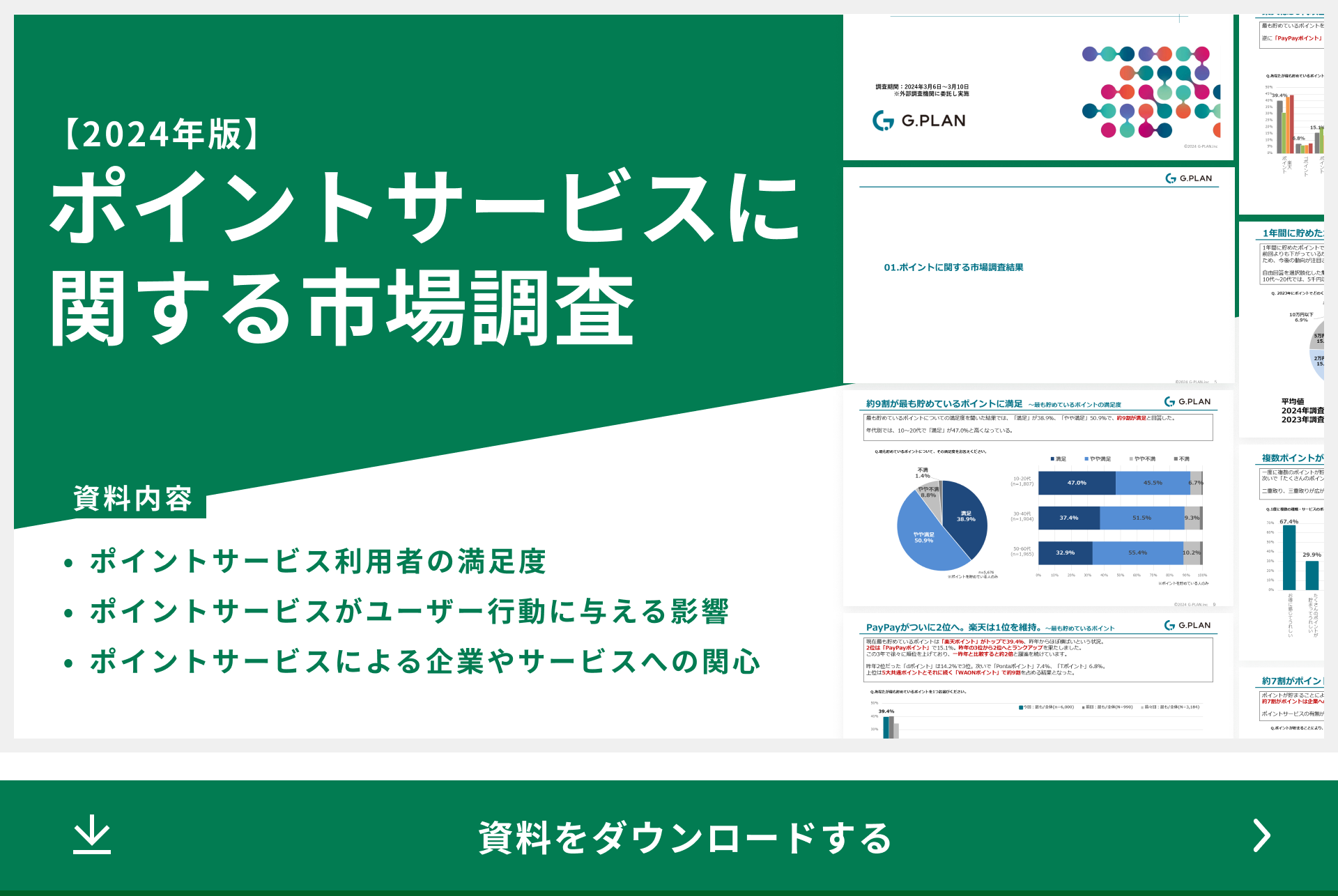電子マネーとポイントの違いとは?具体例を挙げながら詳しく解説!
近年、社会のキャッシュレス化が急速に進行し、街中やオンライン上で、さまざまなキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済サービスなど)を利用する機会が増加しました。
ところで、日々、何気なく利用している「電子マネー」ですが、「ポイント」との違いを明確に理解している方は少ないかもしれません。そこで、本記事では、混同しがちな「電子マネー」と「ポイント」の違いについて、具体例を挙げながら詳しく解説します。
この記事のポイント
ポイント1 電子マネーとポイントには、法律上、明確な違いがある
- ポイント2 各企業の電子マネーとポイントサービスの違いを正確に理解しよう
- ポイント3 ポイントサービスのほうが、電子マネーよりも導入しやすい
目次[非表示]
- 1.「電子マネー」と「ポイント」の違い
- 1.1.「マイル」と「ポイント」の違い
- 2.さまざまな企業の電子マネーとポイントサービスをご紹介
- 2.1.「Suica電子マネー」と「JRE POINT」
- 2.2.「Vマネー」と「Vポイント」
- 2.3.「nanaco」と「nanacoポイント」
- 2.4.「WAON」と「WAONポイント」
- 3.電子マネーよりもポイントサービスのほうが、導入するハードルが低い
- 4.ポイントサービスを実施する際に把握しておくべき経済産業省のガイドライン
- 4.1.消費者がポイントサービスの内容を網羅的に確認できる仕組みを用意する
- 4.2.トラブルが発生した場合は適切に対応する
- 4.3.有効期限を短くしたり、ポイントの価値を減少させたりする場合は、消費者への配慮が求められる
- 5.まとめ
「電子マネー」と「ポイント」の違い
多くの方が、日々、コンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーなどで、「電子マネー」や「ポイント」を利用して買い物をしています。どちらも現金と同様、商品の購入に利用できますが、両者には、法律上の位置付けに違いがあります。
電子マネーとは、「資金決済法」における「前払式支払手段」に該当するもので、利用者から現金などの対価を受け取って発行されています(コンビニエンスストアのレジやATM、専用端末、クレジットカードなどでチャージした金額が「残高」に反映)。
それに対し、一般的にポイントサービスは、「商品・サービスを購入した際に、支払額の一定割合(例えば、1%など)に相当する分を付与する」といった形で運用されているものです。基本的にポイントは、利用者から対価を受け取って発行されているわけではないため、前払式支払手段に該当せず、資金決済法の適用外となります。
ただし、「ポイント」という名称であっても、消費者から対価を受け取って発行されるものは、前払式支払手段と見なされることにご留意ください。サイトでポイントを購入し、「投げ銭」として利用するサービスなどはこちらにあたると考えられます。
「マイル」と「ポイント」の違い
航空会社などが提供している「マイル」と、「ポイント」の違いについて気になっている方もいるのではないでしょうか。
マイルとポイントは、「名称」が異なるものの、法的な位置付けは同じです。消費者から対価を受け取って発行しない限りは、前払式支払手段に該当しません。重要なのは、名称ではなく、対価を受け取って発行しているかどうかという点です。
さまざまな企業の電子マネーとポイントサービスをご紹介
以下、電子マネーおよびポイントの代表例として、4社のサービスをご紹介します。具体例を見ながら、両者の違いについて理解を深めましょう。
まず前提として、電子マネーは「ユーザー自身で残高へのチャージを行うもの」であるのに対し、ポイントは「何らかのアクション(カードの利用・提示など)をすることで付与されるもの」という点を認識しておきましょう。
「Suica電子マネー」と「JRE POINT」
Suica電子マネーとは、JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)が発行している電子マネーです。IC乗車券「Suica」にチャージすることで、残高の範囲内で「鉄道の乗車」「加盟店におけるショッピング」などでの支払いを行えます(有効期限は、最後に利用した日から10年間)。
他方、JRE POINTとは、「Suica」「JRE POINTカード」「ビューカード」を利用したり、提示したりすることで付与されるポイントです。貯まったポイントは「1ポイント=1円」の価値があり、ショッピングや、グリーン券・各種プレゼントとの交換で利用できます(有効期限は、最後にポイントを獲得・利用した日から2年後の月末まで)。
※Suica電子マネーとJRE POINTの違いはこちらの記事でも詳しく説明しています。
「Vマネー」と「Vポイント」
Vマネーとは、CCCライフパートナーズ株式会社が発行している電子マネーです。「Vポイントが貯まるカード」にチャージすることで、さまざまな加盟店で利用できます(有効期限は、最終利用から10年間)。
Vポイントとは、加盟店で買い物をする際にモバイルVカード(スマートフォンの画面上に表示されるバーチャルカード)や三井住友カード(クレジットカード)を提示することで付与されるポイントです。貯まったVポイントは「1ポイント=1円分」として、加盟店における買い物で利用できます(有効期限は、最終変動日から1年間)。
「nanaco」と「nanacoポイント」
nanacoとは、事前にnanacoカードやアプリにチャージ(入金)をしておくことで、残高の範囲内でショッピングでの支払いに利用できる電子マネーであり、株式会社セブン・カードサービスが発行しています。なお、nanacoの電子マネーに有効期限はありません。
他方、nanacoポイントとは、電子マネーのnanacoで支払いを行ったり、一部のクレジットカード(セブンカード・プラス、セゾンカード、UCカード等)を利用したり、メールマガジン「nanacoニュース」のリンクをクリックしたりすることで付与されるポイントです。電子マネーと同様に、株式会社セブン・カードサービスが運営しています。
貯まったnanacoポイントは、「1ポイント=1円」として、セブン&アイグループのオンラインショッピングで利用できるほか、電子マネーのnanacoに交換することも可能です(当年4月1日~翌年3月末日に加算されたポイントの有効期限は、翌々年の3月31日まで)。
※nanacoとnanacoポイントの違いはこちらの記事でも詳しく説明しています。
「WAON」と「WAONポイント」
WAONとは、イオンリテール株式会社が発行している電子マネーです。あらかじめカードにチャージしておくことで、加盟店(実店舗、自動販売機、オンラインショップ等)において、残高の範囲内で支払いに利用できます。電子マネーのWAONに有効期限はありません。
それに対し、WAONポイント(電子マネーWAONポイント)とは、電子マネーWAONで支払いを行ったり、各種キャンペーンに参加したりすることで付与されるポイントです(有効期限は、最大2年間)。貯まったWAONポイントは、「WAONポイント1ポイント=電子マネーWAON1円分」のレートで電子マネーWAONに交換したうえで、ショッピングで利用できます。
ここで注意しなければならないのは、「WAONポイント」というカタカナ表記のポイントのほかに、「WAON POINT」というアルファベット表記のポイントも存在することです。似ているため、混同しがちですが、両者の違いを理解しておきましょう。
WAON POINTは、イオングループの店舗で買い物をする際に、対象カード(「WAON POINTカード」など)を提示することで付与されるポイントです。
WAONポイント(電子マネーWAONポイント)との違いとしては、「そのまま利用できるかどうか」という点が挙げられます。電子マネーWAONポイントの場合、一旦、電子マネーのWAONに交換したうえでショッピングで利用することになりますが、WAON POINTの場合、そのまま利用することが可能です。
WAON POINTは、電子マネーWAON以外の手段(現金など)で支払いを行った場合でも貯まります。貯まったWAON POINTは、「1ポイント=1円」の価値で、加盟店で利用することが可能です(有効期限は、最大2年間)。
※WAON POINTとWAONポイントの違いはこちらの記事でも詳しく説明しています。
電子マネーよりもポイントサービスのほうが、導入するハードルが低い
以上のように、電子マネーはあらかじめ「チャージ」を行い、その残高の範囲内で利用できるキャッシュレス決済手段です。一方、ポイントは、ユーザー自身が「チャージ」を行うのではなく、何らかのアクション(ポイントカードの提示など)をした際に付与されます。
電子マネーは、ユーザーからの対価(チャージ)を得たうえで発行しているので、経営を圧迫する心配がありません。
ポイントの場合、対価を得ていないため、実質的に「商品価格の割引」と同じ効果があります。大量に付与してしまうと経営を圧迫することになりかねません。このような事情から、手間をかけてでも電子マネーを発行するという選択肢もあり得るでしょう。
上で実例として挙げたように、BtoCビジネスを営む(一般消費者に商品・サービスを販売している)大企業では、電子マネーとポイントサービスの両方を導入しているケースもあります。ただし、社内の人的リソースが不足している場合、電子マネー発行に伴う事務手続きに対応するのは困難かもしれません。その場合は、原資をどうするかを十分に吟味したうえで、ポイントサービスのみの導入を検討する方が合理的と言えそうです。
ポイントサービスは、基本的に資金決済法の適用を受けないため、法務局への供託や財務局への届出・登録が不要であり、電子マネーに比べて導入が容易です。
なお、電子マネーであっても「発行日から6ヶ月以内に限って利用できるもの」に関しては資金決済法の適用対象外となるほか、「ポイント」と称していても「現金などの対価を得て発行されている場合」は前払式決済手段と見なされ、資金決済法が適用されることになります。
自社で電子マネーやポイントの発行を検討しているのであれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
ポイントサービスを実施する際に把握しておくべき経済産業省のガイドライン
ポイントサービスは、電子マネーとは異なり、資金決済法の適用を受けませんが、消費者の利益に配慮した対応が求められます。独自のポイントサービスを実施するのであれば、経済産業省の「企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)」の内容を把握しておきましょう。
これは、「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」における議論に基づいて策定されたガイドラインであり、ポイント発行企業が対応するべきことが記載されています。
以下、ガイドラインの主な内容をご紹介するので、独自ポイントを発行している(または、これから発行することを検討している)企業・店舗は、ぜひ参考にしてください。
消費者がポイントサービスの内容を網羅的に確認できる仕組みを用意する
経済産業省のガイドラインでは、「消費者が必要に応じてポイントサービスの内容を網羅的に確認できる仕組み」を整備することを、ポイント発行企業に要請しています。独自ポイントを発行する場合は、ポイントサービスの内容を示す「約款」を記載した書面を交付するか、Webサイトで表示しましょう。
具体的には、「ポイントの付与条件」「ポイントの利用条件」「利用条件の変更に関する事項」「トラブル発生時(ポイントカード紛失時・パスワード失念時など)の対応」「ポイントの譲渡に関する事項」「ポイントサービス終了時の対応」などに関して記載しておきましょう。
トラブルが発生した場合は適切に対応する
ポイントサービスを実施していると、「顧客がポイントカードを紛失する」「顧客がパスワードを忘れる」「企業・店舗のシステムの不具合により、ポイントを利用できない」など、しばしばトラブルが発生します。経済産業省のガイドラインによると、ポイント発行企業は、トラブル発生時に適切に対応する必要があります。
トラブルが発生した場合に備えて、例えば、「ポイントカードの再発行手続き」「パスワードの再発行手続き」「システムの不具合が発生した場合に、レシートなどにスタンプを押し、後日、ポイントを付与する」といった対応を考えておきましょう。
有効期限を短くしたり、ポイントの価値を減少させたりする場合は、消費者への配慮が求められる
ポイントサービスを長期間実施していると、有効期限を短くしたり、ポイントの価値を減少させたりするケースがあるかもしれません。共通ポイントを導入(または、共通ポイントと独自ポイントを併用していた状態から、共通ポイントのみに一本化)し、独自ポイントを廃止する場合もあるでしょう。
経済産業省のガイドラインでは、利用条件を「消費者にとって不利益となる方向」に変更する場合は、顧客の利益に配慮した措置を講じることを、ポイント発行企業に要請しています。
すでに貯めているポイントを、これまでの条件で利用する機会を顧客に与えるために、事前にアナウンスを実施し、変更までに充分な期間を確保しましょう。
まとめ
電子マネーとポイントサービスの主な違いは、資金決済法の適用を受けるか否かという点にあります。両者とも、日々、何気なく利用しているサービスですが、法的な位置付けが異なるのでご注意ください。
ポイントサービスは基本的に資金決済法の適用を受けないため、電子マネーよりも導入が容易です。ただし、独自のポイントサービスを実施する場合は、経済産業省のガイドラインを踏まえた対応が求められます。また、自社の店舗でしか利用できない「独自ポイント」だけでは、新規顧客の獲得が難しいかもしれません。さまざまな店舗で広く利用できる「共通ポイント」も導入すれば、それらのポイントを貯めているユーザーを自社の顧客として獲得しやすくなるでしょう。
多種多様なポイントを貯めているユーザーに、より強くアピールするためには、ジー・プランの各種ソリューションを活用することも選択肢のひとつです。例えば、「PCT LITE」や「ポイント・コンセント」なら、 自社ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントに直接交換できるので、ポイント運営の負担が軽減されるでしょう。
****
監修者:弁護士 米山 清貴
米山法律事務所(豊島区南大塚)。中小企業支援や事業再生などの他、後見や相続などの資産承継をはじめ一般民事を幅広く取り扱っている。
****
関連記事