
CS(顧客満足度)向上に効果的な7つの施策|盛り込むべき要素や成功事例をわかりやすくご紹介します!
CS(顧客満足度)向上は、あらゆる企業・店舗にとって、極めて重要な課題です。
しかし、具体的にどういう施策が有効なのかとなると、分かるようで分からないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では、CS向上施策に盛り込むべき要素を抽出した上で、具体的かつ効果的な7つの施策をわかりやすく紹介しています。
企業におけるCS向上の成功事例やよくある質問もまとめているので、効果的な施策立案の参考にしてください
<この記事のポイント>
✓ポイント1 顧客満足度は企業イメージやブランディングにも直結する極めて重要な要素
✓ポイント2 CS向上施策には「事前期待のコントロール」「期待感の醸成」などを盛り込むと効果的
✓ポイント3 接客品質の向上、顧客アンケートなどに加えて顧客接点を増加させることも重要
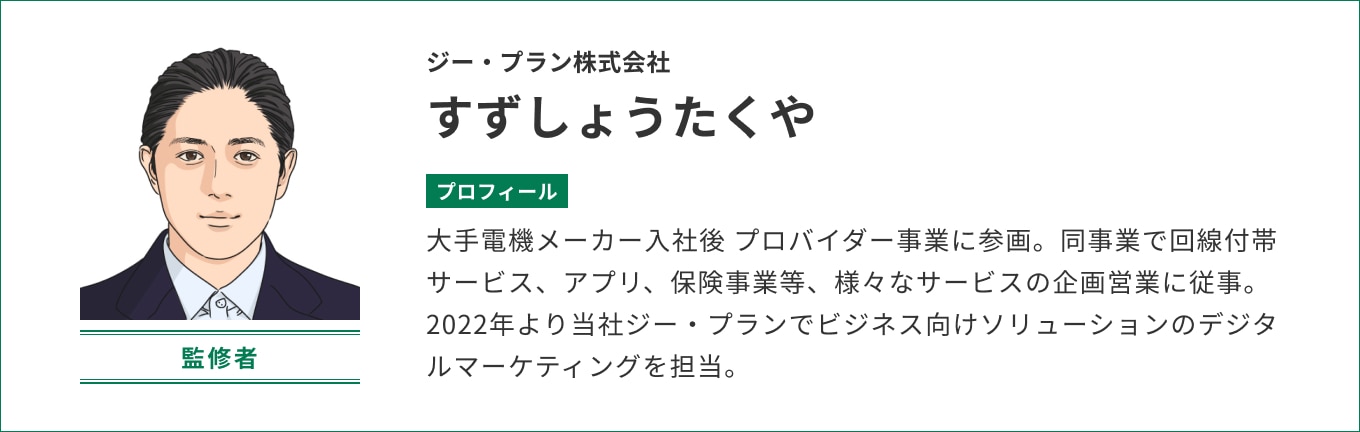
目次[非表示]
- 1.CS(顧客満足度)向上の施策を考える上で重要な心得
- 2.CS(顧客満足度)向上の施策に盛り込むべき5つの要素
- 2.1.1.顧客を発信元とした推奨
- 2.2.2.事前期待のコントロール
- 2.3.3.損失回避による安全性の立証
- 2.4.4.顧客体験のイメージ
- 2.5.5.定期性を持った期待感の醸成
- 3.CS(顧客満足度)向上に効果的な7つの施策
- 3.1.CS向上施策1.きめの細かい接客教育の徹底
- 3.2.CS向上施策2.顧客アンケートの定期実施
- 3.3.CS向上施策3.商品やサービスの高付加価値化
- 3.4.CS向上施策4.従業員満足度の向上
- 3.5.CS向上施策5.顧客接点の増加
- 3.6.CS向上施策6.CRMやSFAの活用
- 3.7.CS向上施策7.コミュニティ形成
- 4.CS(顧客満足度)向上の施策として参考にしたい成功事例3選
- 4.1.事例1:エネルギー会社
- 4.2.事例2:クレジットカード会社
- 4.3.事例3:専門広告会社
- 5.CS(顧客満足度)向上の施策に関するよくある質問
- 6.【まとめ】
- 7.おすすめの資料はこちら
CS(顧客満足度)向上の施策を考える上で重要な心得
CS(Customer Satisfaction/顧客満足度)とは、顧客が商品やサービスに対してどの程度満足しているかを示す用語です。
顧客満足度は、顧客が企業の商品、サービスに対して持っている期待値と、その結果によって左右されます。簡単にいえば、想定よりもよい商品、サービスであると感じれば満足度は高くなり、逆の場合は低くなるということです。
実際に購入・利用したあとだけでなく、購入・利用前のイメージにも深く関わっているため、CSは単なる商品評価や満足度に留まらず、企業イメージ及びブランディングに直結する極めて重要な要素であると言えるでしょう。
顧客満足度が向上すると、次のようなメリットがあります。
- リピーターが増加するため、新規顧客獲得のための広告宣伝費が削減できる
- 顧客の期待が把握しやすくなり、関係性が長期間持続する
- 商品やサービスへの好評価が増えることで、企業のブランド力が向上する
とはいえ、満足度はそのときの顧客の感情に左右されるため、状況に応じて変化しやすいことも事実です。常に顧客の心理を推し量りながら、サービス向上に向けた適切な施策を打ち出して行く必要があるでしょう。
CS(顧客満足度)向上の施策に盛り込むべき5つの要素
効果的な施策を講じるには、何が顧客に影響を及ぼすのかを把握した上で、施策に盛り込む必要があります。ここでは、施策検討の際に考慮しておきたい要素とその手法をご紹介します。
1.顧客を発信元とした推奨
化粧品や消費財など、対象が日常的で身近なものであればあるほど、消費者は同じ消費者の立場から発信された情報を信頼する傾向が高まります。
例えば、SNS等での体験談や商品レビューは、企業が発表する公式情報よりも公平で客観性があると感じる人が多いため、新規顧客の獲得につながりやすいのです。
そのため、顧客を発信元として推奨拡大する手法は、CS向上施策に取り入れたいもののひとつです。
具体的には、実際に利用経験のある顧客のなかから協力者を募り、WEBで口コミ情報やレビューをアップしてもらう、といった形になります。
このとき、なるべく利用歴が長く、商品やサービスに愛着のあるユーザーを選択するようにしましょう。
発信元となる顧客次第で、客観性と信頼性の高い広告宣伝が実現することも、逆に、思ったような共感を得られないケースもあるため、慎重に選ぶことをおすすめします。
2.事前期待のコントロール
顧客が持つ事前期待は、ある程度コントロールすることができます。
前述の通り、顧客満足度は事前期待に大きく依存しています。例えば、商品購入時に実像を超えた過度な期待をさせてしまうと、実際の利用シーンでは「思ったほどよくなかった」と落胆し、満足度も低下することになります。
商品・サービスの価値に見合った適正な期待値を持ってもらえるよう、コントロールすることも必要です。
そのために効果的な施策が、マイナス情報の開示です。
まず、顧客アンケートなどを通して、顧客が商品・サービスのなかで「我慢していること」「やむなく妥協していること」などを調査します。その結果から商品・サービスのウィークポイントのようなマイナス情報を洗い出し、公式サイト情報やカタログ、営業シーンなどで開示します。
特に新発売、新リリース等により著しく注目度が高いなど、期待値が過度に高まっていると判断される場合は、熱を冷ますためのマイナス開示が有効に働くでしょう。
顧客が最初からマイナス要素を把握していれば、過度な事前期待を持たずにすむため、利用後に落胆させることも少なくなります。事前に認識しているウィークポイントは顧客にとって評価の対象外となることが多く、他の長所に目を向けてもらいやすくなる点もメリットです。
コントロールによって適正値となった事前期待と満足体験は、企業の信頼度とともに顧客満足度を向上させてくれるでしょう。
ただし、開示するマイナス情報は、競合する商品・サービスとのバランスを見ながら精査、選択するようにしてください。
3.損失回避による安全性の立証
損失回避の法則は行動経済学の分野で提唱された理論で、「人間は利益から得られる満足より損失の苦しみの方が大きいため、得を求めるより損を避ける」という心理傾向を指したものです。
例えば、株取引をしたとします。
保有する株の価格が100万円値上がりした場合、「今後さらに上がって利益が増える」「一気に値下がりして元金割れする」という2つの可能性がありますが、多くの人は後者の不安を払拭できません。結果として、さらに増えるかもしれない利益よりも、損失を避け今ある100万円を確実に取るために、売却を選択します。
こうした心理傾向は、不動産や高級車などの高額商品、また手に取って見ることのできない通信販売などのジャンルで、特に強く見られます。
このとき返金保証などの対応があれば、損失のダメージを回避できるため顧客の安心感が増し、成約に結びつく可能性が高まるでしょう。
結果として返品や返金がなかったとしても、購入・利用時の不安が払拭されたことで満足度の向上にもつながりやすいのです。
なお、返金保証の基準やシステムについては、景品表示法等の法令遵守を心がけ、顧客とのトラブルを避けるため明文化しておくことをおすすめします。
4.顧客体験のイメージ
マーケティングの概念のひとつに「カスタマーサクセス」があります。これは、企業が顧客を成功に導くための行為や施策を指します。
顧客は、それぞれ目的や希望を持って商品やサービスを購入・利用しているものです。それに対して企業側は、先回りしてフォローしたり積極的に利用方法を提案したりすることで、顧客に成功体験をもたらし、同時に企業の利益にもつなげようという考え方です。
売って終わりにせず、顧客が抱くであろう不満や疑問を予測し、能動的にフォローの働きかけを行なうことで、顧客満足度の維持、向上が実現するでしょう。
ただし、継続的なフォローにはコストがかかります。
本当に必要なフォローを絞り込むためにも、定期的なリサーチが必要となるでしょう。
5.定期性を持った期待感の醸成
同じ商品やサービスでも、定期的にリニューアルを行うことで、新たな期待感を醸成することができます。
例えば成分や原料の見直しを行ったり、細かいサービスを追加したりした際、顧客に向けてリニューアルの告知をすれば、新商品開発の手間を大幅に軽減しつつ、興味関心を引くことができるのです。
さらに、リリース後もブラッシュアップを怠らず、より良いものを追求しようとする企業の誠意もアピールできるため、一石二鳥の施策と言えるでしょう。
顧客の要望や不満を受けてのリニューアルであることを訴求すれば、消費者の声に耳を傾けてくれたという満足感にもつながり、より効果的です。
CS(顧客満足度)向上に効果的な7つの施策
次に、顧客満足度を上げるために効果的な施策を7点ご紹介します。可能なものから取り入れてみてください。
CS向上施策1.きめの細かい接客教育の徹底
CS向上のためには、接客品質の向上が必須項目のひとつです。人は商品、サービス自体のクオリティだけでなく、実際に接した相手の印象も総合的に捉えて評価するからです。
例えば、レストランで出された料理がいかにおいしくても、店員の接客態度が悪ければ不愉快になり、トータルでのCSは低下してしまいます。逆に、料理はまあまあでも、サービスがよく店員の感じがよければ、また来ようという気になる……といったケースは、誰しも経験があるのではないでしょうか。
消費シーンにおける接客態度は、顧客の意思決定を左右する重要なファクターであることを念頭に、受注・発注業務や問い合わせ対応も含めたお客様対応の品質向上に努める必要があるのです。
また、サービスクオリティの平準化を図ることも重要です。
接客を各人の裁量に任せてしまうと、サービスレベルが個々の性格や経験値に左右されることになりかねません。A店では丁寧に接客してくれたのに、B店ではずさんな対応だった、ということになれば、顧客満足度に大きなばらつきが生じます。
どの店舗でも同じレベルの接客品質を確保するため、接客に関わる適切なマニュアルを整備し、スタッフ全員が遵守するよう徹底しましょう。
CS向上施策2.顧客アンケートの定期実施
定期的にアンケートやインタビューを実施し、顧客が抱えている不満や潜在的なニーズなどを把握することも重要です。
企業側が考える「よいサービス」と、顧客が考える「よいサービス」との間に隔たりがあるケースも少なくありません。あるべき姿と現状のギャップを埋め、サービス向上を図るためにも、まず重要なのは調査です。
いまの接客で顧客は満足しているのか、次の施策は本当に実情に沿っているかなど、CS向上に向けた今後の課題や改善のヒントが得られるでしょう。
CS向上施策3.商品やサービスの高付加価値化
すでに説明したように、CS(顧客満足度)は、顧客が抱える期待値を結果が上回ったときに上がります。
企業としてよい商品、よいサービスを追求することは当然ながら、「おいしい」「便利」「使いやすい」などの機能的価値から生まれる満足度は、顧客が事前に抱いていた期待値によって左右されるため、予測しづらいことも事実です。
そのため、機能的価値は維持しつつ、さらにお客様満足を高める付加サービスを実施することで、総合的に顧客の期待値を超える施策を検討しましょう。
商品・サービスの体験が万一期待値を下回っていた場合でも、付加サービスによって総合的な満足度が上がれば、CS向上につながる可能性は高くなるのです。
CS向上施策4.従業員満足度の向上
顧客満足度と同時に、ES(従業員満足度)にも目を向ける必要があります。
ESが低いと社員のモチベーションが低下しやすいため、勤務態度が悪化するだけでなく、顧客サービスの品質低下にもつながります。
逆にESが高い場合は、業務に熱意を持って取り組むことができるので、サービス品質も向上するでしょう。つまり、ESは顧客満足度に間接的に影響する要素なのです。
ESを上げるためには、アンケートやヒアリングを通して社員の満足度や不満点を定期的に確認することが重要です。従業員研修を行い営業スキル向上や業務効率改善に取り組む、福利厚生を見直すなど、状況に応じて適切な施策は異なります。
社内の課題を整理検討し、総合的に取り組むとよいでしょう。
CS向上施策5.顧客接点の増加
リピーターを獲得するためには、顧客との接点を増やす必要があります。
そのために有効な施策が、ポイントマーケティングの導入です。
商品購入やサービス利用実績に応じてポイントを付与するシステムは、顧客のメリット感を増大させるだけでなく、再来店・再訪問を促す効果が高いため、顧客接点を増やすことにつながります。
ただし、ポイントシステムの構築には大きなコストが発生します。特に顧客満足度の高いポイント交換を独自に導入すると、さらにコストが増大することになるため、ポイント交換ソリューションを上手に利用するとよいでしょう。
たとえば、ジー・プランが提供するポイント交換ソリューション「Gポイント交換」では、Gポイントを経由することで、独自ポイントを100種類以上のポイント銘柄に交換することができます。また、約150社のポイントと提携する「ポイント・コンセント」なら、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントに、ユーザー自身で直接交換可能です。
こうしたソリューションを活用すれば、コストを抑えつつ顧客の利便性を上げ、効果的にリピート率向上につなげることができます。
成功事例のひとつをご紹介しましょう。
関西電力の会員向けポイントサービスを運用する株式会社かんでんCSフォーラム(大阪府大阪市)では、「ポイント・コンセント」を導入したことで、運用コストを約4割カットすることに成功しました。
また、交換先銘柄の追加にかかるシステム開発が不要となったこと、データ連携や精算の一元化が可能となったことなどから、ポイント交換先の拡充が実現し、会員の満足度は大きく上昇。ポイントサービス開始当初25万人ほどだった会員数が、現在では250万人(2022年2月時点)と、大幅に増加しています。
ポイントマーケティングはCS向上につながる魅力的な施策ですが、さまざまなコストを考慮しつつ効率化を模索する必要があるという示唆に富んだ事例と言えるでしょう。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/03
CS向上施策6.CRMやSFAの活用
適切なシステムの導入により業務の効率化を図ることも、CS向上のためには有効です。
業務効率化につながるシステムとしては、CRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援システム)などがあります。
CRMでは、顧客購買履歴や閲覧履歴などを総合的に把握することが可能です。SFAは営業支援のためのツールで、営業活動を通した顧客管理や顧客情報分析を行うことができます。
こうしたツールを利用すれば、営業の進捗や事前期待値を含む顧客情報を、部署全体で共有しつつ適切に管理できるようになるため、自社製品・サービスの開発及び改善の効率化が望めるでしょう。
近年では、CRMとSFA両方の機能を備えたツールも増えているので、自社に合ったものを選ぶようにしてください。
CS向上施策7.コミュニティ形成
コミュニティの形成によって、商品・サービスへの愛着を育む方法もあります。
商品・サービスを通じて顧客同士が交流できる独自のコミュニティでは、商品・サービスに関するポジティブな帰属意識を育むことが可能です。年代、性別を超えたメンバー同士の交流も、顧客にとっての付加価値につながるでしょう。
顧客のみではなく、そこに企業が介在するコミュニティも、マーケティング面から見て非常に有益です。
最近は、FacebookやInstagramなどのSNSを通じて、顧客と接点を持つ企業も増えてきましたが、こうしたコミュニティがあれば、開発側からは見えなかった商品の長所短所やリアルな使用感、サービスの課題などをユーザーから直接聞くことができます。
ここで得た新たな気づきをマーケティングに活かすことで、より具体的、実践的な商品開発が可能となるでしょう。
さらに、参加メンバーは直接企業と意見交換することで当事者意識が高まり、企業や商品への愛着もより強くなります。結果としてロイヤルカスタマー育成につながるでしょう。
CS(顧客満足度)向上の施策として参考にしたい成功事例3選
ここからは、実際にCS向上の取り組みに成功した企業の事例をご紹介します。
事例1:エネルギー会社
ガス・電気の小売事業に主軸を置くエネルギー会社、大阪ガス株式会社では、2009年に会員専用サイト『マイ大阪ガス』の運営を開始。当初付与していたのは、サイト内でのみ利用可能なオリジナルポイントですが、ユーザーからは「共通ポイントに交換したい」との声も上がっていました。
ガス・電力の自由化でユーザーが自由に契約先を選べるようになった状況を受け、顧客との長期的な関係構築を模索していた同社は、会員サイトのリニューアルを決断。顧客体験を向上させ、会員数を増やすことを目的として、ジー・プランが提供する「ポイント・コンセント」導入を決めたのです。
2021年3月、全国的に普及している共通ポイントに、大阪エリアで利用可能な地域密着型ポイントを加えた合計6銘柄を交換先に選び、新サービスをスタート。
以前の会員数は80万人でしたが、リニューアル後は2021年末までに20万人が新規会員登録し、会員数100万人を突破するなど、これまでにない伸びを見せています。2022年も新規会員登録者数は15万人となりました。
リニューアル後に行ったアンケート調査では、お客様満足度が10%アップしており、ポイント施策の成功がCS向上の大きな要因と考えられます。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/06
事例2:クレジットカード会社
大丸松坂屋百貨店などの運営元であるJ.フロントリテイリングのグループ会社、JFRカード株式会社が発行する『大丸松坂屋カード』『大丸松坂屋ゴールドカード』では、クレジットカードでの決済時に大丸・松坂屋のポイントが付与されます。貯まったポイントは大丸松坂屋百貨店での買い物や食事の際に利用できるため、顧客にとってのメリットはもちろん、店舗にとってもリピーター獲得などの効果があります。
ただ、利用シーンが限定されていることから、利用者の拡大という面では課題もありました。そのため、新たに『QIRA(キラ)ポイント』というポイント特典に変更。カード加盟店の決済時にはQIRAポイントが、大丸松坂屋百貨店での決済時には大丸・松坂屋のポイントとQIRAポイントの双方が付与されることになったのです。
これだけでも顧客メリットはアップしますが、同社ではさらにポイントの活用先の拡大を検討し、ジー・プランの「ポイント・コンセント」導入を決定します。決め手は、ポイント交換先が約150銘柄と豊富であったこと。
導入後は、ポイント交換先が増加したことに対するお客様の喜びの声が多数寄せられるなど、満足度の観点からも高く評価されています。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/05
事例3:専門広告会社
年間約300件のキャンペーンを手がけるなど、企業向けセールスプロモーションのサポートを行う株式会社ディー・エム広告社。同社でキャンペーン支援ツールとして開発されたのが、WEB応募サイト制作サービス『Dohbo(ドーボ)』でした。ただ、キャンペーンの内容・ターゲットは顧客企業によって多種多様なだけに、景品発行機能を実装する際には、いかに景品ラインナップを充実させるかという課題がありました。
そこで選択したのが、ジー・プランが提供する「Gポイントギフト」です。「Gポイントギフト」は、一円単位で発行が可能で、100種類以上のラインナップに交換できる電子ギフトサービスです。
同社の『Dohbo』を活用した大手石油元売企業でのキャンペーンでは、「Gポイントギフト」が景品として採用されました。コンビニなどガソリンスタンド併設店舗で商品を購入すると応募が可能となり、加えて先着で全員に100Gポイントギフトをプレゼントするといった施策です。
キャンペーンを展開後、併設店舗間での相互送客率は、前年比150%増を記録。顧客企業からは、応募や当選、景品発送の手間が省けるなど各店舗の負担が大幅に軽減したとして、高い評価を受けています。
顧客企業に以前から提携している電子マネー・ポイントが複数ある場合、キャンペーンの景品をいずれかに絞ることは難しいものです。その点「Gポイントギフト」では、多種多様な景品を広くカバーすることが可能なため、顧客への配慮という面でも満足度向上につながったのでしょう。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/07
CS(顧客満足度)向上の施策に関するよくある質問
【小見出し】質問1.CS(顧客満足度)向上の施策で役立つ目標や指標はありますか?
主な評価指標としては、次のようなものが知られています。
1.LTV(Life Time Value)
顧客が商品・サービスの利用を開始してから終了するまでの間に得られる売上を表したもの。LTVが高いほど顧客ロイヤルティが高まる傾向があるため、ロイヤルカスタマーの実数を測る指標としても活用できます。ただし、長期にわたる消費活動をベースにした数値なので、短期的な目標設定には不向きな点に注意しましょう。
2.CSI(Customer Satisfaction Index)
世界約30ヵ国で利用されている顧客満足度を測定するための指標。自社製品に関連する「顧客期待値」「知覚品質」「知覚値」「顧客不満度」「顧客忠実度」の5項目から構成されています。データ数が多いほど信頼性の高い結果を得られるため、大企業や政府等の調査によく用いられます。
3.JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)
CSIを日本国内向けにカスタマイズしたもの。CSIの5項目に「推奨意向(商品を他人に勧めたいか)」を加えた6項目となっています。利用前から利用後までの全体を調査分析することで、最初の期待値や利用後の評価、価格への納得感など、顧客の心理的背景を算出することが可能。業界や業種を問わず利用できる点も特長です。
4.C-SAT(Customer Satisfaction)
顧客満足度を見る際にもっともよく利用される指標のひとつ。「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」などを、星や数字によって視覚的に評価してもらいます。自由記述欄を設け、自社の商品・サービスや課題に沿った形で実施することも可能です。
5.CES(Customer Effort Score)
日本語では「顧客努力指数」。「欲しい商品を探し当てるのが大変だった」「商品の使い方がよくわからない」など、顧客がその商品やサービスを利用する際、どの程度の「努力(負担)」が必要であったかが分かります。CESが高ければ顧客の不満が多く、低ければ少ない、つまりロイヤルティが高いと判断できます。
6.NPS®(Net Promoter Score)
顧客ロイヤルティを示す指標。「商品やサービスを人に勧める可能性はどのくらいあるか」を、11段階で評価してもらう形式です。満足度は各人の解釈の相違が生じやすい面もありますが、NPS®では意味や対象が具体化されているため、回答のブレが少ない点が特徴です。
7.CRR(Customer Retention Rate)
「顧客維持率」を表す指標で、既存の顧客が一定期間にどの程度取引を続けているかがわかるため、スコアが高ければ顧客満足度も高いと考えてよいでしょう。スコアが下がる大きな原因は、商品やサービス自体の品質よりも、問い合わせ時の対応が悪かったなど心理的な要素が大きいとされています。よい顧客体験を提供できるよう、改善や見直しのきっかけとして活用しましょう。
質問2.CS(顧客満足度)向上のための具体的な取り組みとは?
一般的には以下のような取り組みが挙げられます。
・アンケート・インタビューの実施
企業側が考える「よいサービス」と、顧客が考える「よいサービス」との間に隔たりがあるケースも。まずはアンケートやインタビューを実施し、顧客が抱えている不満や潜在的なニーズなどを把握しましょう。
・接客品質を高める
消費活動においての接客態度は、顧客の意思決定を左右する重要なファクターです。受注・発注業務や問い合わせ対応も含めたお客様対応の品質向上に努めましょう。
・サービスクオリティの平準化を図る
サービスレベルが人によって異なると、不信感につながります。どの店舗でも同じレベルの接客品質を確保するため、接客マニュアルを整備し、サービスクオリティを平準化しましょう。
・情報提供の流れを円滑化する
顧客に疑問や不明点があれば気軽に情報を得られるよう窓口には複数のチャネルを設け、スムーズな情報提供に努めましょう。過去の問い合わせ内容、やり取りについても、すぐに参照できるとよいでしょう。
・顧客の期待値を超える
「おいしい」「便利」といった機能的価値を維持しつつ、さらにお客様満足を高める付加サービスを実施することで、総合的に顧客の期待値を超える施策を検討しましょう。
・ポイントマーケティングの導入
商品購入やサービス利用実績に応じてポイントを付与するシステムは、顧客のメリット感を増大させるだけでなく、再来店・再訪問を促す効果が高いため、顧客接点を増やすことにつながります。
質問3.CS(顧客満足度)とNPS®(顧客ロイヤルティ)の違いは?
CS(顧客満足度)とは、顧客が商品やサービスに対してどの程度満足しているかを、「NPS®」は「顧客が特定の商品やサービスを周囲に勧める割合」を表すものです。
CSでは、商品やサービスを利用した時点での「個人的な満足度」を示しているのに対し、NPS®では比較的長期的な目線での「他者への推奨度」を示している点が大きく異なります。
後者の場合、責任範囲が他者に及ぶことから回答者が慎重になる傾向があり、よりリアルな顧客ロイヤルティを測ることができます。
【まとめ】
以上、CS(顧客満足度)向上施策の基本的な考え方と必要な要素、また、具体的な施策をご紹介しました。
消費者が商品・サービスの選択時に重視するのは、品質や価格だけではありません。接客品質はもちろん、利用までの流れやトラブル時の対応、さらには利用に至った目的とその結果をも踏まえた総合的な満足度が、継続的な選択決定の後押しとなります。
そのため、各シーンでCS向上を念頭に置いた施策を講じる必要があるだけでなく、それぞれの状況において、顧客自身の心理面にまで踏み込んだ施策が求められるのです。
商品・サービスに、いかに消費層とマッチした付加価値を与えられるか、また、それをいかに自社のお客様に伝えられるかが、現代の企業にとっての重要命題と言えるでしょう。
その際に重視すべきは、まず顧客接点を増やすことにほかなりません。接点がなければ、付加価値を訴求することも、相手の心理を推し量ることも困難だからです。
ポイントマーケティングは、そのための施策として非常に有効なもののひとつです。
来店や購入、利用の際にポイントを付与する仕組みは、顧客の再来店・再来訪を促す効果があるため、顧客接点を増やすことが可能となります。
また、ポイント付与のメリット感自体も付加価値につながり、トータルでの満足感向上に寄与するでしょう。
ただし、特定企業・店舗のみで利用可能な独自ポイントは利用シーンが限定されるため、訴求力を考慮するなら、ポイント交換も併せて導入することをおすすめします。
ジー・プランの提供するポイント交換ソリューション「ポイント・コンセント」「Gポイント交換」なら、コストを最小限に抑えつつ、ポイント交換の利便性を顧客に提供することが可能です。CS向上施策の一環として活用することを、是非ご検討ください。
おすすめの資料はこちら
関連記事








