
CS(顧客満足度)向上のための取り組みとは?具体的な手法・企業の成功事例を分かりやすくご紹介
現代のビジネスシーンにおいて、CS(顧客満足度)の向上は、企業の命運を握る非常に重要な要素です。しかし商品の品質だけでは、CSを飛躍的にアップさせることはできません。
では、具体的にどのような施策を打ち出せばCS向上が実現するのでしょうか。そのためにはまず、CSの基本やCS向上が重要視される背景、CS向上によりもたらされるメリットを押さえた上で、自社のサービスや顧客にマッチした施策を打ち出す必要があります。
本記事では、CS向上の効果的な取り組みについて、CS向上が重要視される背景やCS向上の6つのメリット、具体的な手順とともに解説しています。
また、実在企業のCS向上成功事例や、施策検討の際に活用したい評価指標についてもまとめました。これからCS向上のための新たな施策を検討している、あるいはすでに実施済みの施策を見直す際に、ぜひ参考にしてください。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 顧客満足度が重要視される背景には、企業数増加やSNSの普及、企業間競争の激化がある
✓ポイント2 CS向上の取り組みを強化する際は、まず顧客の不満やニーズを吸い上げ、期待値を把握しておく
✓ポイント3 各企業の成功事例を参考に、各評価指標も活用してCS向上の取り組み施策を検討する
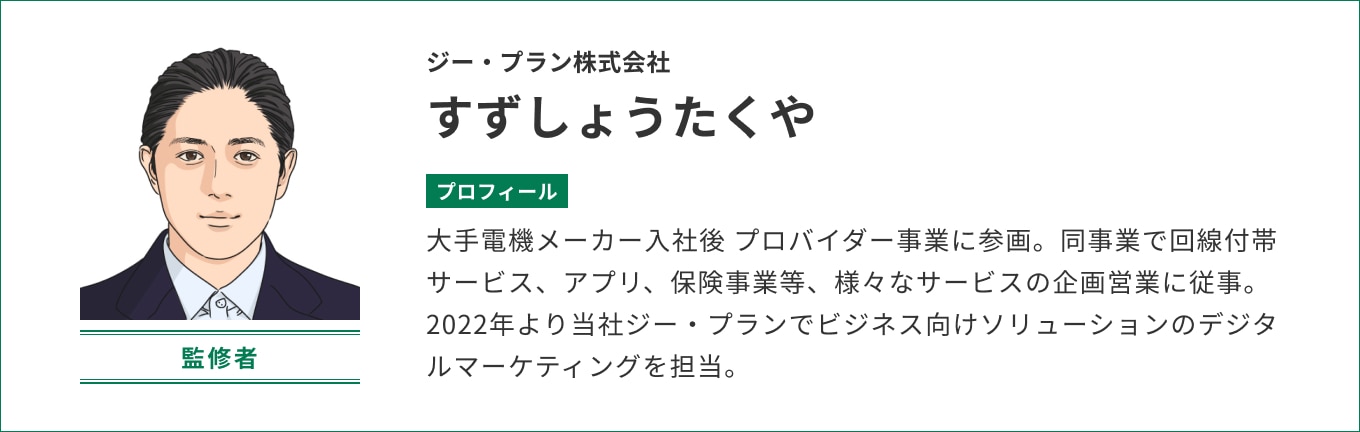
目次[非表示]
- 1.CS(顧客満足度)とは?
- 2.CS(顧客満足度)が重要視されている背景
- 2.1.企業数の増加による企業間競争の激化
- 2.2.SNSによる好評・悪評の拡散
- 2.3.ロイヤルカスタマーの重要性の向上
- 3.CS(顧客満足度)向上による6つのメリット
- 3.1.メリット1,リピート率が向上する
- 3.2.メリット2,リピーター獲得によるLTVの向上につながる
- 3.3.メリット3,口コミ・SNSによって新規顧客を集客できる
- 3.4.メリット4, 自社がより幅広く認知される
- 3.5.メリット5,自社のブランド力が向上する
- 3.6.メリット6,副次的に採用ブランディング・離職率ダウンにつながる
- 4.CS(顧客満足度)向上のための具体的な取り組み
- 4.1.顧客フィードバックの収集と活用
- 4.2.顧客の期待値の正確な把握
- 4.3.従業員教育による接客の品質向上とカスタマーサポート強化
- 4.4.サービスクオリティの平準化
- 4.5.リアルタイムでの問題解決対応
- 4.6.顧客の期待値を超える商品やサービスの提供
- 4.7.顧客体験の継続的な改善
- 4.8.長期的な顧客ロイヤルティの育成
- 5.CS向上のためのツールとシステムの導入
- 5.1.CRM・SFAの導入
- 5.2.デジタルツールを活用した顧客対応
- 5.3.ポイントマーケティングの導入
- 6.CS(顧客満足度)向上の取り組みに成功した企業の事例
- 6.1.事例1:エネルギー会社
- 6.2.事例2:クレジットカード会社
- 6.3.事例3:専門広告会社
- 7.CS(顧客満足度)の評価指標
- 7.1.1.LTV(Life Time Value)
- 7.2.2.CSI(Customer Satisfaction Index)
- 7.3.4.C-SAT(Customer Satisfaction)
- 7.4.5.CES(Customer Effort Score)
- 7.5.6.NPS®(Net Promoter Score)
- 7.6.7.CRR(Customer Retention Rate)
- 8.まとめ
- 9.おすすめ資料はこちら
CS(顧客満足度)とは?
CS(顧客満足度)向上とは、顧客が製品やサービスに対してより高い満足感を得られるようにするための取り組みを指します。具体的な例として、カスタマーサポートの充実、個別対応やパーソナライズされたサービスの提供、迅速な問題解決が挙げられます。
例えば、あるECサイトが購入後のフォローアップメールを送ることで顧客の満足度を高めることや、定期的なアンケート調査を行い、フィードバックをサービス改善に活かすといった施策があります。
CS(顧客満足度)が重要視されている背景
企業にとってCSの向上は非常に大切なものですが、特に現代においては重要性がより高まっています。その背景を考察していきましょう。
企業数の増加による企業間競争の激化
CS向上の取り組みがより重要視されるようになった最も大きな要因は、企業間競争の激化にあります。
昔に比べて企業数自体が増加しているうえ、異業種参入や多角化、グローバル化が進み、競合範囲はより一層拡大しました。従来なら競合とはならなかった企業が自社のサービス領域に進出してくる、といったケースも珍しくないでしょう。
こうして顧客獲得争いが激化するなかで、自社の商品を手に取ってもらうことは、決して容易ではありません。
もちろん他社にはない商品、サービスを提供することが最重要課題ではありますが、たゆまず新製品を生み出し続けるには、時間・人・金銭などさまざまな面でコストがかかります。また、技術の発展により、製品ごとの品質の差が少なくなったことも無視できません。
こうした状況を背景に、「同じような商品ならこちらを選ぶ」という動機付けの根拠として、CSをはじめとする商品・サービスの付加価値に対する重要性が高まっているのです。
SNSによる好評・悪評の拡散
また、インターネットの影響も大きいでしょう。
ここ数十年、SNSは一層広がりを見せ、さまざまなサービスが登場しています。
その拡散性は非常に高く、ときとして利用ユーザーの口コミ情報は、提供側である企業の情報量をも凌駕します。
商品購入やサービス利用の前に、消費者がまずインターネットで利用者のレビューや口コミ情報に目を通すという行動も、すでに定着しているといえるでしょう。
それだけに、ネットにおける商品やサービスの評価は極めて重要です。
よい評価がそのまま商品の売り上げに直結することもある一方で、悪い評価が増えれば企業にとっての大ダメージになりかねません。
顧客の満足度を高め、好意的な口コミを増やすことは、SNS対策としても重要なのです。
ロイヤルカスタマーの重要性の向上
ロイヤルカスタマーとは、利用金額や利用頻度が多く、企業ブランドへの愛着・忠誠心の強い顧客を指します。容易に他社製品への乗り換えをせず売り上げに貢献するだけでなく、自発的に企業ブランドの良い評価を広めてくれる存在です。
多くの企業にとってロイヤルカスタマーの獲得・育成は非常に大切な要素ですが、前述した競合商品・サービスの増加、またSNSの普及による拡散性の向上などを背景として、現在ではその重要性がさらに増しています。
ロイヤルカスタマーを獲得・育成するためには、顧客の期待値を超えるメリットを提供する必要があります。そのためにはCS向上の取り組みが欠かせません。
CS(顧客満足度)向上による6つのメリット
メリット1,リピート率が向上する
CS(顧客満足度)向上のメリットのひとつは、リピート率の向上です。顧客が製品やサービスに満足すると、再び同じブランドを選ぶ可能性が高まります。
例えば、迅速なカスタマーサポートやパーソナライズされたサービス提供が顧客の信頼感を強化し、リピート購入を促進します。満足した顧客は、他社への乗り換えを考えにくくなり、さらに友人や家族に商品やサービスを推薦する可能性も高まり、結果的に売り上げや利益に貢献します。
中長期的に売り上げを支えてくれるリピーターの獲得は、マーケティング上極めて重要な課題なのです。
メリット2,リピーター獲得によるLTVの向上につながる
一人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の指標を「LTV(Life Time Value)」といいます。CS向上に伴って既存客がリピーターとなり、利用頻度や購入金額に比例して、企業に利益をもたらしてくれます。つまり、LTVの向上が見込めるということです。
さらに、利用シーンなどでパーソナライズ化された顧客満足度を十分に提供することができれば、ブランドへの愛着と忠誠心を持つ「ロイヤルカスタマー」の育成に成功する可能性も高まるでしょう。
メリット3,口コミ・SNSによって新規顧客を集客できる
CS向上は、新規顧客の獲得とも密接に結びついています。
気に入った商品やサービスを友人知人に推薦するといった行動は従来からあるものですが、前述の通り、現代はとりわけSNSでの口コミ評価が存在感を増しています。
顧客満足度が上がり、インターネット上に高評価が浸透すれば、評判を目にした新規顧客の購入・利用が促進されるため、集客効果は非常に大きいでしょう。
従来のような販促活動を通して新規顧客を獲得しようと考えると、多大なコストが必要です。効果的な集客を考えるならば、新規顧客に向けた広報宣伝にリソースを割くより、顧客満足を心がけ、CS向上の取り組みを強化する方がはるかに効果的で、費用対効果の面でも優れているのです。
メリット4, 自社がより幅広く認知される
口コミ評価が増えることにより、自社の認知度アップが期待できます。
「認知度が高い」とは、社名やブランド名だけでなく、扱っている商品の傾向やサービス内容の概要までが知られている状態を指します。
もちろん企業広告や商品広告の効果もありますが、やはり身近な人によるユーザー目線でのリアルな体験談や、フォロワーの多いインフルエンサーの発言は影響力が大きいもの。
顧客の満足度が向上することにより、具体的な商品、サービスの内容に言及した好意的な口コミが増えれば、ポジティブなイメージとともに自社の認知度を高めることができます。
メリット5,自社のブランド力が向上する
CSの高低は、ブランドイメージにも大きな影響を与えます。
評判の良い商品、サービスは、それだけで世間から好意的に受け入れられるものです。さらに、固定客の多さは安定したサービス品質の根拠となって、企業自体のイメージも底上げしてくれます。
ブランドのネームバリューで他社より優位に立つことができれば、価格競争に巻き込まれにくくなり、事業展開もスムーズに進めることができます。
また、リピーターが自発的に良い情報を発信してくれるので、広告宣伝のために多額の費用をかける必要がなくなり、経費削減も実現できるでしょう。
メリット6,副次的に採用ブランディング・離職率ダウンにつながる
CSの高い企業は、社員にとって働き心地の良い環境でもあります。
「自分の仕事が社会の役に立っている」という実感は、働く人間のモチベーション維持において重要な要素のひとつです。
CSが高いということは、顧客がその企業の商品・サービスを好意的に捉えているということですから、やりがいや手応えを感じられる機会は自然と増加するでしょう。
こうした環境では、社員の定着率が高く、離職率は低くなる傾向が見られます。
さらに、世間的にポジティブなイメージが浸透すると、ここで働きたいと感じる人も増加するため、採用活動がスムーズになります。
優秀な求職者を多数集めることができれば、将来を見据えた採用ブランディングも容易になるでしょう。
CS(顧客満足度)向上のための具体的な取り組み
では、どうすればCSを向上させることができるのでしょうか。具体的な取り組みとしては、主に以下のような方法があります。
顧客フィードバックの収集と活用
CS(顧客満足度)向上のための取り組みとして、まずは顧客フィードバックの収集と活用が欠かせません。具体的には、アンケートやインタビューを実施し、顧客が抱えている不満や潜在的なニーズなどを把握する必要があります。
企業側が考える「良いサービス」と、顧客が考える「良いサービス」との間に隔たりがあるケースも少なくありません。あるべき姿と現状のギャップを埋め、サービス向上を図るためにも、まず重要なのは調査です。
いまの接客で顧客は満足しているのか、次の施策は本当に実情に沿っているかなど、CS向上に向けた今後の課題や改善のヒントが得られるでしょう。
顧客の期待値の正確な把握
CS向上のためには、顧客の期待値を正確に把握することもポイントとなります。商品やサービス自体への期待値がわからなければ、付加サービスの内容やメリットのレベル感を正しく設定できず、結果として顧客のニーズとズレた施策となってしまうリスクがあるためです。
前述したアンケートやインタビューは、顧客の本音を知ることができるだけでなく、こうした期待値を正しく把握するためにも非常に有効です。上手に活用し施策に活かしていきましょう。
従業員教育による接客の品質向上とカスタマーサポート強化
CS向上のためには接客品質の向上が必須項目のひとつです。人は商品、サービス自体のクオリティだけでなく、実際に接した相手の印象も総合的に捉えて評価するからです。
例えば、レストランで出された料理がいかにおいしくても、店員の接客態度が悪ければ不愉快になり、トータルでのCSは低下してしまいます。逆に、料理はまずまずでも、サービス品質が十分であり、スタッフの応対がよければ、また来店しようという気持ちになる……といったケースは、誰しも経験があるのではないでしょうか。
消費活動においての接客態度は、顧客の意思決定を左右する重要なファクターであることを念頭に、受注・発注業務や問い合わせ対応も含めたお客さま対応の品質向上、ひいてはカスタマーサポートの強化に努める必要があります。
サービスクオリティの平準化
CS向上のために、サービスクオリティの平準化を図ることも重要です。
接客を各人の裁量に任せてしまうと、サービスレベルが個々の性格や経験値に左右されることになりかねません。A店では丁寧に接客してくれたのに、B店ではずさんな対応だった、ということになれば、顧客満足度に大きなばらつきが生じます。
どの店舗でも同じレベルの接客品質を確保するため、接客に関わる適切なマニュアルを整備し、スタッフ全員が遵守するよう徹底しましょう。
リアルタイムでの問題解決対応
顧客が抱える疑問点や不明点をスピーディーに解決するためには、気軽に情報を得られる窓口と、スムーズな情報提供の仕組み作りが必要となります。
ここで重要な点は、以下の2点です。
- 顧客が都合に合わせて選択できるよう、複数の連絡手段を確保すること
- 過去のやり取りがすぐ参照できるようにすること
情報提供の手段が電話のみ、メールのみなどの場合、手段選択の余地がなく、顧客の環境によっては不便を強いることになりかねません。
逆に電話、メール、チャットなど複数の連絡手段が用意されていれば、課題解決のための情報を得やすくなり、顧客満足につながります。
また、同様のトラブルで複数回の問い合わせがあったとき、何度も同じ話を繰り返す必要があると、顧客はうんざりして満足度が低下してしまいます。逆に、過去の問い合わせ内容を踏まえた対応ができれば、自分を大切に扱ってくれたと感じ、CS向上につながるでしょう。
過去の問い合わせ内容やその際のやり取りについて、すぐに参照できる仕組み作りが重要です。
顧客の期待値を超える商品やサービスの提供
前段でご紹介した通り、CS(顧客満足度)は、顧客が抱える期待値を結果が上回ったときに上がります。
企業として良い商品、より良いサービスを追求することは当然ながら、「おいしい」「便利」「使いやすい」などの機能的価値から生まれる満足度は、顧客が事前に抱いていた期待値によって左右されるため、予測しづらいことも事実です。
そのため、機能的価値は維持しつつ、さらにお客さまの満足を高める付加サービスを実施することで、総合的に顧客の期待値を超える施策を検討しましょう。
商品・サービスの体験が万一期待値を下回っていた場合でも、付加サービスによって総合的な満足度が上がれば、CS向上につながる可能性は高くなるのです。
顧客体験の継続的な改善
顧客がブランドやサービスに対して常にポジティブな体験を得られるよう、定期的にプロセスや対応を見直し、改善することもCS向上の取り組みとして欠かせません。具体的には、定期的なフィードバックの収集や、顧客のニーズや期待の変化に対応したサービス向上が重要です。
例えば、顧客アンケートを活用し、サービスの弱点を特定して改善策を講じることで、長期的な顧客ロイヤルティやリピート率を高めることができます。
長期的な顧客ロイヤルティの育成
CS向上のために、顧客がブランドに対して持続的な信頼と愛着を持つように働きかけることも重要です。具体的には、定期的なフォローアップ、パーソナライズされたサービス提供、ロイヤルティプログラムなどを活用します。
例えば、購入後のアフターケアや特別な特典を提供することで、顧客はブランドに対する好意を強め、他社への乗り換えを防ぐことができます。これにより、長期的な関係が築かれ、リピート購入や推奨の可能性が高まります。
CS向上のためのツールとシステムの導入
CRM・SFAの導入
適切なシステムの導入により業務の効率化を図ることも、CS向上のためには有効です。
業務効率化につながるシステムとしては、CRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援システム)などがあります。
CRMでは、顧客購買履歴や閲覧履歴などを総合的に把握することが可能です。SFAは営業支援のためのツールで、営業活動を通した顧客管理や顧客情報分析を行うことができます。
こうしたツールを利用すれば、営業の進捗や事前期待値を含む顧客情報を、部署全体で共有しつつ適切に管理できるようになるため、自社製品・サービスの開発および改善の効率化が望めるでしょう。
近年では、CRMとSFA両方の機能を備えたツールも増えているので、自社に合ったものを選ぶようにしてください。
デジタルツールを活用した顧客対応
スマートフォンの普及により、SNSやアプリを利用したコミュニケーションや購買活動が活発化しています。これらのデジタルツールを活用した販売促進やPR活動は、スピーディーな情報提供や、キャンペーンの実施には必要不可欠となっています。
例えば、SNS上で顧客からの質問やクレームにリアルタイムで応答したり、アプリを通じてパーソナライズされたサービスや通知を提供することができます。これにより、顧客は必要な情報をすぐに得られるため、満足度が向上し、長期的な関係構築につながります。
デジタルツールの導入によって、効率的な顧客サポートが可能となるため、CS向上に欠かせないツールと言えるでしょう。
ポイントマーケティングの導入
商品・サービスの高付加価値化を目的とした施策のひとつに、ポイントマーケティングの導入があります。
商品購入やサービス利用実績に応じてポイントを付与することで顧客のメリット感が増大し、結果的に商品・サービスへの期待値を上回ることも可能になるでしょう。
CS向上だけでなく、囲い込み効果や集客効果も見込めるため、マーケティング戦略として非常に効果的な方法のひとつです。
ただし、ポイントシステムの構築には、人的にも金銭的にも大きなコストが発生します。特に顧客満足度の高いポイント交換を独自に導入すると、さらにコストが増大することになるため、ポイント交換ソリューションを上手に利用すると良いでしょう。
例えばジー・プランが提供するポイント交換・発行ソリューション「ポイント・コンセント」なら、約150社のポイントと提携しており、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントへ直接交換可能です。
こうしたソリューションを活用すれば、コストを抑えつつ利便性を上げ、効果的にCS向上を強化することができるでしょう。
CS(顧客満足度)向上の取り組みに成功した企業の事例
ここからは、実際にCS向上の取り組みに成功した企業の事例をご紹介します。
事例1:エネルギー会社
ガス・電気の小売事業に主軸を置くエネルギー会社、大阪ガス株式会社では、2009年に会員専用サイト『マイ大阪ガス』の運営を開始。当初付与していたのは、サイト内でのみ利用可能なオリジナルポイントですが、ユーザーからは「共通ポイントに交換したい」との声も上がっていました。
ガス・電力の自由化でユーザーが自由に契約先を選べるようになった状況を受け、顧客との長期的な関係構築を模索していた同社は、会員サイトのリニューアルを決断。顧客体験を向上させ、会員数を増やすことを目的として、ジー・プランが提供する「ポイント・コンセント」導入を決めたのです。
2021年3月、全国的に普及している共通ポイントに、大阪エリアで利用可能な地域密着型ポイントを加えた合計6銘柄を交換先に選び、新サービスをスタート。
以前の会員数は80万人でしたが、リニューアル後は2021年末までに20万人が新規会員登録し、会員数100万人を突破するなど、これまでにない伸びを見せています。2022年も新規会員登録者数は15万人となりました。
リニューアル後に行ったアンケート調査では、お客さま満足度が10%アップしており、ポイント施策の成功がCS向上の大きな要因と考えられます。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/06
事例2:クレジットカード会社
大丸松坂屋百貨店などの運営元であるJ.フロント リテイリングのグループ会社、JFRカード株式会社が発行する『大丸松坂屋カード』『大丸松坂屋ゴールドカード』では、クレジットカードでの決済時に大丸・松坂屋のポイントが付与されます。貯まったポイントは大丸松坂屋百貨店での買い物や食事の際に利用できるため、顧客にとってのメリットはもちろん、店舗にとってもリピーター獲得などの効果があります。
ただ、利用シーンが限定されていることから、利用者の拡大という面では課題もありました。そのため、新たに『QIRA(キラ)ポイント』というポイント特典に変更。カード加盟店の決済時にはQIRAポイントが、大丸松坂屋百貨店での決済時には大丸・松坂屋のポイントとQIRAポイントの双方が付与されることになったのです。
これだけでも顧客メリットはアップしますが、同社ではさらにポイントの活用先の拡大を検討し、ジー・プランの「ポイント・コンセント」導入を決定します。決め手は、ポイント交換先が約150銘柄と豊富であったこと。
導入後は、ポイント交換先が増加したことに対するお客さまの喜びの声が多数寄せられるなど、満足度の観点からも高く評価されています。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/05
事例3:専門広告会社
年間約300件のキャンペーンを手がけるなど、企業向けセールスプロモーションのサポートを行う株式会社ディー・エム広告社。同社でキャンペーン支援ツールとして開発されたのが、WEB応募サイト制作サービス『Dohbo(ドーボ)』でした。ただし、キャンペーンの内容・ターゲットは顧客企業によって多種多様なだけに、景品発行機能を実装する際には、いかに景品ラインアップを充実させるかという課題がありました。
そこで選択したのが、ジー・プランが提供する「Gポイントギフト」です。「Gポイントギフト」は、一円単位で発行が可能で、100種類以上のラインアップに交換できる電子ギフトサービスです。
同社の『Dohbo』を活用した大手石油元売企業でのキャンペーンでは、「Gポイントギフト」が景品として採用されました。コンビニなどガソリンスタンド併設店舗で商品を購入すると応募が可能となり、加えて先着で全員に100Gポイントギフトをプレゼントするといった施策です。
キャンペーンを展開後、併設店舗間での相互送客率は、前年比150%増を記録。顧客企業からは、応募や当選、景品発送の手間が省けるなど各店舗の負担が大幅に軽減したとして、高い評価を受けています。
顧客企業に以前から提携している電子マネー・ポイントが複数ある場合、キャンペーンの景品をいずれかに絞ることは難しいものです。その点「Gポイントギフト」では、多種多様な景品を広くカバーすることが可能なため、顧客への配慮という面でも満足度向上につながったのでしょう。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/07
CS(顧客満足度)の評価指標
CS向上の取り組みを強化したからといって、すぐに結果が出るとは限りません。継続的な評価を通して各施策を振り返り、PDCAサイクルを回す必要があるのです。そのためには、評価指標の設定が不可欠です。
主な評価指標としては、次のようなものが知られています。
1.LTV(Life Time Value)
顧客が商品・サービスの利用を開始してから終了するまでの間に得られる売り上げを表したもの。LTVが高いほど顧客ロイヤルティが高まる傾向があるため、ロイヤルカスタマーの実数を測る指標としても活用できます。ただし、長期にわたる消費活動をベースにした数値なので、短期的な目標設定には不向きな点に注意しましょう。
2.CSI(Customer Satisfaction Index)
世界約30ヵ国で利用されている顧客満足度を測定するための指標。自社製品に関連する「顧客期待値」「知覚品質」「知覚値」「顧客不満度」「顧客忠実度」の5項目から構成されています。データ数が多いほど信頼性の高い結果を得られるため、大企業や政府等の調査によく用いられます。
【小見出し】3.JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)
CSIを日本国内向けにカスタマイズしたもの。CSIの5項目に「推奨意向(商品を他人に勧めたいか)」を加えた6項目となっています。利用前から利用後までの全体を調査分析することで、最初の期待値や利用後の評価、価格への納得感など、顧客の心理的背景を算出することが可能。業界や業種を問わず利用できる点も特長です。
4.C-SAT(Customer Satisfaction)
顧客満足度を見る際にもっともよく利用される指標のひとつ。「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」などを、星や数字によって視覚的に評価してもらいます。自由記述欄を設け、自社の商品・サービスや課題に沿った形で実施することも可能です。
5.CES(Customer Effort Score)
日本語では「顧客努力指数」。「欲しい商品を探し当てるのが大変だった」「商品の使い方がよくわからない」など、顧客がその商品やサービスを利用する際、どの程度の「努力(負担)」が必要であったかがわかります。CESが高ければ顧客の不満が多く、低ければ少ない、つまりロイヤルティが高いと判断できます。
6.NPS®(Net Promoter Score)
顧客ロイヤルティを示す指標。「商品やサービスを人に勧める可能性はどのくらいあるか」を、11段階で評価してもらう形式です。満足度は各人の解釈の相違が生じやすい面もありますが、NPS®では意味や対象が具体化されているため、回答のブレが少ない点が特徴です。
7.CRR(Customer Retention Rate)
「顧客維持率」を表す指標で、既存の顧客が一定期間にどの程度取引を続けているかがわかるため、スコアが高ければ顧客満足度も高いと考えてよいでしょう。スコアが下がる大きな原因は、商品やサービス自体の品質よりも、問い合わせ時の対応が悪かったなど心理的な要素が大きいとされています。良い顧客体験を提供できるよう、改善や見直しのきっかけとして活用しましょう。
まとめ
ビジネス界において異業種参入や多角化、グローバル化が進み、競合範囲が拡大し続けているいま、顧客満足度の高低が事業の命運を分けると言っても過言ではありません。
顧客満足度が上がればリピーター獲得やロイヤルカスタマー育成につながるだけでなく、企業全体のブランド力が向上し、販売戦略や採用活動も有利に進めやすくなります。
CS向上の取り組み強化は、もはや企業にとって必須課題のひとつなのです。
ただし、曖昧な印象だけで施策決定すると、思ったほど効果が上がらないということになりかねません。
まずは適切な指標を用いた調査やアンケートで顧客の不満・ニーズをチェックし、サービスに対する期待値を正確に把握しましょう。現状を正しく認識したうえで、顧客の期待値を超えるためにはどの部分をブラッシュアップするべきかを検討することが、最も重要です。
同時に、ポイントマーケティングを導入し、ポイントによるメリット感を提供する方法もご検討ください。
記事中でご紹介した通り、ジー・プランが提供する「ポイント・コンセント」のソリューションを活用すれば、自社ポイントから多種多様な他社ポイントへの交換が可能になります。
商品やサービスを大きく変えるような取り組みが難しい場合でも、総合的に顧客の満足度を上げる効果が期待できるでしょう。
Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。
おすすめ資料はこちら
関連記事









