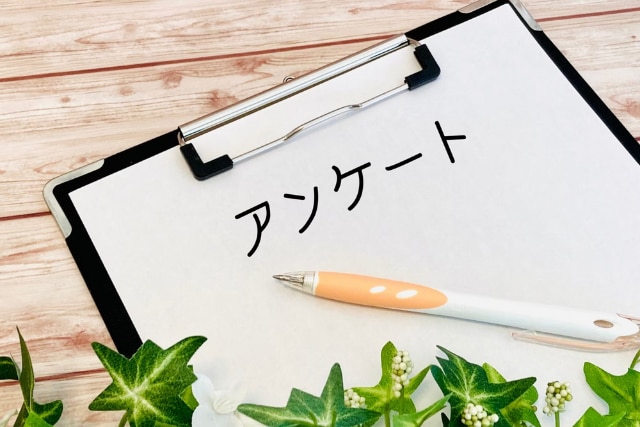
アンケート謝礼の目的や注意点とは?種類や付与方法、金額、進呈するタイミングもご紹介!
アンケート調査に協力してくれた回答者に対して進呈する「謝礼」。調査目的や調査対象者に合わせて謝礼の内容や付与方法を適切に設定すれば、調査の質が向上し、回答者との関係が良好になるでしょう。
本記事では、回答者に対して謝礼を進呈する目的・理由や、謝礼を選定するうえで注意するべき点について詳しく解説します。謝礼の種類や、付与する方法、金額の目安(相場)、進呈するタイミングもご紹介するので、アンケート調査を実施する担当者は、ぜひ参考にしてください。
<この記事のポイント>
ポイント1 回答する労力への感謝の意やインセンティブとして「謝礼」を出そう
- ポイント2 金額や種類、付与方法によっては、回答者の属性が偏る可能性がある
- ポイント3 「電子ギフト」を謝礼にすれば、中立な調査結果を得やすくなる
目次[非表示]
- 1.アンケート謝礼の目的
- 1.1.1.回答にかかる労力への謝辞
- 1.2.2.回答を促すインセンティブ
- 2.アンケート謝礼の注意点
- 2.1.1.過度な金額(値打ち)の謝礼
- 2.2.2.物品やブランドによるバイアス
- 2.3.3.個人情報を適切に取り扱う
- 3.アンケート謝礼の種類
- 3.1.非金銭的なアンケート謝礼
- 3.2.金銭的なアンケート謝礼
- 4.謝礼の付与方法
- 4.1.景品表示法を遵守する
- 5.謝礼金額の相場
- 6.アンケート謝礼を進呈するタイミング
- 7.おすすめの謝礼
- 8.まとめ
- 9.おすすめの資料はこちら
アンケート謝礼の目的
回答者への「謝礼」は、アンケート調査を実施するうえで欠かせない要素であり、主に以下に示す目的・理由で進呈されています。
- 回答にかかる労力への謝辞
- 回答を促すインセンティブ
それぞれについて詳しく説明します。
1.回答にかかる労力への謝辞
アンケート調査の質問文を読んだり、回答欄に記入したり、選択肢に〇などを付けたりする作業には、ある程度の時間・労力を要します。
回答者が、調査主との関係が深い顧客(お得意様など)の場合、「回答するために時間と労力を費やしてくれたことに対する感謝の気持ち」を示すために謝礼を進呈するケースが多いでしょう。
一方で、公的な調査や、調査主と回答者の双方にとってメリットがあるアンケート調査(例えば、ゲーム会社がファンに対して「支持者が多いキャラクター・モンスター・武器などを次の作品で登場させる」と宣言したうえで実施するアンケート調査)の場合は、謝礼なしで実施されることがあります。
2.回答を促すインセンティブ
調査主と回答者の間に特別な関係がなく、多くのサンプルを得たい場合は、回答するモチベーションを湧き起こすために「インセンティブ」として謝礼を進呈することがあります。
設問の内容によって差はありますが、アンケートに回答するためには、一定の時間・労力がかかるため、インセンティブがない場合は「面倒だから、回答するのをやめておこう」と考える方が多くなるでしょう。
しかし、インセンティブとして謝礼を進呈すれば、「多少の時間がかかっても回答しよう」という気持ちになる方が増え、多くのサンプル回収につながることが期待できます。
アンケート謝礼の注意点
アンケート回答者に、過度な金額(値打ち)の謝礼を進呈すると、正しい調査結果を得られない可能性があります。また、謝礼として進呈するアイテムの種類(メーカー、ブランドなど)によっては、回答の中立性が損なわれる場合があります。
そのほか、謝礼の受け渡しに伴って氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを教えてもらう場合は、個人情報保護法に基づいて個人情報を適切に取り扱わなければいけません。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
1.過度な金額(値打ち)の謝礼
過度な金額(値打ち)の謝礼を進呈すると、「実際には興味・関心や知識がないにもかかわらず、謝礼目的でアンケートに回答する事例」が増えてしまいます。
「謝礼目的で回答した集団」の占める割合が大きくなると、幅広い層の好み・意見が反映されず、不正確な調査結果になる場合があるのでご注意ください。
2.物品やブランドによるバイアス
謝礼として進呈するアイテムに「特定のメーカーの商品」や「特定ブランドのポイント・商品券」などを選定すると、そのメーカーやブランドが好きな方や、アイテムをコレクションしている方が、回答者の多くを占めることになりかねません。
その結果、アンケート調査の回答が偏り、中立性を欠くことになる可能性があるので注意しましょう。
3.個人情報を適切に取り扱う
手渡し・郵送・メールなど、手法によって必要な情報は異なるものの、謝礼を進呈する際に氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどの個人情報を教えてもらうケースもあるでしょう。
個人情報を取り扱う(取得・保存する)場合は、個人情報保護法を遵守しなければいけません。具体的には、「取得した個人情報は、アンケート調査の謝礼を贈る目的でのみ利用する」などと利用目的を明確に定め、許諾を取り、その範囲内でのみ利用しましょう。また、情報漏洩が起こらないように、セキュリティ対策をしっかりと講じる必要があります。
なお、個人情報とは、氏名・生年月日・住所など、特定の個人の識別が可能な情報です。ユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別できる場合は、メールアドレス単体でも個人情報に該当するケースがあるのでご注意ください。
アンケート謝礼の種類
アンケート回答者に進呈する謝礼は、以下に示す2つの種類に大別されます。
- 非金銭的な謝礼
- 金銭的な謝礼
「どのような属性の集団から回答を得たいのか」を踏まえ、進呈する謝礼の種類を慎重に見極めましょう。以下、それぞれについて詳しく説明します。
非金銭的なアンケート謝礼
非金銭的な謝礼の具体例としては、「景品(オリジナルグッズ)」「イベントへの招待券」「商品・チケットの先行予約権」などが挙げられます。
例えば、自社の既存顧客で、すでに商品・サービス・ブランドのファンになっている層に回答してもらいたいのであれば、オリジナルグッズやイベントへの招待、先行予約権などを謝礼に選ぶのが効果的になるでしょう。
金銭的なアンケート謝礼
金銭的な謝礼の具体例としては、「商品券」「ポイント」「電子ギフト」などが挙げられます。
「オリジナルグッズは不要」「イベントに興味・関心がない」「先行予約してまで購入するつもりはない」という方も含めて、幅広い層から多くのサンプルを集めたいのであれば、さまざまな店舗で利用できる金券類(商品券やポイント、電子ギフトなど)のほうが謝礼として適しています。
謝礼の付与方法
謝礼の付与方法としては、全回答者に「一律」で進呈する方法や、回答者のなかから「抽選」で進呈対象者を決める方法のほか、公募や懸賞的な内容を含む場合は「審査」で謝礼(報奨)進呈者を決める方法もあります。
全員に一律で進呈するほうが、回答率が高くなることにご留意ください。付与方法によって、回答者の属性に多少の変化が生じる可能性があることも認識しておきましょう。また、「抽選」で進呈対象者を決める場合、当たる人数と金額のバランスを考慮する必要があります。キャンペーン的な要素を含んだアンケートであれば、A賞・B賞・C賞など謝礼にランクを付けることを検討してもよいでしょう。
景品表示法を遵守する
抽選で進呈対象者を決める場合は、「景品表示法」を遵守しなければいけません。下表に、景品表示法で定められている「取引価格と景品類の限度額の関係」をまとめました。
取引価格 |
1人の回答者に進呈する景品類の最高額 |
景品類の総額 |
5,000円未満 |
取引価格の20倍 |
売上予定総額の100分の2以下 |
5,000円以上 |
取引価格の10倍 |
例えば、入場料が1,000円のイベント会場(イベントでの売上総額は500万円を予定)において、来場者に対してアンケートを実施するケースを想定してみましょう。このケースでは、1,000円が「取引価格」となるため、1人の回答者に進呈する謝礼(景品類)の最高額は2万円に、謝礼(景品類)の総額は10万円以下に制限されます。
ただし、一般的に、アンケートが「顧客を誘引するための手段」や「商品・サービスの取引を行うもの」に該当しない場合、景品表示法は適用されません。アンケートの回答者のなかから抽選で謝礼進呈者を選ぶのであれば、念のため、消費者庁や弁護士などに相談し、景品表示法に違反していないことを確認しておくと良いでしょう。
謝礼金額の相場
以下に、アンケートの種類ごとに、「謝礼として進呈する金券類や物品」の相場を示します。あくまでも「目安」であり、自社の予算やターゲットに応じて、臨機応変に金額を変えましょう。
- Webアンケート:数十円~数百円
- 商品試用アンケート:0円~数千円
- 郵送アンケート:500円~数千円(BtoBの調査の場合、金額が高め)
- ストリートキャッチ(30分未満):500円分のギフトカードなど
- コンベンション会場などにおける対面アンケート:数十円~500円程度のグッズや商品券
商品試用アンケートでは、「試用してもらう商品そのもの」を謝礼にすることも可能です。自社製品の顧客などを対象とする「新製品の試用に関するアンケート」は数多く実施されており、しばしば「新製品や試供品そのものが謝礼の代わり」というケースがあります。ただし、長期テストなど、回答者に負担がかかる場合は、別途、謝礼を進呈するほうが良いでしょう。
ステルスマーケティング規制を踏まえて適切に対応しよう
アンケート回答者に対して、サンプル商品を試用した結果をブログやSNSなどで「広告」とわからない形で報告することを要求すると、「ステルスマーケティング規制」の対象(景品表示法違反)となる可能性があるのでご注意ください。
ステルスマーケティングとは、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為」です。アンケート回答者に対して、ブログ・SNSなどに感想を書き込むことを依頼することも「広告」に該当します。その場合、「広告」と明記するように回答者に要請しましょう。
広告であることが分からない状態でブログ・SNSに感想が書き込まれる、つまりステルスマーケティングを行ってしまうと、消費者庁から行政処分(消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」)を受ける可能性があります。
アンケート謝礼を進呈するタイミング
アンケート謝礼を進呈するタイミングとしては、「即時進呈」と「後日進呈」の2種類があります。以下、それぞれに関して詳しく説明します。
即時進呈
アンケートへの回答が完了したタイミングですぐに謝礼を進呈する場合、回答者のモチベーションが高まりやすくなり、回答率の向上を期待できます。ただし、「謝礼が欲しいだけ」の回答者が一定数含まれ、いい加減な回答が混入する可能性があります。
即時進呈の場合、何名が回答するのかが不明な状態で開始するため、謝礼の在庫を厳格に管理し、不足しないように注意しなければいけません。また、抽選で進呈者を選定するのであれば、スムーズに抽選を実施するためのツール・システムを導入する必要もあります。
後日進呈
アンケートへの回答直後ではなく、一定期間経過後に謝礼を進呈することも選択可能です。後日進呈の場合、用意するべき謝礼の数量が明確になるため、基本的に余剰在庫が発生しません。また、回答者が「手抜きをせず、謝礼を得るために時間をかけて誠実に回答しよう」という心理になりやすいため、より正確な回答結果を得られるメリットもあります。
ただし、「すぐに謝礼を受け取れないのであれば、回答しない」と考える人も一定数存在するため、回答率が低下する可能性は否定できません。
おすすめの謝礼
おすすめの謝礼は、ポイント交換ソリューションなどを開発・提供している専門業者の「電子ギフト」です。
「特定のメーカー・ブランドのアイテム」「特定の銘柄の金券類」を謝礼として進呈すると、回答者が、そのブランド・メーカー・銘柄のファンや利用者に偏ってしまうおそれがあります。
例えば、楽天ポイントを進呈する場合、回答者の多くを楽天ポイント利用者が占める可能性があり、dポイントを進呈する場合、dポイント利用者ばかりが回答することになりかねません。その結果、楽天ポイント(またはdポイント)の利用者の価値観・意見・好みが強く反映された調査になってしまうことにご留意ください。
しかし、多種多様な銘柄(ポイントや電子マネーなど)に交換できる電子ギフトなら幅広い層にメリットがあり、バイアスのないニュートラルなポジションの回答者を獲得しやすくなります。また、グッズや商品券とは異なり、郵送する必要がなく、メールなどの手段を用いて低コストで進呈できることも魅力です。
まとめ
アンケート調査を実施する際は、回答者の労力に対して「感謝の意」を示すために、あるいは回答を促す「インセンティブ」として、「謝礼」の進呈を検討しましょう。謝礼の内容を決める際は、金額・種類・付与方法・進呈するタイミングによっては、回答者の属性が偏る可能性があることにご留意ください。
おすすめの謝礼は、幅広い層にメリットがある「電子ギフト」です。例えば、ジー・プランの「マルチバリューコード」なら、ひとつの電子ギフトで、消費者が好きなポイント銘柄(dポイント、nanacoポイントなど)を自ら選んで取得できるので、アンケート回答者が特定の銘柄のポイント利用者だけに偏ることを防止できます。
初期費用・発行手数料0円から導入することが可能であり、メールやSNSのダイレクトメッセージなどで手軽に送付できるので、アンケートの謝礼として活用してみてはいかがでしょうか。
おすすめの資料はこちら
関連記事










