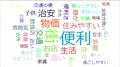ポイントマーケティングに取り組む6つのメリット|市場の現況や消費者が魅力に感じる理由も解説!
ポイントの歴史は古く、一説によると日本では100年以上前から存在していると言われています。
そして、今や多くの企業や店舗で導入されているポイントサービスですが、当たり前だからこそどこにメリットがあり、何を意識して企画すればいいのか迷われている方が珍しくないようです。
そこで、ここではポイントマーケティングを採用するメリットを解説するとともに、ポイントサービス市場の現状と消費者がどこに魅力を感じるのかその理由まで深堀りしていきましょう。
ポイントサービスを導入する上での大切な点にも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 ポイントサービスは顧客をファンに育成するきっかけとなるもの
✓ポイント2 顧客は”ためる”と”使う(割引)”の2重のお得感に魅力を感じている
✓ポイント3 還元率の高さだけを追求する安売り合戦には参入しない方がいい
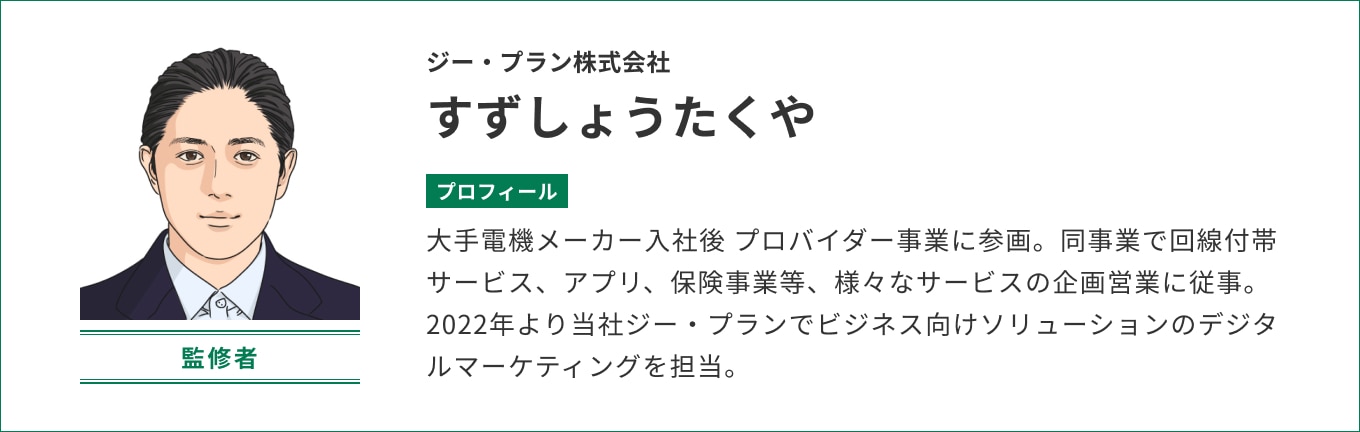
目次[非表示]
- 1.ポイントサービスとは?
- 1.1.ポイントサービス市場の現在
- 1.2.ポイントサービスの主な種類は2つ
- 1.3.1.共通ポイント
- 1.4.2.独自ポイント
- 2.ジー・プラン「ポイント・コンセント」なら独自ポイントを共有ポイントに簡単に直接交換する仕組みを導入できる!
- 3.消費者がポイントサービスに魅力を感じる2つの理由
- 4.ポイントマーケティングに取り組む6つのメリット
- 4.1.1.顧客の離脱を防げる
- 4.2.2.顧客とのタッチポイントを増やせる
- 4.3.3.顧客情報の収集につながる
- 4.4.4.他のマーケティング施策に活用できる
- 4.5.5.少額で高い効果を生むことができる
- 4.6.6.値引きよりも効果が高い
- 5.ポイントマーケティングに役立つ共通ポイントの特徴
- 6.ポイントマーケティングでよくある3つの質問
- 7.【まとめ】
- 8.おすすめの資料はこちら
ポイントサービスとは?
ポイントサービス(ポイントプログラム)とは、顧客にポイントを付与するサービスを活用したマーケティング施策のひとつです。このようなポイントサービスは昔から、それこそ日本では100年以上前からあるものなのですが、実は今、昔とは異なる目的で活用する事例が増えてきています。
ポイントサービス市場の現在
まずは今、日常的に利用されているポイントサービス、その起源についてご紹介しましょう。
これにはさまざまな説が存在しますが、ひとつの説としては、1916年に福岡県北九州市の久我呉服店が始めたとされています。その具体的な内容については定かではありませんが、もしこの説が真実であれば、日本におけるポイントサービスは100年以上の歴史があるということになります。
それから時が経ち、1989年に家電量販店ヨドバシカメラが、値引きの手間を省く目的で日本初のバーコード式ポイントカードを採用しました。このイノベーションが、現代にまで続くポイントカード制度の礎を築いたとされています。
このようにして生まれたポイントサービスはしだいに単なる値引きの一環から、集客・顧客の囲い込みの手段として変化してきました。そして、顧客の囲い込み(=リピーター化)からファンの創出(=企業やブランドへの長期的な支持者層の獲得)へと発展していきます。
前提として、ファンを創出するにはポイントサービスだけでなく、さまざまなサービスの活用が欠かせません。しかし、ファンになってもらうきっかけづくりとして考えると、古くから私たちの生活に深く浸透しており、ほかのサービスとの相性もいいポイントサービスが最適ではないでしょうか。
また、株式会社矢野経済研究所の発表によると、2021年度のポイントサービス国内市場規模はポイント発行額ベースで約2兆1千億円で、2026年度には約2兆5千億円にもなると予測されています(※)。つまり、すでに一般化しているポイントサービスではありますが、そこにはまだ成長の余地があると期待されているわけです。
注1.ポイント発行額ベース
注2.特定の企業・団体や企業グループが提供するサービスや商品の購入等に対して、発行されるポイントやマイレージ等を対象とし、市場規模は民間企業によるポイント発行額と行政主体の政策によるポイント発行額の合算値である。
※出典:(株)矢野経済研究所「ポイントサービス市場に関する調査(2022年)」(2022年8月22日発表)
ポイントサービスの主な種類は2つ
前述のように、ポイントサービス市場が今後も成長していくことが予想される要因のひとつには、独自ポイントの発行に加えて、ひとつの企業が共通ポイントを活用して複数のポイント制度を採用するマルチポイント制度の導入が一般化してきていることが挙げられます。
1.共通ポイント
dポイントやVポイント、Pontaポイント、楽天ポイントなどのように複数の企業や店舗が加盟し、自社のサービスに組み込めるポイントサービスです。共通ポイントはポイントを獲得した企業や店舗だけでなく、ほかの加盟店でもそのポイントを代金の支払いに利用できます。
2.独自ポイント
企業や店舗が自身のサービス内でのみの使用を想定したポイントサービスです。自社や店舗内でのみのサービスのため、独自ルールを自由に設定できるのが特徴です。例えば、リピーターへの還元率を高めてほかの顧客より優遇すれば、ファン化を促す効果が期待できます。
まずはすでにブランド力があり、大きな経済圏を築いている共通ポイントを活用して広く新規顧客を集客し、そこから顧客をファン化するべく、独自ポイントによる施策で強固な囲い込みをかけていく、という手法を採用する企業や店舗が増えてきているわけです。
ジー・プラン「ポイント・コンセント」なら独自ポイントを共有ポイントに簡単に直接交換する仕組みを導入できる!
ちなみに、ジー・プランが提供するポイント交換プラットフォーム「ポイント・コンセント」は約150社の共通ポイントと提携し、独自ポイントをdポイントやVポイント、Pontaポイント、楽天ポイントなどに交換する仕組みを導入することができます。
一般的にポイントサービス間のやり取りには複雑な手続きや、高額なシステム開発費がかかるものです。そのため、多くの企業や店舗では共通ポイントと独自ポイントは切り離して運用するしかないわけですが、「ポイント・コンセント」ならその心配はありません。
「ポイント・コンセント」は共通ポイントと独自ポイントの垣根を手軽に取り除くことができ、ひとつの大きなポイントサービスとしてポイントマーケティングに活かすことができます。
消費者がポイントサービスに魅力を感じる2つの理由
ポイントサービス市場が成長を続ける背景には、顧客がポイントに魅力を感じ、積極的に利用してくれていることも挙げられるでしょう。では、具体的に消費者はポイントサービスのどこに魅力を感じているのかですが、主に2つのことが考えられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
1位楽天ポイント、PayPayポイントも躍進【ポイントサービスに関する市場調査・2023年版】結果公開
1.「ためる」「割引」の2重のお得感を得られる
獲得したポイントは、各企業や店舗が定める有効期限内であればためることが可能です。そして、たまったポイントは商品の支払いに活用したり、特定のサービスに換えることもできます。つまり、ポイントサービスにはためる、そして使う(=実際に割引を受ける)という2つの側面が存在します。
ジー・プランが独自に実施したアンケート調査によると、ポイントを積極的にためているユーザーは7割を占め、ためる理由としては、「たまる場所が多いから」が最も高く、次いで「使える場所が多いから」でした。この結果から、ためると使う(=割引)、この2つのお得感が顧客の心を強く引きつけていることが見て取れます。
2.生活のなかでシナジーが発生する
すでにポイントサービスは私たちの生活のさまざまな場面と密接に関係しています。とくに企業や店舗に制限がない共通ポイントでは顕著で、ある店舗を利用したときに獲得したポイントを、関係性のまったくない別の店舗でも消費できる、というようにその影響は広範囲に及びます。
このようにポイントサービスは業界の壁をも簡単に越え、相互に価値を向上させる(シナジーを生み出す)というほかにはない特徴をもっているわけです。生活のさまざまな場面で自然と使え、それですこし豊かになれるのですから、顧客にとって魅力的にうつるのは当然のことでしょう。
ポイントマーケティングに取り組む6つのメリット
ポイントサービスは昔からあるものだけに、ただ何となく導入している企業や店舗も少なくないと思います。しかし、本来のポイントサービスというのはその本質を正しく理解し、取り入れることができれば、利益を何倍にも高めてくれる可能性を秘めたものです。
1.顧客の離脱を防げる
一般的に別のサービスに乗り換えると、これまで獲得してきたポイントは使えません。つまり、この所有ポイントが顧客の離脱を防ぐスイッチングコストとなるのです。また、長い間活動がない休眠顧客に対して、ポイントはサービスの存在を思い出してもらうきっかけにもなりえます。
2.顧客とのタッチポイントを増やせる
顧客にポイント残高をチェックするようメルマガやSMSなどで案内することで、顧客とのコミュニケーションの機会を創出できます。また、ポイント残高の確認という顧客にもメリットがあることを話題とすることで開封率が高まり、そこから新たな営業機会につながることも期待できます。
3.顧客情報の収集につながる
本来、すでにサービスを利用してくれている顧客に対して、追加で情報提供の協力を得るのは難しいものです。ただ、そういうときでも、ポイントのプレゼントを掲げることで協力を得やすくなることがあります。また、新規の顧客登録でも、ポイントのプレゼントは有効な手段となるでしょう。
4.他のマーケティング施策に活用できる
イベントやキャンペーンへの参加を促す手法としても、ポイントのプレゼントは効果が期待できます。ポイントは対面で直接配ることもできますし、URLやQRコードなどを活用すればオンラインでも簡単に配れることから、アイデアしだいでさまざまなマーケティングに活用が可能です。
5.少額で高い効果を生むことができる
周辺サービスとの連携は顧客満足度を高めるうえで効果的な施策ですが、組織の壁やデータベースの統合の難しさなどさまざまな障壁が存在します。一方、ポイントサービスは独自ポイントでも少なくとも自社のサービスとの連携が容易ですし、ジー・プランの「ポイント・コンセント」のようなポイント交換プラットフォームを活用すれば共通ポイントとの連携も少額で実践できます。
6.値引きよりも効果が高い
単純な値引きよりも、ポイントを付与する方が集客効果は高いとされています。これは「メンタルアカウンティング理論」と呼ばれるもので、ポイントの方がためる喜びが付加価値として感じられるからと考えられます。ただし、集客効果が高いのは付与率が1〜15%程度の場合です。ポイントに比べて、割引率があまりにも高い場合には、割引の方が有利になることもあります。
ポイントマーケティングに役立つ共通ポイントの特徴
大きな経済圏を築いている共通ポイントは新規顧客の集客をはじめ、ポイントマーケティングを成功に導くうえでの重要なツールです。ただ、共通ポイントは数が多いため、どれを選べばいいのか迷ってしまう方が少なくありません。そこで、主な共通ポイントの特徴をまとめてみました。
dポイント
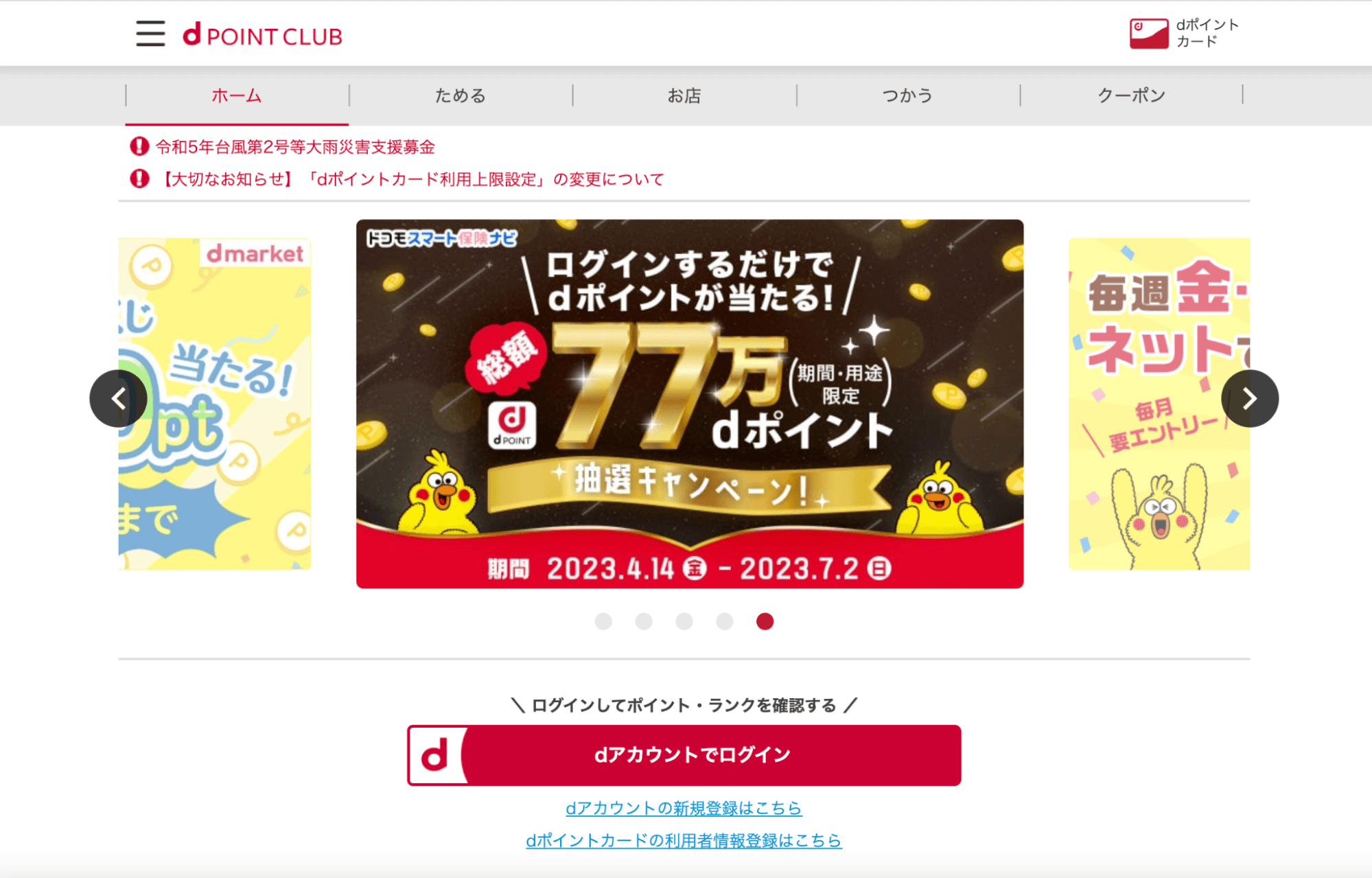
https://dpoint.docomo.ne.jp/index.html
会員数:dポイントクラブ会員数約8,000万(2021年1月末時点)
dポイントとは、NTTドコモが提供しているポイントサービスです。しかし、ドコモ関連のサービスだけでなく、提携している多数の企業でも利用できます。また、ドコモの契約者であればもちろん、非契約者でもdアカウントを取得すれば利用することが可能です。
さらに、dポイントカードのほかに、iDやd払いなどキャッシュレス決済にも対応しています。2020年6月にはフリーマーケットアプリのメルカリと連携し、同年9月にd払いとメルペイが同じQRコードで利用できるようになるなど、年々顧客側の利便性が向上していて、共通ポイントとして導入すれば集客窓口としての高い機能が期待できるポイントサービスです。
Tポイント
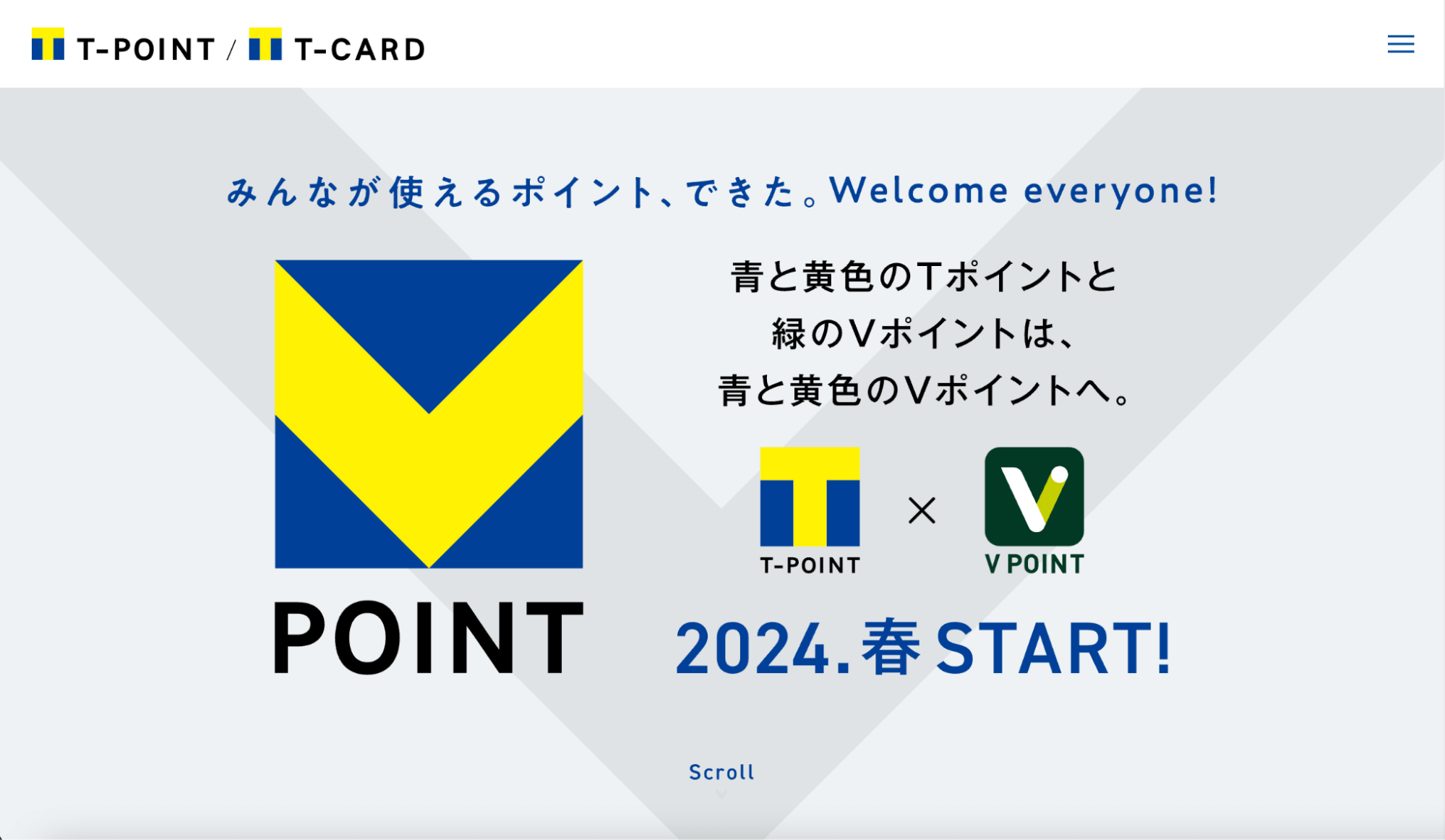
会員数:約7,000万人(2022年5月末時点)
Tポイントはカルチュア・コンビニエンス・クラブグループが提供するポイントサービスです。日本人の2人に1人(約55.6%)がTカードを保有し、5割以上のユーザーが月に1回以上利用していることから、日本でもっともアクティブユーザー数の多いポイントサービスのひとつと言えます。
また、登録時に性別、生年月日、郵便番号単位までの基本情報を収集し、1人につき1つのIDのユニークユーザーとして管理しているのも特徴です。そこから「誰が」「いつ」「どこで」「総額いくらで」「何を」「どのくらい」「それぞれいくらで」という粒度の細かい決済データを収集することで、精度の高いポイントマーケティングを可能としています。
Pontaポイント

https://point.recruit.co.jp/point/
会員数:1億1,305万人(2023年5月末時点)
Pontaとはロイヤリティ マーケティングが運営するポイントサービスです。2020年5月21日にKDDIのポイントサービスau Walletポイントを統合、au PAYという強力な決済機能を得たことで、現在のようなユーザー数1億人を超える巨大な経済圏ができあがりました。
また、2022年5月時点の提携店舗数は26万店であったのが、1年後の2023年5月末時点には142の提携社に190のブランド、28万もの提携店舗と今なお急速にシェアを拡大しています。さらに、共通ポイントでありながら加盟店の裁量の余地をあえて大きく残しているのも特徴的で、企業や店舗が自社の商品やサービスと組み合わせやすいのが魅力のひとつです。
楽天ポイント
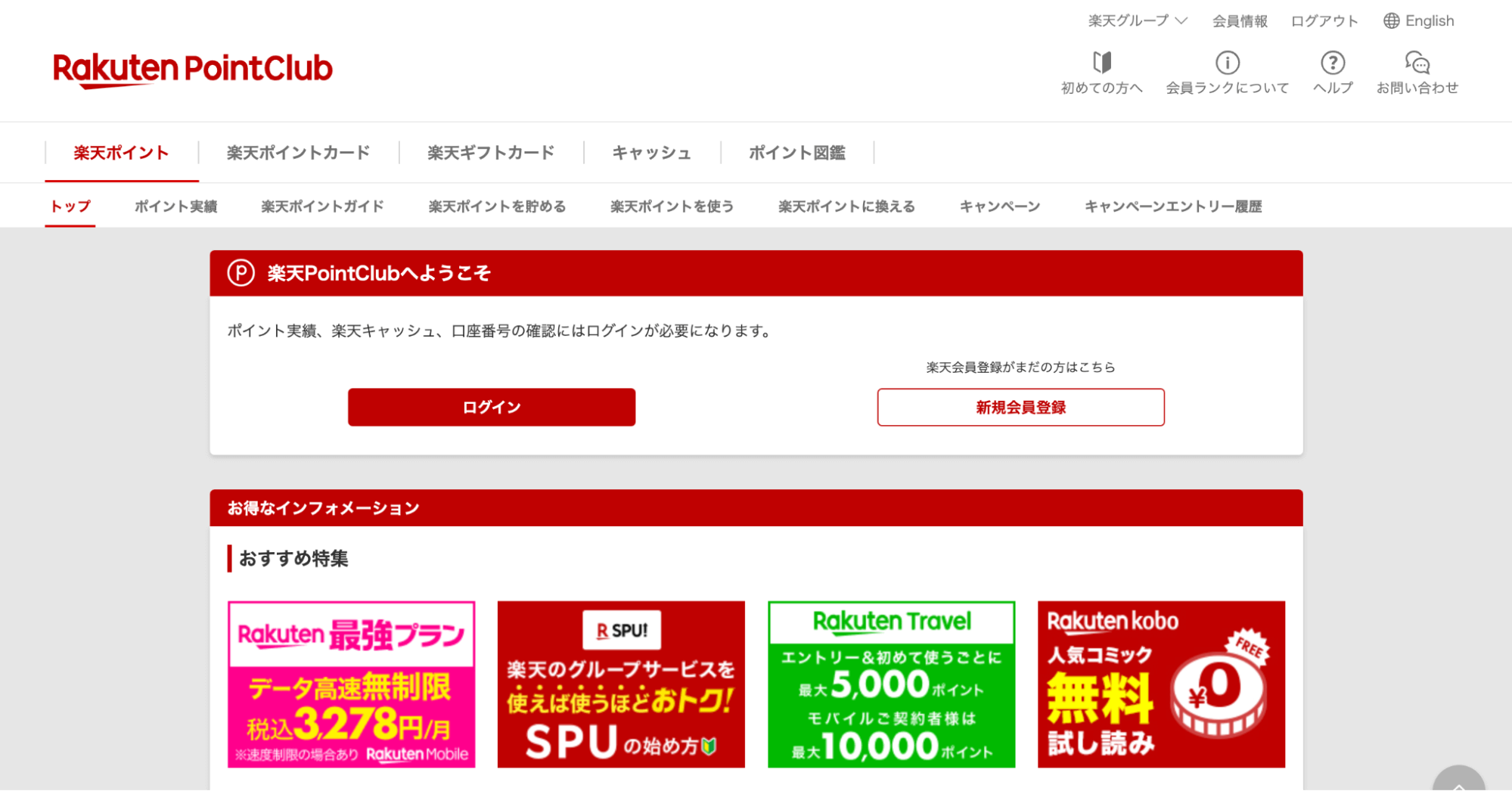
会員数:1億人以上(2022年12月時点)
楽天ポイントとは楽天グループの提供するポイントサービスです。2022年7月時点で通算10万ポイント以上を獲得しているヘビーユーザーが750万人を超え、累計発行ポイント数が3兆を突破。ユーザーアンケートでは「一番ポイ活したいポイント」として高く評価されています。
このように多くのユーザーを魅了するのは、楽天グループがインターネットサービスやクレジットカード、金融サービス、携帯電話事業、プロスポーツなど多岐にわたる分野で70以上のサービスを展開し、楽天ユーザーを中心とした独自の経済圏を築いているからでしょう。とくに日本最大級のECサイト楽天市場が利用できるのは、共通ポイントとして導入する際の強みとなります。
ポイントマーケティングでよくある3つの質問
今や多くの企業、店舗が何らかのポイントサービスを活用しているだけに、単に導入すれば効果が得られるというものではなくなっています。そこで最後に、企業の担当者や店舗の代表者がポイントマーケティングを実施する際に悩みやすい点、疑問に感じることについて解消しましょう。
質問1.ポイントサービスで重要な還元率以外の要素とは?
最近のポイントマーケティングではバーコード決済(○○Pay)と連携するなどして、高い還元率を謳い文句としているものを多く見かけます。中には、30%以上の驚くほどの還元率(実質的な割引)のものもあり、確かに顧客目線で見ると魅力的で、利用する価値があります。
ただ、将来を見据えるのなら、この還元率の競争に参入するのはおすすめしません。安売り合戦と同じで、最終的には資本力の弱い企業、店舗にしわよせがいくと考えられるからです。むしろ世間が還元率に注目している今であれば、還元や値引きに頼らない差別化が強みとなるでしょう。
例えば、アパレルや生活雑貨を販売するセレクトショップCOSUCOJIではためたポイントで「コスコジの2時間店長」になれる独創的な企画を実施していました。また、クレジットカード関連のクレディセゾンではためたポイントを運用し、疑似的に投資体験ができる「永久不滅ポイント運用サービス」を展開しています。
このようにポイントと、その企業や店舗だから体験できる何かと結びつけることで、お得感にとどまらない価値を提供でき、顧客を新たなファンに育てるきっかけとなるわけです。
質問2.ポイントマーケティングでタッチポイントが重視される理由とは?
当たり前のことですが、顧客に企業や店舗、そして商品やサービスについて知ってもらわないことには購入にはつながりません。そして、顧客からの認知を得るためには、前提としていかに顧客とのタッチポイント(接点)を増やすのかがカギとなります。
では、どうすれば顧客とのタッチポイントを増やせるのかですが、広告やECサイト、店頭販売などいくつか方法があるなかで、安いコストで効果を見込めるのがポイントサービスなのです。
これまでご説明してきた通り、ポイントサービスでもすでに多くのユーザーを抱える共通ポイントは新規顧客の集客窓口として優秀です。また、ポイントサービスへの登録で顧客情報を収集できたら、次からは企業や店舗側から顧客に向けて情報を発信することもできます。
また、ポイントサービスは顧客の間でも当たり前のものとして浸透していることから、独自サービスを展開しても比較的受け入れられやすいという特徴もあり、まだ資本力の小さな企業や店舗でも手軽に導入できるという点でも、ポイントマーケティングは重要な存在なのです。
質問3.タッチポイントを検討する際の流れは?
- ブランドイメージを明確にする
ブランドイメージが明確でないと、強みがわからない - 顧客のペルソナについて深く分析する
顧客について知らないと、ニーズがわからない - 顧客と接する流れを重視する
ストーリーがあるからこそ、タスクの優先度が明確になる - 複数の方向からアプローチをかける
媒体を限定していると、失敗のリスクが高くなる - 結果を分析して次の施策に活かす
改善を繰り返すことで、成功への道筋が見えてくる
先ほど、ポイントサービスはほかとの差別化が重要とご説明しましたが、独創性のあるサービスを展開したからといって必ずしも成功できるわけではありません。むしろ、これまでにない独創的なサービスだからこそ、顧客に受け入れられないことの方が多いものです。
1度目の実施が思うような結果にならなかったからといって諦めるのではなく、得られたデータを財産として次の施策に活かすことが大切です。そして、導入コストがあまりかからないポイントサービスは、こうした新たなことに挑戦する際のハードルが低い手法であると言えます。
【まとめ】
本記事では、ポイントマーケティングを採用するメリットやポイントサービス市場の現状、顧客がポイントのどこに魅力を感じているのかを分析してきました。ポイントは顧客とのタッチポイントを手軽に増やせる手段として、企業や店舗の多くが積極的に導入しています。
ただ、その手法が還元率をウリとする安売り合戦のようなものになるのはおすすめしません。当たり前になっているものだからこそ、周りの企業や店舗がやっていない、自社だからこそ実現できる何かとポイントを組み合わせることができれば、顧客をファンに育成する強力なツールとなるでしょう。ポイントサービスを導入する際には、ぜひ自社の強みが何かを考えてみてください。
おすすめの資料はこちら
関連記事