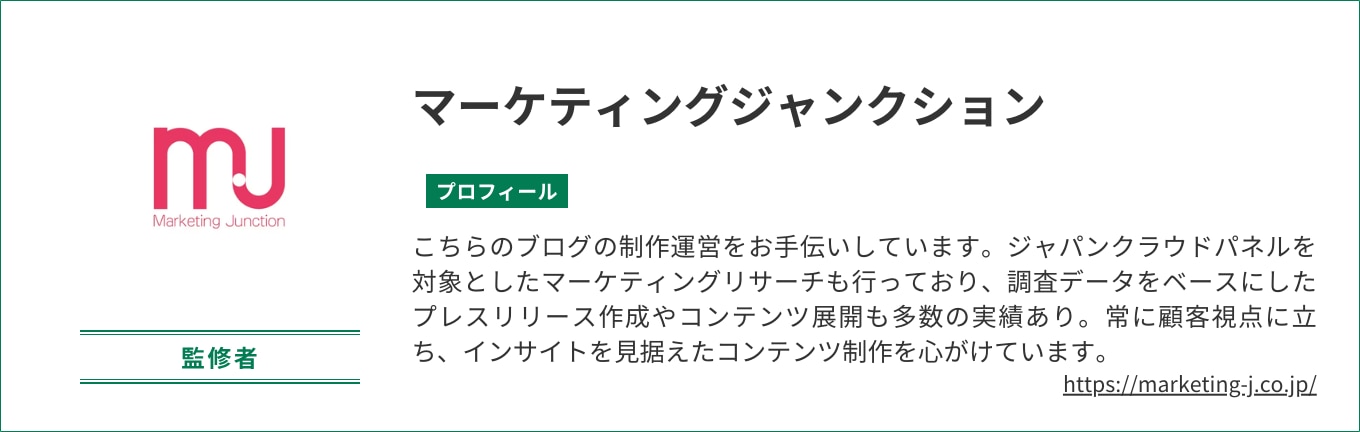ホテル・宿泊業ではリピーター獲得戦略が重要!ポイントサービスの活用法とは?
ホテル・宿泊業で売上増を実現するためには、リピーター獲得戦略を練る必要があります。リピーターを獲得するための方法のひとつに「ポイントサービス」がありますが、ほかの業種・業態と異なり、宿泊業では「顧客の利用間隔が長い(利用頻度が少ない)」という特殊事情があることを踏まえて施策を講じなければなりません。
本記事では、ホテル・旅館など、宿泊業を営む企業の経営者やポイント施策担当者に向けて、ポイントサービスを活用したリピーター獲得戦略について徹底解説します。利用間隔が長いという事情から、共通ポイントのほうが喜ばれる傾向があるものの、独自ポイントにもさまざまなメリットがあるので、双方のメリットを活かした施策を立案しましょう。
この記事のポイント
ポイント1 宿泊業のリピーター獲得戦略として、「ポイントサービス」の活用を
-
ポイント2 利用間隔が長いため、「共通ポイント」のほうが喜ばれる傾向がある
-
ポイント3 独自ポイントと共通ポイントの双方のメリットを活かすことが大切!
目次[非表示]
ホテル・宿泊業において重要なのは「リピーター獲得戦略」
少子高齢化により、毎年、日本の人口が減少する時代になりました。そのため、日本国内において、新規に顧客を集めることが困難になりつつあります。今後も安定的に売上を拡大し続けるためには、「訪日外国人(インバウンド需要)への対応」に加えて、「日本国内の既存顧客にリピーターになってもらうこと」も意識しなければなりません。
たとえば、北海道の観光地「ニセコ」であれば、外国人が大量に訪れるため、外国人に特化した施策(「飲食店のメニューを外国語表記にする」「英語・中国語などでコミュニケーションする」など)に取り組むことで売上が拡大するかもしれませんが、外国人があまり訪問しない地域で営業しているホテル・宿泊業の場合、インバウンド需要に特化するのではなく、日本在住者向けの施策も打ち出してリピーターを獲得するべきです。
リピーターを獲得するための施策としては、再訪した顧客が飽きないように、定期的にリフォーム・模様替えを実施することが挙げられます。これは、「消費から体験へ」という消費者ニーズの変化を踏まえた施策です。前回訪問時と同じ設備の状態になっていると「サプライズ」が感じられず、顧客に飽きられてしまうかもしれません。
リピーター獲得戦略という意味では、「ポイントサービス」を実施することも、有効な手段の一つです。自社の独自ポイントにも共通ポイントにも、それぞれメリットがあるので、目的や戦略に応じて適切に組み合わせましょう。次の章以降で詳しく説明します。
「独自ポイント」をリピーター獲得手段として活用するメリット
以下、自社・自施設の「独自ポイント」をリピーター獲得手段として活用するメリットを3つご紹介します。
ブランドロイヤルティの強化に役立つ
独自ポイントは、顧客に対して、特定のホテルに繰り返し訪れるインセンティブを提供します。共通ポイントの場合、幅広い店舗で利用できるため、受け取ったポイントを自社の宿泊施設で使用してくれるとは限りません。
しかし、独自ポイントなら、使い道を「自社の宿泊料金への充当」や「自社ブランドのグッズとの交換」に限定することが可能で、顧客に宿泊施設に再訪してもらったり、自社ブランドに親しんでもらったりすることに繋がります。
たとえば、「アパホテル」では、「アパポイント」という名称の独自ポイントが貯まるポイントサービスを実施しています。宿泊実績に応じて会員ステイタスが上昇し、ポイント還元率も高くなっていく仕組みであり、リピーター獲得を意識した施策といえるでしょう。
貯まったアパポイントは、オリジナルアイテム(「アパオリジナルフェイスタオル」や「アパ社長カレー」)と交換したり、宿泊料金として使用したり、現金と交換したりすることが可能です。
顧客に関する詳細なデータを収集できる
顧客の消費行動・好みに関する詳細なデータを収集できることも、独自ポイントを展開するメリットです。共通ポイントの場合、ポイント提供企業によって取捨選択された情報しか入手できません。しかし、自社の独自ポイントなら、「何月何日に、どの顧客が、どこで、どのような行動をしたのか」という詳細なデータを自由自在に取得できます。
それらの情報に基づいて、各顧客の興味・関心・嗜好に沿った施策(たとえば、「ポイントをオリジナルタオルに交換する回数が多い顧客に対して、感謝の気持ちとして、次回宿泊時にオリジナルタオルを記念品として贈呈する」など)を講じれば、顧客満足度が高まり、リピート率の向上につながるでしょう。
還元率などを自由に設定できる
共通ポイントの場合、還元率や景品の内容(ポイントの使い道)を自社で自由に決めることができません。しかし、自社の独自ポイントであれば、ポイント還元率や景品の内容などを自由に設定できます。
たとえば、「誕生月にポイント還元率をアップさせる」「一定期間内に一定回数以上宿泊した顧客に対して、特別な景品・体験を贈呈する」「年間利用金額に応じて会員ランクが上昇する仕組みを導入する」といった施策を講じれば、リピートしてもらいやすくなるでしょう。
「共通ポイント」をリピーター獲得手段として活用するメリット
ここからは、「共通ポイント」をリピーター獲得手段として活用するメリットを3つご紹介します。
顧客層の拡大に役立つ
独自ポイントは、基本的に、自社が運営する宿泊施設(および、提携先企業が運営する店舗など)でしか利用できません。しかし、共通ポイントは、幅広い店舗(コンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパー、家電量販店など)で利用することが可能です。
そのため、共通ポイントを提供すれば、「あまり旅行する機会がない(ホテルに宿泊する頻度が少ない)から、宿泊施設でしか利用できないポイントを貯めたいと感じないけれども、ほかの業界・業種の店舗でも利用できる共通ポイントであれば貯めたい」という消費者を、自社の顧客として取り込みやすくなるでしょう。
ポイント付与の観点から新規顧客獲得のチャンスが広がるだけではなく、「共通ポイントで宿泊料金を支払えるから、今回もこのホテルで泊まろう」という顧客も存在するため、リピーターの獲得にも有効です。
ポイントサービスの運用コストを削減できる
独自ポイントの場合、会員情報やポイント数などを管理するためのシステムを用意し、システム運用を担当するスタッフも育成しなければなりません。社内にITに詳しい人材がいない場合は、「ITの専門知識・スキルを有する人材を新規に採用する」「外部業者に委託する」といった対応が必要になります。
しかし、共通ポイントを導入すれば、共通ポイントを提供している業者のシステムを利用してポイント施策を展開できるため、自社の独自ポイントを提供する場合に比べて、システムの開発・運用に関するコストの削減につながるでしょう。そして、自社のスタッフを、宿泊業のコア業務(接客、施設の維持管理など)に専念させることが可能になります。
共通ポイントのプロモーションによるマーケティング効果
共通ポイントを提供している業者(グループ企業・提携企業も含む)のプロモーション・広告などによって、自社の宿泊施設の認知度が向上することも、共通ポイントの魅力です。
規模の大きいものとして、「楽天トラベル」では、さまざまな宿泊施設で利用できる「割引クーポン」を発行しているほか、宿泊料金の30%~40%相当の楽天ポイントを還元する「楽天スーパーDEAL」という施策も実施しています。ページ内に対象となる宿泊施設やプランなどの情報も掲載されているので、楽天ポイントを貯めている消費者に対しての訴求効果を期待できます。
そのほか、共通ポイントに対応している旅行サイトのなかには、「後日、ポイントを付与する」という仕組み(ポイントの後付け)ではなく、「付与予定のポイントを、予約時に利用できる」という仕組みが採用されているケースがあることも認識しておきましょう。
たとえば、PayPayポイントを獲得できる旅行予約サイト「Yahoo!トラベル」や「一休.com」では、「ポイントの後付け」のほかに、「獲得予定のポイントを予約時に使用する」という選択も可能になっています(デフォルトでは即時利用した場合の料金が表示)。
「予約時におけるお得感」を消費者に対してアピールできるという点も、共通ポイントの魅力といえるでしょう。
宿泊業における「ポイントの意識のされ方」
宿泊業では、他業界・他業種とは異なり、独特な「ポイントの意識のされ方」をすることにご留意ください。
まず、宿泊前にポイントサービスに関して意識する顧客が他業種に比べて少ないことが挙げられます。食品や日用品、家電製品などを購入する場合は、「なるべく還元率が高い店舗を選んで、少しでもお得に購入しよう」と考えて事前に入念にリサーチを行う消費者であっても、旅行という非日常的なイベントでは、価格(ポイント還元率)よりも「体験の質」を重視するケースが多いでしょう。
ポイントが付与されるタイミングが、「予約したタイミング」ではなく、「チェックイン後」や「チェックアウト時」「チェックアウト日から一定期間経過後」に実施される場合が多いことも、「ポイント還元率が多いから、このホテルを選ぼう」と事前に考える顧客が少なくなっている要因といえるでしょう(上述したように、「獲得予定のポイント」を予約時に利用できる旅行予約サイトも存在)。
そのほか、「次回、いつホテルを利用するか」が不確定であることも、宿泊業における「ポイントの意識のされ方」という点で重要な要素です。ホテルの利用頻度は、日常的に利用される業種・業態(コンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなど)に比べて低い傾向が見受けられます。
多くの顧客は、宿泊施設の独自ポイントを付与されても、付与された時点では「いつ利用できるようになるのか(いつホテル・旅館を再訪するのか)」が不明確であるため、日常的にコンビニエンスストアなどで利用可能な共通ポイントの付与のほうが魅力を感じる傾向があることを認識しておきましょう。
利用頻度が低いからこそ、共通ポイントの価値が高まる
上述したように、宿泊業においては、顧客の来訪頻度が低い(前回宿泊してから次に宿泊するまでに一定の時間を要する)傾向があります。
もちろん、個人ごとにホテルに宿泊する頻度は異なるため、「年に1~2回しかホテルに宿泊しない」という消費者もいれば、「月に1回以上はホテルに宿泊する」という消費者もいるかもしれません。しかし、コンビニエンスストアやスーパーなどとは異なり、「毎日宿泊する」あるいは「週に3~4回程度宿泊する」という消費者はほどんどいないでしょう。
たとえば、独立行政法人中小企業基盤整備機構が2017年に実施した調査によると、ビジネスホテルの利用頻度は、「年に1回以下」が58%、「半年に1回」が22%、「2~3ヶ月に1回」が11%となっています。
この調査結果に該当するような、利用頻度が低い顧客の立場では、「いつ利用できるようになるのかがわからない独自ポイント」よりも、「コンビニエンストアやドラッグストア、スーパーなど、多様なシーンでいつでも利用可能な共通ポイント」のほうが魅力的です。
利便性の高い共通ポイントを付与すれば、結果的に顧客と宿泊施設のエンゲージメント(信頼関係・親密さ)が向上し、リピート率が上昇する可能性があります。また、共通ポイントを貯めている消費者を、自社の顧客として取り込むチャンスが生まれ、新規顧客獲得にも役立つことを覚えておきましょう。
ホテル・宿泊業が取るべき戦略的アプローチ
ホテル・宿泊業が取るべき戦略的アプローチとしては、「マーケティングやプロモーションにおいて、共通ポイントの利点を強調すること」が挙げられます。そうすることで、次回の利用が不確定な顧客にも、魅力を感じてもらえるようになるでしょう。
また、「後付けの(宿泊後、一定期間が経過してからポイントが付与される)特性」を認識し、適切に対応することも大切です。具体的には、チェックアウト時などに「後日、ポイントが付与されること」を明示的にアナウンスすることで、顧客のポイントサービスに対する意識を高めることができます。
独自ポイントと併用することも選択肢として検討を
宿泊業においては「共通ポイント」のほうが顧客にとって魅力があることを述べてきましたが、上述したように「独自ポイント」にもメリットがあるので、両者を併用することもご検討ください。
独自ポイントと共通ポイントを上手に組み合わせれば、顧客の選択肢が広がり、より多くの顧客ニーズに対応できます。それぞれの利点を取り入れ、柔軟なポイント施策を立案しましょう。
共通ポイント(dポイント、楽天ポイントなど)のほかに、「Aカードホテルネットワーク」に加盟するという選択肢もあります。Aカードホテルネットワークとは、日本全国で470施設以上のホテルなどが加盟するポイントサービスです。宿泊業界に特化したポイントサービスなので、旅行好きな消費者を自社の顧客として取り込みやすくなるでしょう。
まとめ
ホテル・宿泊業においては、多くの場合、「宿泊後にポイントが付与される」という性質があります。この「ポイントが後付けされる」という特性と、「次回の利用がいつになるのかが不確定な顧客が多い」という状況を勘案すると、共通ポイントを提供するほうが有利です。ただし、独自ポイントにもメリットがあるので、両者を上手に組み合わせることが成功への鍵となります。
ホテルや旅館などの経営者や、宿泊業界においてリピーターを獲得するための戦略立案に携わっている方は、「ポイントが後付けされる特性」と「共通ポイントの重要性」を認識しておきましょう。本記事でご紹介した内容が、戦略策定の一助になれば幸いです。
なお、独自ポイントを提供するのであれば、「共通ポイントなどへ交換できる仕組み」も導入することも選択肢のひとつとしてご検討ください。たとえば、ジー・プランのポイント交換ソリューション「ポイント・コンセント」なら、独自ポイントを共通ポイントなどに交換できるだけでなく、マーケティング戦略に合わせて、地域独自のポイントへの交換なども自由にカスタマイズでき、顧客満足度の向上につながるでしょう。
おすすめの資料はこちら
関連記事