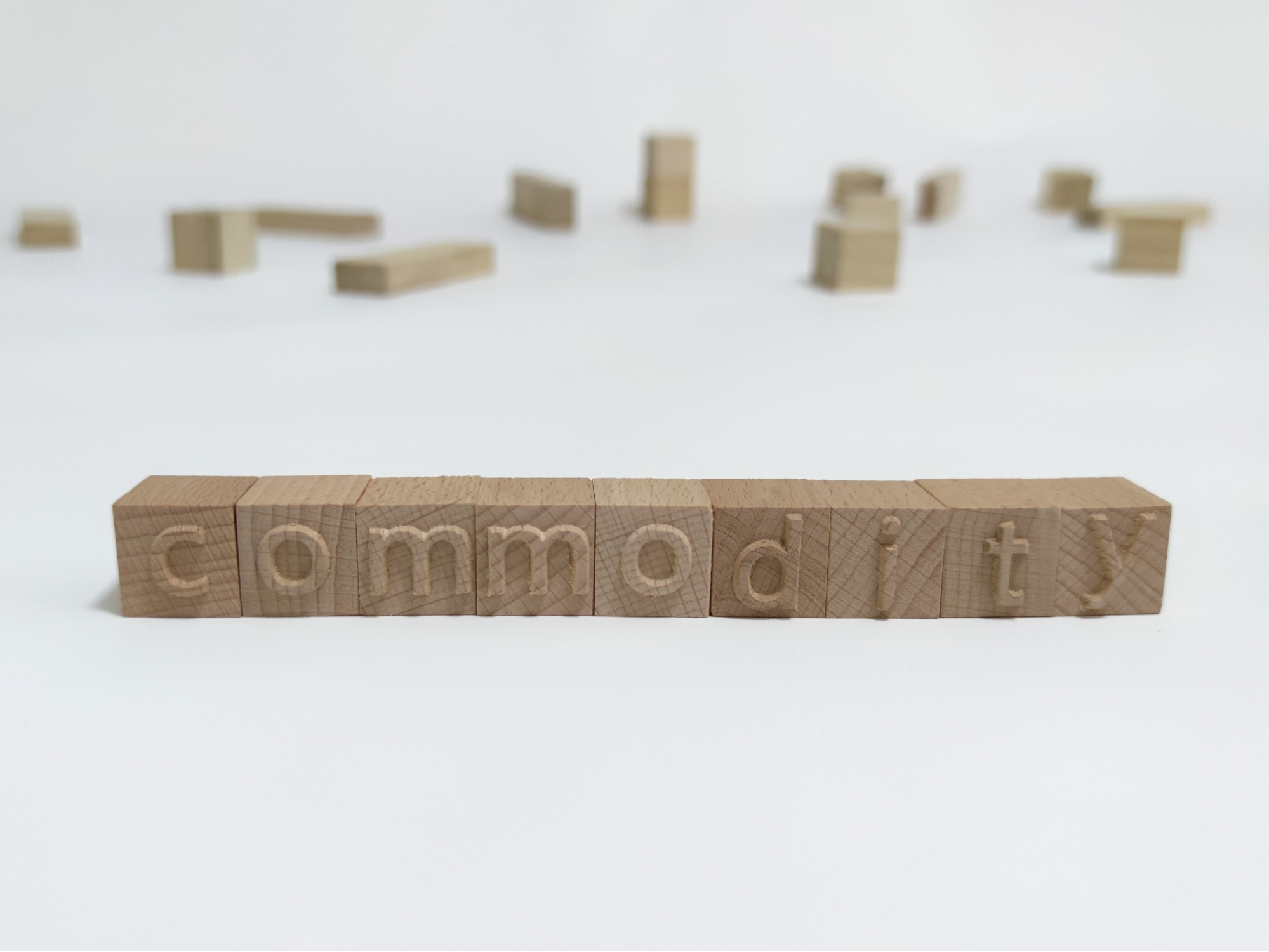
ポイントサービスのコモディティ化が進行中!他社との差別化を図る方法とは?
スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストア、行政、学校など、社会のさまざまな分野で「ポイントサービス」が実施される時代になりました。「ポイントサービスはコモディティ化しつつある」とも言える状況であり、単に導入するだけでは充分に効果が得られない可能性があります。
これから重要になるのは、「どのようにポイントサービスの内容を他社と差別化するか」という点です。ポイント交換ソリューションを導入し、自社のポイントを他社のポイントと交換できる仕組みを提供することも選択肢のひとつでしょう。
<この記事のポイント>
ポイント1 ポイントサービスは珍しいものではなくなり、コモディティ化が進行中
- ポイント2 これからは「どのようにして他社と差別化するか」を考える必要がある
- ポイント3 ポイント交換ソリューションを導入することも、差別化戦略として有効
目次[非表示]
近年、ポイントサービスのコモディティ化が進行している
まず「コモディティ化」の意味を説明したうえで、ポイントサービスが置かれている状況をご紹介します。
コモディティ化とは?
コモディティ化(Commoditization)とは、「当初はユーザーの間で価値が高い製品・サービスと認識されていたものが、さまざまな企業が参入した結果、機能や品質などに差がなくなること」を指すビジネス用語です。
「ポイントサービス」というサービスも、以前は現時点に比べると実施する企業・店舗が少なかったため、「ポイントサービスを実施している」というだけでも価値があり、消費者を引き寄せる効果が充分にありました。
しかし、現在ではスーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアといった商業施設はもちろんのこと、公共施設(学校など)においてもポイントサービスが実施されており、日常生活のなかでありふれた存在になっています。
そのため、これからは、単に「ポイントサービスを実施している」というだけでは特別な価値を感じてもらいにくいことを踏まえて施策を展開しなければなりません。
ポイントサービスが置かれている状況
日本におけるポイントサービスの始まりは、1989年の「ヨドバシカメラ」の施策にまで遡るとされています。それから30年以上が経過した2023年現在においては、無数の企業・店舗・公共施設がポイントサービスを導入しており、総数の把握は困難です。
以前は小売業が中心でしたが、製造業などでもポイントサービスが展開される時代が到来しました。例えば、パナソニックでは、会員向けサイト「CLUB Panasonic」において、さまざまなアクションに応じて「CLUB Panasonicコイン」が貯まる仕組みを提供しています。
今や消費者は、「どの店舗で商品を購入しても、何らかのポイントを獲得できる状態」に置かれていると言っても過言ではないでしょう。
単にポイントサービスを導入するだけでは、充分に効果を得られない
あらゆる企業・店舗がポイントサービスを実施している昨今、単にポイントサービスを導入するだけでは、消費者にとって魅力的な施策にはなりません。
例えば、店舗Aでも店舗Bでも「1,000円(税込み)につき1ポイント(=1円相当の価値)を付与する」という施策を実施している場合、ポイントサービスを実施していること自体は、利用する店舗を選択するための決め手にならないでしょう。
消費者のリテラシーは向上しており、「どのような条件でポイントを獲得できるのか」「有効期限がどのくらいなのか」など、ポイントサービスの内容を精査したうえで「自分に適したポイント施策を展開する企業・店舗」を選択する時代になっています。
これからは、ポイントサービスの内容の差別化が必須
これからの時代、消費者に自社・自店舗を選んでもらうためには、ポイントサービスの内容を差別化する(他社と異なる付加価値を提供する)ことが不可欠です。以下に、差別化するための施策の例を示します。
- ランク制度(ステージ制度)を導入する
- 有効期限を設定しない
- 誕生月に還元率をアップする
- 他社のポイントとの交換を可能にする
ランク制度(ステージ制度)とは、顧客の月間・年間購入金額や各種アクション(Webサイトへや実店舗への訪問回数、資料請求の回数など)に応じて、会員ランク(会員ステージ)が上昇し、さまざまな特典(限定グッズのプレゼント、チケットを先行予約する権利の付与など)を受けることが可能になる仕組みで、自社・自店舗の熱心なファン(ロイヤルティの高い優良顧客)の育成に役立ちます。
また、「大量にポイントを貯めていたのに、有効期限が到来して無効になっていた」という経験をした顧客は、他社・他店舗に流出してしまうかもしれません。そこで、ポイントに有効期限を設定しないことも、差別化戦略のひとつとして検討しましょう。
顧客の誕生月に合わせて還元率をアップすることも有効です。「普段は節約しているけれども、誕生日くらいは自分へのご褒美として贅沢をしよう」と考えやすくなります。
そのほか、「他社のポイントと交換することが可能な仕組み」を提供することも、選択肢のひとつです。
ポイント交換の展開により、「普段は別の店舗で別のポイントを貯めているけれども、ポイントの交換が可能なら、この店舗も利用してみよう」という顧客を自店舗に取り込めるようになります。また、「他店舗のポイントが貯まっていたけれども、その店舗には魅力的な商品・サービスがないため、ポイントを使わないまま放置していた」という顧客に、貯まっているポイントを自店舗で使ってもらうことも可能になるでしょう。
ポイント交換ソリューションの導入も選択肢のひとつ
「自社・自店舗の独自ポイントと他社のポイントを交換する仕組み」を自力で用意する(1からスクラッチ開発する)ことも可能ですが、費用や時間がかかります。そのため、法人向けの「ポイント交換ソリューション」を導入することも選択肢のひとつとして検討しましょう。
ポイント交換ソリューションを導入すれば、システムをスクラッチ開発した場合と比べて低コスト・短期間で、顧客に対して「自社ポイントと他社ポイントを交換する仕組み」を提供できます。
【まとめ】
社会のさまざまな分野で「ポイントサービス」が実施される時代になりました。ポイントサービスのコモディティ化が進行している昨今、単に導入するだけでは充分に効果が得られないでしょう。これからの時代は、「ポイントサービスの内容の差別化」が重要になります。
「自社ポイントと他社ポイントの交換を可能にする仕組み」を提供することは、差別化戦略として有効です。ただし、システムをスクラッチ開発するのは費用や時間がかかるので、「ポイント交換ソリューション」を導入することをおすすめします。
例えば、ジー・プランの「ポイント・コンセント」は、独自ポイントを共通ポイントなどに直接交換するプラットフォームで、人気のポイントを中心に約150社の銘柄と提携しているので、導入することも選択肢として検討してはいかがでしょうか。
おすすめの資料はこちら
関連記事









