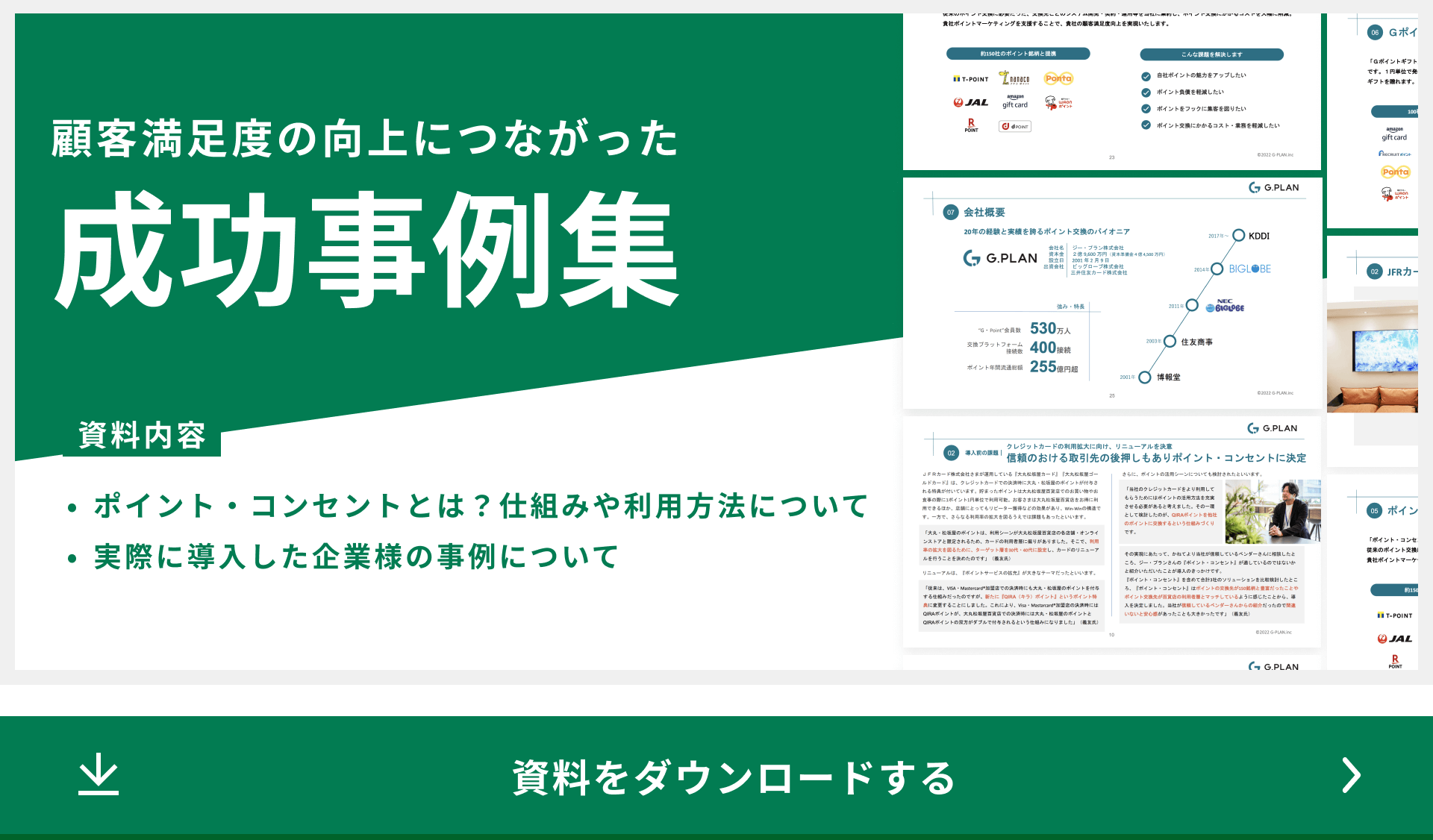【初心者向け】顧客満足度の指標とは?指標や重要視すべき理由、向上させるためのポイントを解説!
企業が売上や利益を伸ばしていくためには、顧客のニーズを継続的に満たしていかなければなりません。そのためには、顧客の動向について理解しておく必要があり、顧客満足度の指標が重要になってきます。
まずは顧客満足度調査を実施した上で、その指標を分析し向上のための施策を検討するのが望ましいです。
本記事では、顧客満足度の指標について、重視すべき理由や向上させるためのポイントなどを中心に解説していきます。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 顧客満足度の指標により自社の商品やサービスを数値で評価できる
✓ポイント2 顧客満足度の指標は調査によって得られた数字をもとにして算出できる
✓ポイント3 顧客満足度の指標が悪いときには改善のための施策が必要
目次[非表示]
- 1.顧客満足度の定義とは?
- 2.顧客満足度の主な指標は3つ
- 2.1.1.NPS®(Net Promoter Score)
- 2.2.2.CSI(Customer Satisfaction Index).
- 2.3.3.JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)
- 3.顧客満足度(CS)を重要視すべき4つの理由
- 3.1.1.リピーターを増加させるため
- 3.2.2.ブランディングを強化するため
- 3.3.3.新規顧客を獲得するため
- 3.4.4.商品・サービスのブラッシュアップにつなげるため
- 4.顧客満足度(CS)を向上させる5つのポイント
- 4.1.1. 顧客の満足を定義する
- 4.2.2. 顧客が求めている以上のサービスを提供する
- 4.3.3.顧客満足度の調査を行う
- 4.4.4.顧客との接点を増やす
- 4.5.5. ポイントサービスを活用する
- 5.顧客満足度調査の実施方法は4つ
- 5.1.1.インターネット調査
- 5.2.2.メール、ハガキ調査
- 5.3.3.対面インタビュー
- 5.4.4.電話インタビュー
- 6.顧客満足度の指標についてよくある3つの質問
- 7.【まとめ】
- 8.おすすめの資料はこちら
顧客満足度の定義とは?
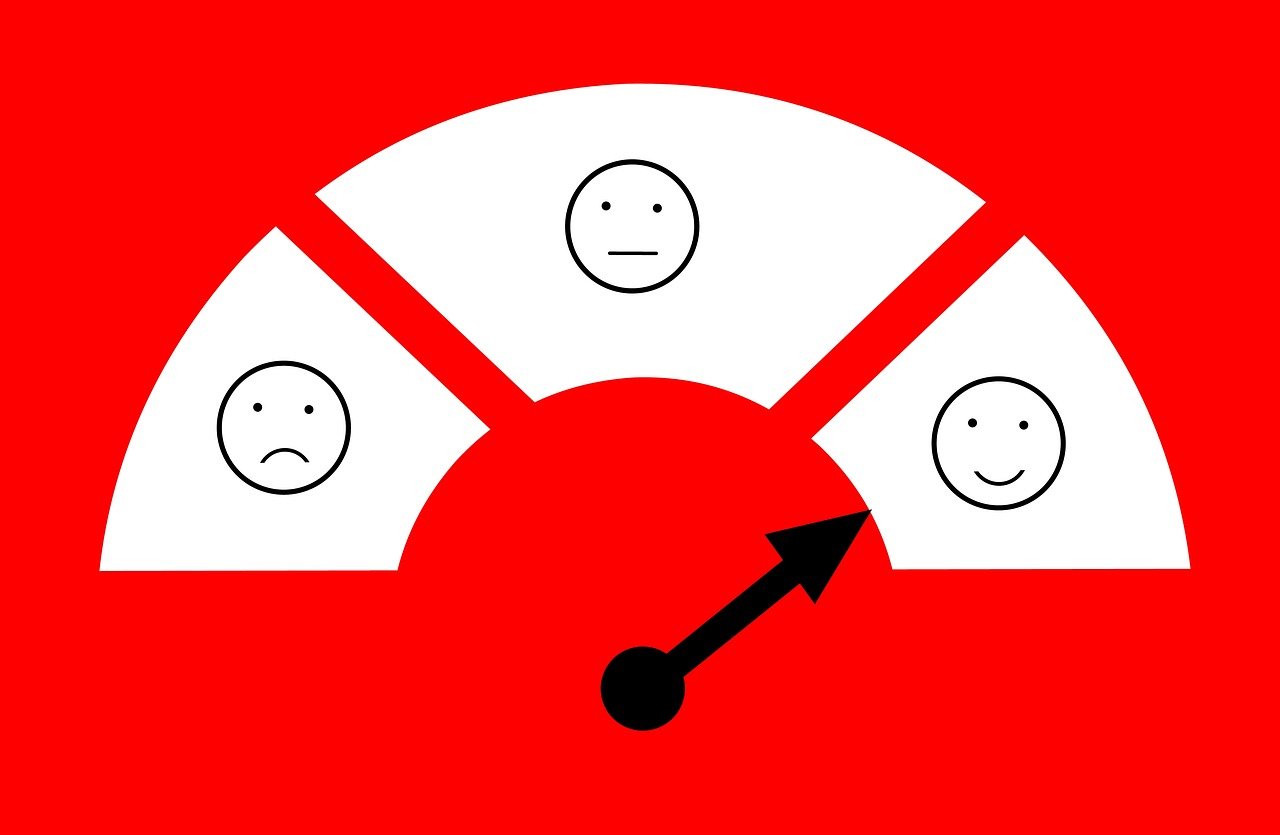
顧客満足度というのは、顧客が自社の商品やサービスに対して、満足している度合いを数値化したものです。英語にすると「Customer Satisfaction」になるため、その頭文字を取ってCSと略して表記されることもあります。
顧客が満足している度合いを数値化する際には、客観的なデータを取った上で行うので、自社の商品について評価する上でも顧客満足度を用いることができます。顧客満足度の数値を根拠に、今後のマーケティング戦略の方向性を決めることもよくあります。
顧客満足度の主な指標は3つ
顧客満足度を測定する際には、主に次の3つの指標が用いられます。では、それぞれの指標について詳しく見ていきましょう。
1.NPS®(Net Promoter Score)
NPS®(Net Promoter Score)は主に顧客ロイヤルティや愛着度などを測定する際に用いられる指標です。
顧客が自社の商品やサービスに対してどの程度の忠誠心があるのか、知人などに対して積極的に勧めようとしてくれるのかといったことを数値化したものです。
そのため、顧客が単に自社の商品やサービスに満足しているだけでは、NPS®の数値はあまり高くはなりません。顧客が友人や知人などに対して、自社の商品やサービスを勧める行動を取ってくれるかどうかがNSP®の数値に影響を与えます。
具体的なNSP®の測定方法は「この商品を誰かに推薦・紹介したいか」という質問を顧客に対して行い、その回答をもとにして集計・計算するというものです。
顧客は0から10までの11段階で回答します。数字が高いほど自社の商品やサービスに対するロイヤルティや愛着が高めです。そして、回答が10点と9点の顧客は推奨者とされます。8点と7点は中立者で、6点以下の顧客は批判者です。その3つのグループに分けてから、推奨者の割合と批判者の割合を算出し、差を取るとNPSの数値になります。
2.CSI(Customer Satisfaction Index).
CSI(Customer Satisfaction Index)は顧客に対して、自社の商品やサービスに関連性の高い質問をいくつか行うことで、顧客満足度を測定する指標です。顧客の意見や感想を網羅的に収集することで、統計的な分析が可能になります。
質問は次の5項目です。
- 顧客期待値
- 顧客不満度
- 顧客忠実度
- 知覚品質
- 知覚値
知覚品質というのは、商品に対する顧客の主観的な評価のことです。知覚値は商品の価格に対する満足度を指します。品質に問題のない商品だとしても、価格が高ければ知覚値は低くなることもあるでしょう。
質問は次のような具合で行います。
- 「〇〇(商品名)に対してどの程度の期待をしていましたか?」
- 「〇〇(商品名)を使用してみて不満に感じた度合いはどの程度でしたか?」
- 「〇〇(商品名)の価格に対してはどの程度満足していますか?」
顧客はこれらの質問に対して0〜100点の範囲内で回答し、その回答の平均値を算出するというものです。これにより、顧客が商品やサービスに対してどれだけ満足しているかを定量的に評価することができます。
データ数が多く集まれば信頼性がさらに高まります。
3.JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)
上で紹介したCSIは日本の産業形態にはあまり合わないこともあります。そこで、CSIを日本の産業環境に適した形でカスタマイズしたのがJCSIです。CSIと同じように、顧客に対して自社の商品やサービスに関連する質問を行いますが、質問する項目に「推奨意向」が加えられています。
「推奨意向」というのは、自社の商品やサービスを友人や知人などに勧めたいかどうかを尋ねるものです。
質問への回答の仕方はCSIと同じで、平均値を算出するという点に関しても、CSIと変わりません
顧客満足度(CS)を重要視すべき4つの理由
顧客満足度は企業にとって非常に重要なデータです。では、なぜ企業が顧客満足度を重要視しなければならないのか、その理由について見ていきましょう。
1.リピーターを増加させるため
リピーターが多いか少ないかは、企業の長期的な利益に大きな影響を与えます。その理由はLTV(Life Time Value/生涯顧客価値)が関係しており、新規顧客の獲得に力を入れるよりも、リピーターの獲得に力を入れた方が効率が良いためです。リピーター獲得なら新規顧客を獲得する場合と比べて、5分の1程度のコストで済みます。
そして、顧客の多くは、自分の期待値を上回る価値を提供されれば、リピーターになってくれます。そのため、顧客満足度を測定し、自社の商品やサービスが顧客の期待値に対して、どうだったのか把握しておくことが重要です。
もし、自社の商品やサービスが顧客の期待値より低かった場合でも、そのことが早期に判明し、改善策を検討できます。
LTVについてはこちらの記事もご覧ください。
▼【2023年最新】LTV向上につながる11の施策|計算方法や高めるメリットをわかりやすく解説!
2.ブランディングを強化するため
ブランディングとは、企業が自社の強みやポジションなどを同じ業界内で確立し、認知度を高めるための取り組みのことです。企業が自社の独自性や魅力を一般に広く伝えるための戦略的な手段として用いられます。
ブランディングを強化することで、自社やブランドのイメージを構築し、顧客の心に響く存在として定着させることができます。これにより、顧客は自社や自社のブランドに対して信頼感や安心感を抱き、商品やサービスを優先的に選択するようになるでしょう。そのため、長期的に利益や売上をアップさせていくのに役立ちます。
強力なブランディングを確立できれば、価格が多少高くてもそのブランドだからという理由で選んでくれる顧客も多いです。
3.新規顧客を獲得するため
新規顧客の獲得は、売上や利益を獲得するのにかかるコストという面で見れば、リピーターに及びません。しかし、リピーター獲得にだけ注力すればいいわけではなく、新規顧客獲得にも、ある程度リソースを割く必要があります。
そして、新規顧客獲得においても、顧客満足度は重要です。顧客満足度が高ければ、既存顧客が友人や知人に対して、積極的に自社の商品やサービスを勧めてくれます。リアルの友人や知人だけでなく、SNSなどを通じて不特定多数の人に勧めてくれることもあるでしょう。そこから上手くバズって良い評判が広まれば、大勢の新規顧客獲得につながる可能性もあります。
4.商品・サービスのブラッシュアップにつなげるため
現在リピーターが多い商品やサービスでも、今後ずっと売れ続けるとは限りません。同業他社が、もっと魅力的な商品を発売したりサービスをリリースしたりして、そちらに乗り換えられてしまう可能性もあります。
そのような場合に備えて、商品やサービスのブラッシュアップが必要です。ブラッシュアップを続けていれば、リピーターをつなぎとめやすくなるでしょう。そして、ブラッシュアップのためには、定量的なデータが必要です。顧客満足度の測定によって得られる定量的なデータがあるからこそ、顧客のニーズを満たすブラッシュアップが実現できます。
顧客満足度(CS)を向上させる5つのポイント

顧客満足度を向上させるためには、次のようなポイントを押さえておく必要があります。
1. 顧客の満足を定義する
顧客の満足度に関する「明確な定義」は、顧客満足度を向上させる上で重要な要素です。自社において「顧客満足」とは何を指すのか、どのような状態を目指すのかを明確に定めて、社内全体で共有する必要があります。
社内で共通の理解がないと、施策に一貫性がなくなる可能性も高くなります。また、施策を実施した後に評価を行うのが基本ですが、共通理解がなければ適切な評価が難しくなり、次の施策に上手く活かせなくなってしまう可能性があります。
顧客満足度の定義が明確になっていれば、一貫性のある施策を実施することができるため、施策を重ねるごとに改善していくことができるでしょう。
2. 顧客が求めている以上のサービスを提供する
顧客のニーズを把握したら、それを満たす内容のサービスを提供すれば顧客満足度も向上する、と考えている人は多いでしょう。たしかに、顧客のニーズを満たすことで、顧客満足度はある程度向上します。少なくとも指標で悪い数字が出てしまうことはないでしょう。
しかし、顧客のニーズを満たすだけでは十分とはいえません。顧客にとっては、自分のニーズを満たしてくれるのは当たり前という考え方をする人もいます。そのため、リピーターになってもらうためには、顧客が求めている以上のサービスを提供するのが望ましいです。
同業他社で顧客のニーズを満たすだけにとどまっている場合には、それ以上のサービスを提供することで、差をつけることができるでしょう。
3.顧客満足度の調査を行う
顧客満足度を向上させるためには、自社の視点では気づけないような意見や新たなニーズを発掘する必要があります。そのため重要なのが顧客満足度の調査です。
そして、顧客満足度の調査を実施する際には、その対象に偏りがないようにする必要があります。顧客満足度の調査対象が特定の層に偏っていると、顧客全体のニーズを反映するものにはなりません。特に既存の優良顧客を中心に調査を実施した場合には、新規顧客のニーズとの乖離が大きくなります。その調査結果をもとにして施策を実施しても、なかなか芳しい結果にはつながらないでしょう。
既存の優良顧客から新規顧客、若年層、シニア層など、幅広い層を対象として調査を実施することが大切です。
4.顧客との接点を増やす
業種によっては、顧客と直接接する機会がほとんどない場合もあるでしょう。展示会やセミナーなど自社で顧客と直接接する機会を設けることはできますが、実際に顧客が参加してくれるとは限りません。一部の優良顧客の中には積極的に参加する人もいるかもしれませんが、一般の顧客はなかなか参加しようとはしないでしょう。
そこで、SNSなどを活用して顧客との接点を増やす方法が効果的です。SNSなら、参加のハードルが低くなります。自社の商品やサービスに対して、それほど強い思い入れのない顧客でも参加してくれる人が多いでしょう。
SNSを通じて情報発信することで、顧客が自社をより身近に感じることができます。それがきっかけで信頼関係が築き上げられて、顧客満足度の向上につながることも多いです。
5. ポイントサービスを活用する
最近ではポイ活などにより、ポイントを積極的に貯めようとしている人が増えています。ポイントサービスを導入して、自社の商品購入やサービスの利用でポイントを付与するのが効果的です。
ただ、自社ポイントだと、使える場が限られていることで、不満を持つ顧客も出てくるかもしれません。そこで、ジー・プランの「Gポイント交換」や「ポイント・コンセント」などのサービスがおすすめです。
「Gポイント交換」は自社ポイントを「Gポイント」を介して、他の共通ポイントなどに交換できます。交換先のポイントは100種類以上です。「ポイント・コンセント」なら、自社ポイントを他の共通ポイントや電子マネーなどに直接交換できます。
そのため、顧客にとってはポイントを使える場が限られていることで不満に感じることはありません。顧客満足度の向上のためにポイントサービスを導入するなら、ぜひ「Gポイント交換」や「ポイント・コンセント」の利用を検討してみてください。
顧客満足度調査の実施方法は4つ
顧客満足度調査を実施する際には、次のような方法で行います。
1.インターネット調査
インターネットを介してオンライン上で回答を集める調査方法です。専用のサイトやアンケートツールなどを利用して実施します。期限内であれば、顧客は好きなときに回答できます。
一度に多くの顧客に対してアンケートを実施できて、場所を問わずに回答できるため、幅広い層の顧客を対象にできるのがメリットです。集計も自動的に行いやすく、手間もかかりません。
2.メール、ハガキ調査
アンケートをお願いする旨の内容のメールを送信したりハガキを送付したりする調査方法です。インターネット調査と同様に、顧客は好きなときに回答できます。
ただし、回答を集計するのに手間がかかるのがデメリットです。ハガキの場合には郵送費などのコストもかかります。
3.対面インタビュー
対面インタビューは、顧客と実際に対面して質問をする調査方法です。直接話ができるため、質問内容について詳しく聞くことができます。
ただし、インタビューをするための機会を設けなければなりません。そのため、時間もコストもかかります。また、調査対象が狭くなってしまいがちなのもデメリットです。遠方の地域に住んでいる顧客に対して対面インタビューを実施するのは難しいため、どうしても近場に住んでいる顧客に限られてしまうでしょう。ただし、最近ではオンラインで実施することも可能です。
4.電話インタビュー
顧客に電話をかけて質問する調査方法です。対面インタビューよりは、手間やコストを抑えて実施することができます。また、地理的な制約を受けることもありません。遠方の地域に住んでいる顧客に対しても電話インタビューを実施できます。
ただし、電話インタビューも調査対象が狭くなってしまうことが多いです。電話番号が分かる顧客に対してしか実施することができません。
顧客満足度の指標についてよくある3つの質問
顧客満足度の指標に関して、よくある質問とその回答について見ていきましょう。
質問①顧客満足度調査をする際の注意点は?
顧客満足度を調査するにあたって、どんなことに注意すればいいのか気になっている人は多いでしょう。調査のやり方が良くないと、その調査によって得られた指標の数字も信頼性の低いものになってしまいます。そうなると、施策を実施しても、なかなか売上や利益が伸びないでしょう。
顧客満足度の調査を行う際に注意したいことは、3つあります。まず、顧客の現状を企業が把握すること。そしてその現状を踏まえて、顧客が企業に対してどんな期待を持っているのかを把握すること。最後に、その期待を超える改善を行っていくことです。
そしてその上で重要なことは、顧客満足度調査を定期的に繰り返し実施することです。そうすることで、調査結果から得られる指標も次第に変化してくることが分かります。指標の数値が改善しているのであれば、施策が上手くいっていると判断できるでしょう。指標の数値が変わらなかったり、悪化していたりする場合には、施策の内容に問題があるのかもしれません。施策を見直してみて、次回以降の調査で指標の数値がどう変化するのか注視していきましょう。
もし、顧客満足度調査を1回しか実施せずに施策を実施していた場合には、施策の効果を検証したり改善したりすることができません。
質問②顧客満足度調査のデメリットは何ですか?
顧客満足度調査を実施する際に、メリットだけでなくデメリットも把握しておきたいでしょう。費用対効果を考える上でも、デメリットの把握は大事です。
そして、顧客満足度調査を実施することのデメリットとしては、企業にとって負担が大きいことが挙げられます。
前章で4つの方法を提示しましたが、もっとも簡単なインターネット調査を実施する場合でも、専用のサイトを制作するなど、かなりの手間がかかります。データを収集した後の分析にも手間と時間がかかるでしょう。また、外部に委託して実施するケースも考えられますが、その場合はコストもかかります。
そのため、顧客満足度調査を実施するのであれば、十分な人的リソースや予算を確保しておく必要があります。余裕がない状況だと、顧客満足度調査を実施するのは難しいかもしれません。
質問③顧客満足度を高める方法はありますか?
顧客満足度を向上させる方法としては、サービスのクオリティを平準化することが挙げられます。スタッフによってサービスのクオリティに差があることで、不満につながるケースは多いです。例えば、前回利用したときにはクオリティが高く満足した場合でも、次に利用したときに同程度のクオリティのサービスを受けられなかったら、顧客は不満を持つこともあるでしょう。
スタッフによるサービスのクオリティの差をなくすには、マニュアルなどを整備したり研修を実施したりする必要があります。マニュアルがあれば、一貫した方法でサービスを提供することが可能になり、スタッフによるクオリティの差は生じにくくなるでしょう。定期的に研修を実施することで、サービス提供に必要な知識やスキルを向上させることもできます。
顧客満足度を高めるのに効果的な方法は他にもいくつかありますが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
https://www.g-plan.net/service/blog/94
【まとめ】
顧客満足度の指標は、顧客が自社の商品に対して満足している度合いを数値化したものです。代表的なものとしてNPS®、CSI、JCSIの3種類があります。指標の数値を得るには、調査を実施してデータを収集しなければなりません。データを計算式に当てはめることで、指標の数値を算出できます。
顧客満足度の指標が良い数値の場合には、リピーターを獲得できていて、ブランディングが強化されていることが多いです。
もし、数値が良くなかった場合には、原因を分析した上で、施策を実施して改善策を考える必要があります。顧客との接点を増やしたりポイントサービスを導入したりして、少しずつ改善を図っていきましょう。
Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。
おすすめの資料はこちら
関連記事