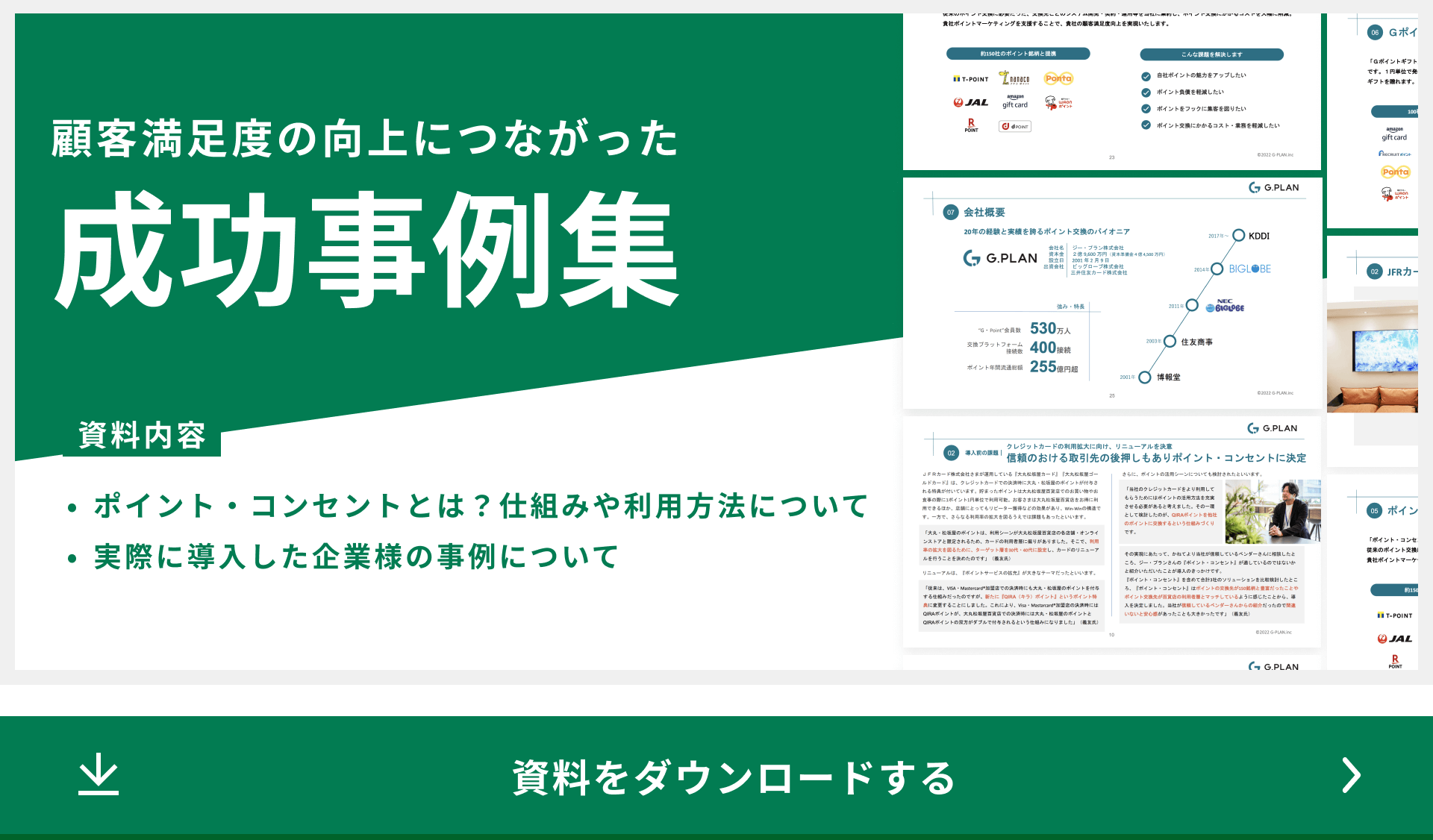顧客満足度(CS)を上げる接客が欠かせない理由とは?実践すべき心がけや取り組む手順も解説します!
本記事では、顧客満足度(CS、Customer Satisfaction)を上げる接客が欠かせない3つの理由や、接客で押さえておきたい3つのポイント、実践するべき5つの心がけ、やっていけないこと、取り組む手順について解説します。
よくある質問(および、それに対する回答)や、顧客満足度の向上に取り組む際に役立つポイントソリューションもご紹介するので、ポイント施策を担当している方は、ぜひ参考にしてください
<この記事のポイント>
✓ポイント1 売上を増加させるためには、顧客満足度を上げる接客が欠かせない
✓ポイント2 心がけるべきこと、やってはいけないことを把握して接客に取り組もう
✓ポイント3 ポイントサービスを実施することも、顧客満足度の向上につながる
目次[非表示]
- 1.顧客満足度(CS)を上げる接客が欠かせない3つの理由
- 1.1.1.リピート率がアップするため
- 1.2.2.紹介数が増えるため
- 1.3.3.事前期待を超えるため
- 2.顧客満足度(CS)を上げる接客で押さえておきたい3つのポイント
- 2.1.ポイント1.傾聴
- 2.2.ポイント2.マニュアル化
- 2.3.ポイント3.質問力
- 3.顧客満足度(CS)を上げる接客で実践すべき5つの心がけ
- 3.1.1.大事なお客様ほど手厚く対応する
- 3.2.2.ゆったりとやわらかな動きを心がける
- 3.3.3.笑顔で安心感を与える
- 3.4.4.アナログなつながりを持つ
- 3.5.5.まずは共感する
- 4.顧客満足度(CS)を上げる接客でやっていけないこと
- 5.顧客満足度を上げる接客に取り組む手順は4ステップ
- 5.1.ステップ1.顧客満足度の「定義」を社内で統一する
- 5.2.ステップ2.現状の課題について調査する
- 5.3.ステップ3.具体的な数値目標を設ける
- 5.4.ステップ4.継続的に業務改善を行う
- 5.5.顧客満足度の向上に効果的なポイントマーケティングを導入する
- 6.顧客満足度を上げる接客でよくある3つの質問
- 7.【まとめ】
- 8.おすすめの資料はこちら
顧客満足度(CS)を上げる接客が欠かせない3つの理由
以下、顧客満足度(CS)を上げる接客が欠かせない理由を3つご紹介します。
1.リピート率がアップするため
顧客満足度が向上すると、リピート率が上がります。リピート率を上げることは、売上アップを目指すうえで大切です。
なお、「住宅」「電話」「インターネット回線」の契約など、「一度購入・契約したら、その後は何度もリピートしない商品・サービス」も存在します。
しかし、同じ商品・サービスの購入でなくても、ほかの商品・サービスや有料オプションを追加で申し込んでくれる場合があるので、顧客満足度を上げる接客が欠かせません。
2.紹介数が増えるため
「満足した」と感じた場合、その商品・サービスを、身近な人(家族、友人など)に紹介したくなるものですよね。つまり、顧客満足度が上がれば、「新規顧客の紹介」も増えると言えます。
業種・業界によっては、紹介で新規顧客を獲得する割合が多いケースもあるでしょう。そのような業種・業界では特に、顧客満足度の向上が非常に重要になります。
3.事前期待を超えるため
事前期待(「このようなメリットを得られるだろう」という期待)を超えるためには、顧客満足度を上げる接客が欠かせません。
さまざまな工夫をして、顧客に満足してもらえる接客をすれば、事前に期待していた水準を超えることが可能になるでしょう。
顧客満足度(CS)を上げる接客で押さえておきたい3つのポイント
顧客満足度(CS)を上げる接客を実現したいのであれば、以下の3点を押さえておきましょう。
ポイント1.傾聴
最も重要なポイントは、顧客の声に丁寧に耳を傾けること(傾聴)です。
「この商品・サービスを売りたい」という気持ちが先立って、一方的に商品説明をしてしまう販売員がいますが、「無理やり売ろうとしている」「押しつけがましい」という印象を与え、逆効果になりかねません。
まずは、先入観なしで、顧客の声を正しく聞き、顧客の嗜好やライフスタイルに適した商品・サービスをおすすめしましょう。
ポイント2.マニュアル化
「販売担当者全員が最低限実施するべきこと」を「マニュアル」にまとめることも重要です。
マニュアルで決めた項目を浸透させるためにスタッフに研修を行い、全員が実行できるようにしたうえで、個別の対応を行えば、顧客満足度の向上を実現できます。
ポイント3.質問力
顧客が求めているものを聞き出す力を磨くことも大切です。これを「質問力」といってもいいでしょう。
顧客から販売員に語りかけてくる内容だけでは、「本当は何を求めているのか」が分からないケースもあります。その場合、「真に求めているもの」を見抜くために、販売員側から質問を投げかけなければなりません。
顧客満足度(CS)を上げる接客で実践すべき5つの心がけ
ここからは、顧客満足度(CS)を上げる接客において実践するべき5つの心がけをご紹介します。
1.大事なお客様ほど手厚く対応する
すべての顧客に対して、同じ対応をする必要はありません。大事な(重要性が高い)顧客ほど、手厚く対応することを心がけましょう。
「1度しか購入しない顧客」「少額商品しか購入しない顧客」に時間・労力を割くよりも、「繰り返し購入してくれる顧客」「高額な商品を購入してくれる顧客」に対して接客するための時間・労力を割くほうがトータルでの売上増につながります。
2.ゆったりとやわらかな動きを心がける
ゆったりとやわらかな動きを心がけることは、接客の基本です。それが丁寧な印象を与えるからです。逆に慌てて行動したり、せかせかと動いていたりしてしまうと、それだけで雑な印象を与えかねません。
また、動きだけではなく、敬語や謙譲語など、正しい言葉遣いを習得しておくことも重要です。
3.笑顔で安心感を与える
接客においては、笑顔で安心感を与えることが大切です。販売担当者が笑顔で接客すれば、店舗内の居心地が良くなり、安心できる環境になるでしょう。その結果、商品の販促につながり、リピーターとして再来店してもらえる可能性も高まります。
顧客の前では、常に口角や目元を緩めた表情をするように心がけましょう。近年、笑顔などの表情を識別・検出できるITツールも登場しているので、「きちんと笑顔になっているかどうか」を確認するために活用してはいかがでしょうか。
なお、マスクを着用している場合は、目元だけでも和らげてください。「目は口ほどにものを言う」ということわざがあるように、目元は安心感を与えるうえで重要な要素です。
4.アナログなつながりを持つ
「IT化が進んでいるから、紙媒体のチラシやパンフレット、ダイレクトメール、ハガキ、手紙などは必要ない」とお考えの方がいるかもしれません。
しかし、IT化が進んでいるからこそ、逆に「アナログなつながり」が重要になっています。メールは一斉に送信することが可能であり、印刷コストもかかりませんが、受け取った顧客は「ほかの顧客にも同じような文面を送っているんだろう」と感じてしまいがちです。また、メールボックスの中で埋もれたまま、目を通してもらえない可能性もあります。
紙媒体(チラシ、パンフレット、ダイレクトメールなど)は、印刷・郵送する手間・コストがかかりますが、「郵便受けに入っているものを顧客自身が回収する」というプロセスがあるため、目を通してもらいやすくなるでしょう。
また、無味乾燥な定型文を送付するのではなく、顧客ごとに内容を変えて、手書きのハガキや手紙を送付すれば、顧客に対して「大切にされている」「気にかけてもらえている」という特別感を与えることが可能です。
5.まずは共感する
人間は、「自分に共感してくれる人物」を好きになる傾向があります。なお、共感とは「あなたは、そう感じたんですね」と反応することを意味し、販売員自身が同じ気持ちを持っていなくても問題はありません。
例えば、顧客から「病気を克服した」という話を聞いたら「それは、大変なことでしたね」と、「サイクリングをすると、風が心地よく感じる」という話を聞いたら「自動車とは違って、直接、風を感じれるのは良いですよね」といった具合に共感を伝えましょう。
顧客満足度(CS)を上げる接客でやっていけないこと
以下、顧客満足度(CS)を上げる接客において、やってはいけないことを2つご紹介します。
過剰なサービス提供
予算や人員は有限です。「顧客満足度向上は、何よりも優先する」と考えて、過剰にサービスを提供するのはやめましょう。人件費・輸送費などのコストを上昇させ、利益を減少させかねません。
過剰なサービスの提供は、値下げと同じ効果を生じさせる場合もあります。例えば、「荷物運び」「駅からの送迎」「傘の提供」を有料サービスにすれば売上になるところ、「顧客が喜ぶから」という理由で無償にすると、その分の利益を獲得できなくなり、採算が合わなくなる場合があるのでご注意ください。手厚いサービスを提供するのであれば、それ相応の対価を受け取るべきです。
対応の放置
顧客からの問い合わせがあった場合、放置せずに速やかに対応しましょう。放置していると、「無視されている」と感じて満足度が低下してしまいます。
顧客満足度を向上させたいのであれば、問い合わせや相談への対応を疎かにせず、迅速かつ丁寧に対応しましょう。
顧客満足度を上げる接客に取り組む手順は4ステップ
ここからは、顧客満足度を上げる接客に取り組む手順をご紹介します。
ステップ1.顧客満足度の「定義」を社内で統一する
顧客満足度を上げる接客に取り組むのであれば、まずは「何を持って顧客満足度とするか」という「定義」を社内で統一させなければなりません。
定義を明確化しなければ、スタッフ間で「認識の齟齬」が生じてしまいます。顧客満足度の定義を明確化すれば、一貫性のある接客を実現できるでしょう。
ステップ2.現状の課題について調査する
顧客満足度の定義を統一したら、「現状の課題」について調査しましょう。具体的には「現状の顧客満足度を把握すること」と「衛生要因と動機づけ要因を把握すること」が欠かせません。
まず、現時点における課題を正確に把握するために、顧客がどのようなニーズや不満を抱えているのかを調査しましょう。そのうえで、「衛生要因は何なのか」「動機づけ要因は何なのか」という点も考えてください。
衛生要因とは、「不満に関わる要因」であり、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグによって提唱されました。「満たされない場合には、満足度が下がってしまう」「満たされてたとしても、満足度が上がらない」とされるものです。
もう片方の動機づけ要因とは、「満足に関わる要因」です。同じくハーズバーグによって提唱されました。「満たされた場合、満足度が上がる」「満たされなくても、満足度が下がらない」とされます。
つまり、衛生要因を満たすだけでは、不満は解消されるものの満足感を得られません。また、動機付け要因を満たすだけでは、満足感は得られるものの、不満は取り除かれません。顧客満足度を向上させるためには、衛生要因と動機づけ要因の両方を満たすように対策を講じる必要があります。
ステップ3.具体的な数値目標を設ける
具体的な数値目標を設定することも重要です。「どのような指標を計測するか」を明確にしたうえで、具体的な数値目標を設定しましょう。
例えば、「顧客に対してアンケートを実施し、〇割以上の顧客から「満足した」という回答を引き出せるように努力する」という数値目標を掲げてみてはいかがでしょうか。
顧客満足度は「個々人の感情」に左右されるため、「数値化しなくても良い」とお考えの方がいるかもしれません。しかし、何らかの形で数値目標を設定しなければ、成果が出ているのかどうかが不明確になってしまいます。そして、改善策を練り上げることもできません。
なお、最初に設定した数値目標が達成にほど遠いものであれば、より現実的な数値目標に変更しましょう。
ステップ4.継続的に業務改善を行う
顧客満足度を向上させるための施策を実施したら、PDCAサイクルを回しながら、継続的に業務改善に取り組みましょう。
PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の頭文字から名付けられた「業務改善に関するフレームワーク」です。「計画→実行→評価→改善→計画→」というプロセスを繰り返すことで、接客の質が向上し、次第に顧客満足度が上がっていきます。
顧客満足度の向上に効果的なポイントマーケティングを導入する
ここまでご紹介した4ステップの手順のほかに、ポイントマーケティングを導入することも顧客満足度の向上に効果的です。
ただし、ポイントシステムの構築には大きなコストが発生します。特に顧客満足度の高いポイント交換を独自に導入すると、さらにコストが増大することになるため、ポイント交換ソリューションを上手に利用するとよいでしょう。
たとえば、ジー・プランが提供するポイント交換ソリューション「ポイント・コンセント」は約150社のポイントと提携しています。「ポイント・コンセント」を導入すれば、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントに、ユーザー自身で直接交換ができるようになります。
成功事例のひとつをご紹介しましょう。
関西電力の会員向けポイントサービスを運用する株式会社かんでんCSフォーラム(大阪府大阪市)では、「ポイント・コンセント」を導入したことで、運用コストを約4割カットすることに成功しました。ポイント交換先の拡充が実現し、会員の満足度は大きく上昇。ポイントサービス開始当初25万人ほどだった会員数が、現在では250万人(2022年2月時点)と、大幅に増加しています。
詳しくはこちら
https://www.g-plan.net/service/case/03
顧客満足度を上げる接客でよくある3つの質問
以下、顧客満足度を上げる接客に関して、「よくある質問」、および、それに対する「回答」を3つご紹介します。
質問1.顧客満足度を把握するための指標はありますか?
以下は、お客様満足の把握に役立つ指標の代表例です。
- CSI(Customer Satisfaction Index):世界約30ヵ国で利用されている顧客満足度を測定するための指標。自社製品に関連する「顧客期待値」「知覚品質」「知覚値」「顧客不満度」「顧客忠実度」の5項目から構成されている。データ数が多いほど信頼性の高い結果を得られるため、大企業や政府等の調査によく用いられる。
- JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index):CSIを日本国内向けにカスタマイズしたもの。CSIの5項目に「推奨意向(商品を他人に勧めたいか)」を加えた6項目から構成される。利用前から利用後までの全体を調査・分析し、「なぜ満足したのか」「どう行動するのか」といった因果関係を明らかするものであり、業界・業種にかかわらず調査・計測することが可能。
- C-SAT:「満足」「普通」「不満」などを視覚的に(星や数字で)表してもらう仕組みであり、Webサイト上やメールアンケートなどで簡単に評価してもらうことが可能。データを集めやすいというメリットがある一方で、「評価に協力的なお客様は、すでにロイヤリティの高い状態にある」という点に注意。
- LTV(Life Time Value):お客様が商品・サービスの利用をスタートしてから終了するまでの間に得られる売上を表す指標。LTVが高いほどロイヤルティが高い傾向にあるため、「優良顧客の割合」を測るために活用される。短期的な計測が難しいため、PDCAサイクルを回しにくい点に注意。
- NPS®(Net Promoter Score):「商品・サービス・企業を、友人や家族に推奨したいかどうか」の度合いを11段階で評価して数値化。お客様のロイヤルティとの相関性が強く、企業の収益向上に焦点を当てた指標。
- CES(Customer Effort Score):「この手続きは、どのくらい大変でしたか」といった質問が記載されたアンケートを、お客様に送付することによって実施し、「負荷」「ストレス」というネガティブな側面を計測する。CESが高ければ不満要素が多く、低ければロイヤリティが高いと判断される。
- CRR(Customer Retention Rate):「顧客維持率」を表す指標で、既存の顧客が一定期間にどの程度取引を続けているかがわかるため、スコアが高ければ顧客満足度も高いと考えられる。スコアが下がる大きな原因は、商品やサービス自体の品質よりも、問い合わせ時の対応が悪かったなど心理的な要素が大きいとされている。
それぞれの特徴を把握したうえで、自社に適した指標をご活用ください。
質問2.顧客満足度を上げる接客に活用できるツールはありますか?
顧客満足度を上げる接客に活用できるツールとして、再来店や再訪問を促すことができる「ポイントサービス」があります。
「自社の独自ポイントのみを提供する」という選択肢もありますが、顧客にとっての利便性を向上させ、満足度向上につなげたいのであれば、「独自ポイントを他社ポイントと交換する仕組み」を用意するほうが良いでしょう。
たとえば、ジー・プランが提供するポイント交換ソリューション「Gポイント交換」を導入すれば、Gポイントを経由することで、自社独自ポイントを100種類以上のポイント銘柄に交換することができます。
また、約150社のポイントと提携する「ポイント・コンセント」を導入することで、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントに、ユーザー自身で直接交換可能です。
質問3.顧客の事前期待を把握する方法はありますか?
顧客満足度(CS)向上のためには、顧客の事前期待を把握することが重要です。そのためには、アンケートやインタビューを実施しなければなりません。インセンティブとして、アンケート回答者に「電子ギフト」を進呈するのも良いでしょう。
ジー・プランでは、初期費用・発行手数料0円から電子ギフトを手軽に導入できる「Gポイントギフト」というソリューションを提供しています。アンケートを実施するのであれば、インセンティブとしてGポイントギフトを活用することも選択肢として検討してはいかがでしょうか。詳細については、こちらのページをご覧ください。
【まとめ】
顧客満足度(CS)を上げる接客が欠かせない理由は、「リピート率がアップするため」「紹介数が増えるため」「事前期待を超えるため」の3つです。本記事でご紹介した「実践すべき心がけ」や「手順」を踏まえつつ、顧客満足度の向上に取り組みましょう。
顧客満足度を向上させるための施策を実施する際には、ジー・プランの各種ソリューション(「ポイント・コンセント」「Gポイント交換」「Gポイントギフト」)を活用することも選択肢として検討してはいかがでしょうか。
おすすめの資料はこちら

関連記事