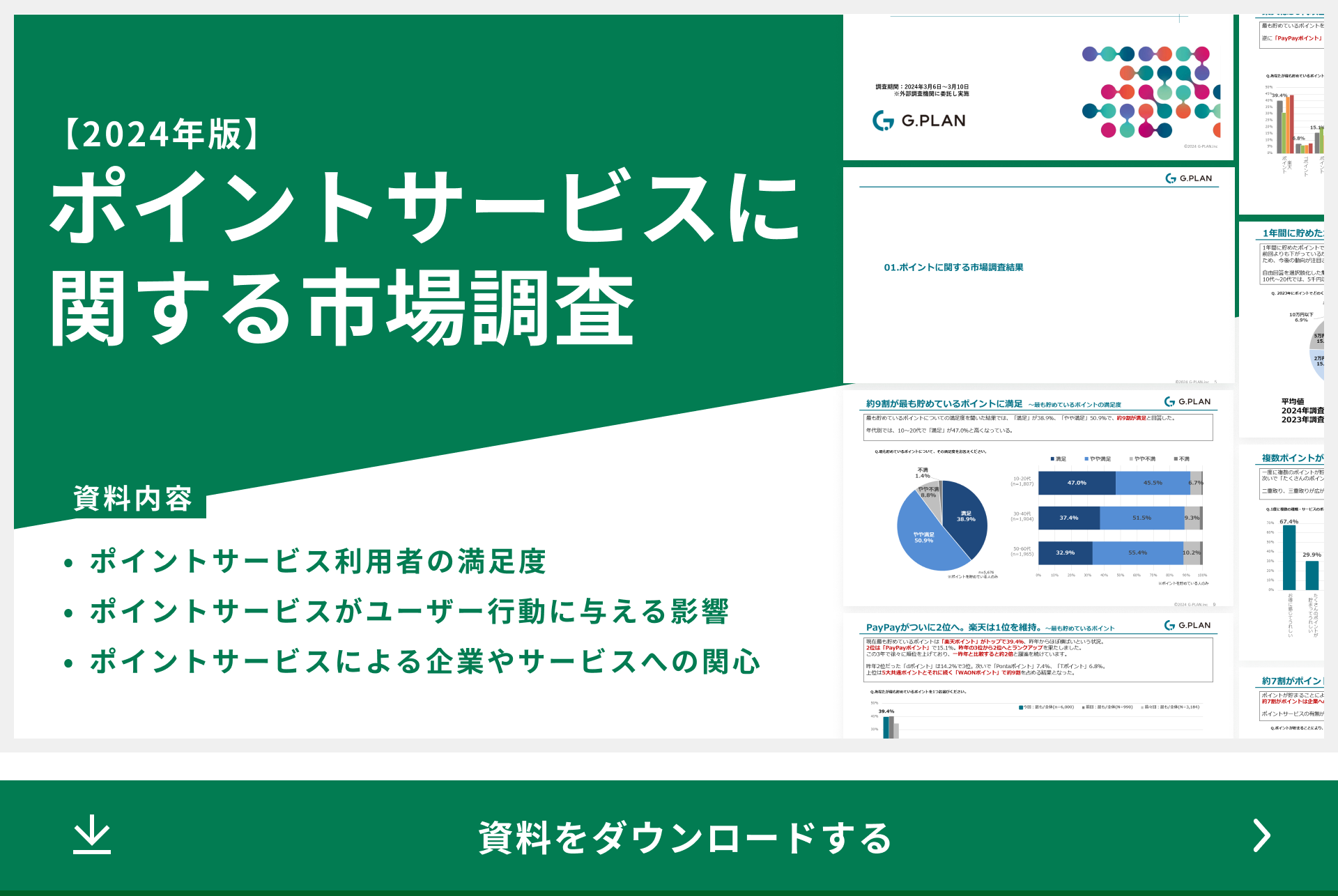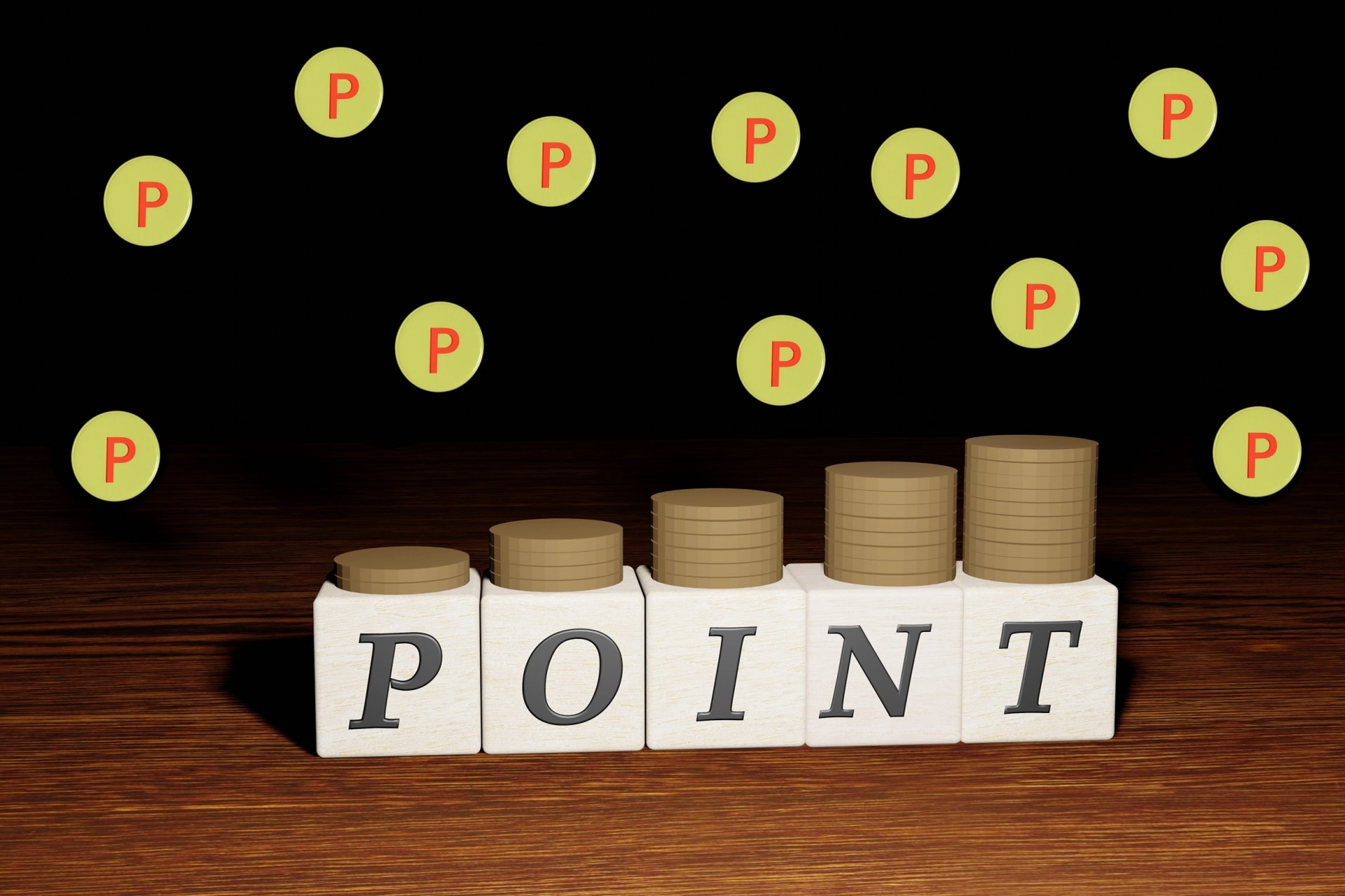
【企業向け】共通ポイントとは?トレンドや特徴、利用するメリット・デメリットを徹底解説!
今やさまざまな企業・店舗が実施しているポイントサービス。
大きく分けると、各企業・店舗が独自に展開する独自ポイント、業種業態を問わず幅広い加盟店で利用可能な共通ポイントの二種類がありますが、最近は特に共通ポイントが大きくシェアを伸ばしています。
代表的なものとしては、Tポイント、Pontaポイント、楽天ポイント、dポイントなどが挙げられるでしょう。
これら共通ポイントは、大手携帯キャリア決済との提携や、大手コンビニチェーン等が複数の共通ポイントに対応する「マルチポイント化」を通じてさらに利用シーンを拡大。マイナポイント事業といった行政施策にも活用されるなど、その勢いはいよいよ増すばかりです。
ただし、独自ポイントであっても、施策次第で共通ポイント同様の販促効果を取り入れることは可能です。
本記事では、ポイントサービス導入のメリットデメリットを解説。4大共通ポイントのトレンドと特徴を比較したうえで、ポイント管理システムについても紹介します。
ポイントサービスの新規導入、もしくは既存のポイントサービスの底上げを検討する際の参考にしてみてください。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 ポイントサービスは「独自ポイント」と「共通ポイント」の二種に大別される
✓ポイント2 ポイントサービスにはデメリットもあるが、販促面ではメリットが上回ることが多い
✓ポイント3 4大共通ポイントの特徴と強みを理解し、ポイントシステム導入及び付加価値向上施策を検討しよう
目次[非表示]
- 1.共通ポイントとは
- 2.企業がポイントサービスを利用する4つのメリット
- 2.1.1.来店率や購入単価のアップ
- 2.2.2.競合他社に対する優位性
- 2.3.3.新規顧客の獲得
- 2.4.4.マーケティングへの活用
- 3.企業がポイントサービスを利用する3つのデメリット
- 4.4大共通ポイントのトレンドと特徴を比較
- 5.ポイント管理システムの比較・選定のポイントは4つ
- 5.1.1.自社に必要な機能を備えているか
- 5.2.2.業界の利用シーンに適切なシステムか
- 5.3.3.同業界での導入実績があるか
- 5.4.4.外部システムとの連携ができるか
- 6.ポイント管理システムでよくある3つの質問
- 7.【まとめ】
- 8.おすすめの資料はこちら
共通ポイントとは
ポイントプログラムは、自社・自店舗の顧客囲い込み及びリピーター獲得を目的として生まれたマーケティング施策のひとつです。
以前は紙のカードにスタンプを押していき、一定数集まったら商品やサービスの提供を受けられるという仕組みが一般的でした。インターネットやスマホの普及を背景に、スタンプではなくポイントを貯めていく形式が主流となりましたが、いずれにせよこの場合、サービスを受けられるのはカード・ポイントの発行店のみである点が特徴です。
これは各企業による独自のポイントシステムなので、独自ポイント、オリジナルポイントなどと呼ばれています。
一方、共通ポイントとは、業種業態を問わず、あらゆる企業・店舗が加盟できるポイントプログラムを指します。ユーザーは、加盟している店舗・企業であればどこでもポイントを貯めることができ、また、貯めたポイントをあらゆる加盟店で使用することが可能です。
例えば、コンビニやスーパー、ガソリンスタンド、美容院、ネットショップ等の利用、通信料金の支払いなど、ユーザーの生活における各シーンで、同一のポイントを貯めたり使ったりすることができるのです。
これら共通ポイントの登場によって、ユーザーは各企業による多様なポイントを個別に管理する必要がなくなり、また、リアル店舗はもちろんネットサービスの利用など、さまざまな消費活動を通してポイントを貯めることができるようになりました。
最近では大手企業同士の連携や通信事業者との提携が進み、利便性がさらに向上したことで、利用者は急激に増加しています。
ポイント付与元が多くなればなるほど、ポイントが貯まる速度は上がります。結果として、各ユーザーのポイント利用金額及び利用機会が増加するため、企業側からみても、共通ポイントの導入には大きな販促効果がありました。
そもそも、企業が独自にポイントプログラムを導入、運営するためには、マンパワーの面でも金銭面でも多大な負担がかかります。また、ポイントによるお得感を演出できる場所は自社店舗・サービスに限定されるため、顧客の囲い込み効果はあるものの、大々的に全国展開しているような大企業を除けば集客効果の面では分が悪いことも事実です。
共通ポイントであれば、既存のポイントプログラムに加盟することで導入及び管理コストは大きく削減可能であるだけでなく、多種多様な加盟店間での相互送客効果が期待できます。また、共通ポイント自体の知名度やブランド力を利用することで、多大なコストをかけることなく顧客への高い訴求効果が見込めます。
共通ポイントのマーケットは、こうしたユーザー側、企業側のメリットを背景として、現在急成長しているのです。
企業がポイントサービスを利用する4つのメリット
では、まず共通ポイント・独自ポイントに関わらず、企業がポイントサービスを導入することによって得られるメリットを、4項目に分けてご紹介しましょう。
1.来店率や購入単価のアップ
ポイントのメリットを感じている顧客にとって、ポイント付与は来店動機となり得ます。結果として来店率の向上や、ついで購入等による購入単価の上昇が期待できます。
また、ポイントには有効期限を設定することができます。特に独自ポイントであれば、有効期限を自社の販売戦略に応じて自由に設定できますから、貯めたポイントの期限内消費を目的とした来店・利用機会を増やすこともできるでしょう。
2.競合他社に対する優位性
同じような商品、サービスであれば、ポイントが付く店・企業で消費しようと考える消費者は少なくありません。同一または類似品の多い商品を扱う事業者であればなおさら、ポイントサービスを導入することで、競合他社よりも優位に立つことが可能となります。
3.新規顧客の獲得
「期間限定でポイント倍付」「新規加入で〇〇ポイント付与」などのポイントキャンペーンを通して、新規顧客の獲得がしやすくなります。
自社の商品・サービス自体を活用したキャンペーンは、企画から実施まで時間もコストもかかりますが、ポイント主体の施策はシステムさえ整っていれば比較的簡単に展開できるため、実施へのハードルが低くなる点もメリットのひとつです。
4.マーケティングへの活用
マーケティング施策を立案するためには、顧客の属性把握や行動分析が必須です。
ポイントサービスではアカウントごとにポイントを紐付けていくことになるため、顧客データ及び購買データを容易に管理、蓄積することができます。こうしたデータを事業の特性に応じて分析すれば、効果的なマーケティング施策に結びつけることができるでしょう。
企業がポイントサービスを利用する3つのデメリット
ただし、ポイントサービスはメリットばかりというわけではありません。一方でデメリットとなり得る面もあるため、導入時には慎重に準備しておく必要があります。
ここではポイントサービス導入に伴う3つの大きなデメリットをご紹介します。
1.収益性の悪化
ポイントは簡単に言えば「値引き」と同義ですが、現時点での値引きではなく、あくまでもポイントが利用された時点での値引きとなる点に注意が必要です。無計画に付与すると、将来的な収益性の悪化につながりかねません。
そのため、ポイントの付与率については、慎重に検討する必要があります。
ただし、付与したポイントがすべて使用されるわけではなく、一定数は有効期限を超過し失効します。実際の利用率や失効率を勘案したうえで付与率を決定するとよいでしょう。
2.客離れの加速
ポイントサービスの使い勝手が悪いと、ポイントに魅力を感じていた顧客が離れてしまう可能性があります。
ポイントの利用先が限定的であったり、有効期限が短すぎたりする場合は、ポイントサービス自体の魅力を十分に引き出すことができず、客離れにつながりかねません。
顧客アンケート等を通じて、顧客にとって魅力的なサービスとは何かを常に把握し、ポイント施策に反映していくことが大切です。
3.会計処理の増加
ポイントサービスを導入すると、会計時の手続きが増加します。現金ベースの会計に加え、ポイントによる支払いが発生するためです。
さらに、ポイント会計は対象によって処理の方法が異なるケースがあり、知識がないと手間取ることもあるでしょう。
事前に下調べを行い、税理士等に相談しておくなど、導入後の混乱を招かないよう準備する必要があります。
4大共通ポイントのトレンドと特徴を比較
共通ポイントのなかでも特に発行ポイント数や会員数の多いTポイント、Pontaポイント、楽天ポイント、dポイントは、「4大共通ポイント」と呼ばれています。
ここでは、4大ポイントそれぞれの特徴について紹介していきましょう。
Tポイント
共通ポイントの草分け的な存在であるTポイントは、カルチュア・コンビニエンス・クラブが展開するポイントプログラム。2003年のサービス開始から、今年で実に20年となる老舗です。
それだけに加盟店も多く、TSUTAYAチェーン、コンビニやガソリンスタンド、ドラッグストア、レストランチェーン、航空会社など、幅広い企業と提携しています。
加盟店で商品購入またはサービス利用すると、基本的に200円の利用ごとに1ポイントが付与され、貯めたポイントは1ポイント=1円として提携店で利用可能。電子マネーの「Tマネー」、クレジットカードの「ファミマTカード」を利用することで、ポイント付与率がアップします。
また、さまざまな商品との交換、ANAのマイルやPayPayポイントへの交換、ポイント投資に利用するなど、使途が豊富である点もTポイントの特徴と言えるでしょう。
2024年春に予定されている三井住友グループの「Vポイント」との統合により、今後どのようなサービスが展開されるのか注目が集まっています。
Pontaポイント
ローソンやリクルート、KDDIなどが出資する「ロイヤリティ マーケティング」により、2010年にサービス提供を開始したPontaポイント。
ローソンはもちろん、リクルート系サービスである「じゃらん」や「ホットペッパー」、さらにスマホ決済の「au PAY」、クレジットカード「au PAY カード」など、auの各種サービスでもポイントを貯めることができるため、auユーザーにとっては特に使い勝手のよい共通ポイントです。
ローソンでは、0:00~15:59の時間帯での利用の場合、200 円(税抜)ごとに1P、16:00〜23:59の時間帯は200 円(税抜)ごとに2Pが付与されます。auの携帯電話、通信利用では1,000円(税抜)ごとに10ポイント付与。「ホットペッパー」で飲食店を予約すると、確定した人数一人につき50ポイント付与されるなど、付与率や条件はサービスによって異なります。
提携するクレジットカードも多く、特に「Ponta Premium Plus」では還元率が最高2~3%と、お得な設定となっています。
楽天ポイント
楽天ポイントは、国内最大級のネットショッピングサイト「楽天市場」を運営する楽天グループが提供。「楽天市場」やその提携サービスの利用によって、基本的には100円につき1ポイントが付与されます。
ファミリーマートや西友、マクドナルドなど、全国展開する大手企業との提携が多く、また楽天でんきや楽天ガスなどのインフラ利用でもポイントが付与されるため、生活のあらゆるシーンで利用しやすい共通ポイントです。
さらに、楽天モバイルの利用でもポイントの獲得及び支払いが可能となり、利便性がアップしました。
楽天ポイントの大きな特徴は、「通常ポイント」と「期間限定ポイント」の二種類に大別される点。楽天市場では「楽天スーパーセール」などのポイントアップキャンペーンを頻繁に開催しており、期間中はポイント付与率が大幅にアップしますが、ここで付与されるのは基本的に「期間限定ポイント」です。指定期間内に消費しなければ失効してしまうため、次の利用につなげやすくなっているのです。
また、楽天グループ内の各種サービス利用数に応じて付与率が変動するポイントアッププログラムや、クレジットカードやスマホ決済「楽天ペイ」、電子マネー「楽天Edy」との併用によって還元率がアップする施策により、グループ内消費・利用を促し、楽天経済圏の確立に寄与しています。
dポイント
NTTドコモが提供するdポイントは、2015年にサービスが開始されました。
携帯キャリアによるポイントプログラムとしては後発であったにも関わらず、現在では勢力範囲を拡大し、勢いのある共通ポイントのひとつです。
ドコモの携帯電話ユーザーであれば、毎月の通信利用料金や端末購入代金に応じてポイントを獲得できるため、非常にお得なプログラムであることはもちろんですが、ドコモユーザーでなくてもdアカウントを作成することで、同様にポイントを貯めることができます。
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど複数のコンビニチェーンに加え、マクドナルド、モスバーガー、ドトールコーヒー、吉野家といった大手飲食チェーンとの提携が多く、利用シーンは非常に幅広いといえるでしょう。
国内他社の各ポイントをdポイントに交換できるほか、台湾やハワイ、韓国など海外で展開する一部のポイントサービスやJALのマイルとは、相互に交換が可能。
基本的には100円の利用につき1ポイントが付与されますが、三ヶ月間の獲得ポイント数に応じたランク制度を導入しており、最大で還元率2.5倍となります。
クレジットカード「dカード」やスマホ決済「d払い」といったドコモの決済サービスを利用することで、ポイントの2重取り、3重取りも可能など、活用方法次第で高還元率が期待できる点も特徴と言えるでしょう。
また、dポイントを使ってのポイント投資も可能です。
ポイント管理システムの比較・選定のポイントは4つ
では、実際にポイント管理システムを導入する場合、どういった点に注視して選定すればよいのでしょうか。
4点の重要要素を解説します。
1.自社に必要な機能を備えているか
まず、自社が必要としているポイント管理の機能とは一体何か、という点を洗い出し、整理しておきましょう。必要な機能は事業の特性によって異なりますから、適切なシステムを選ぶことが大切です
2.業界の利用シーンに適切なシステムか
ポイントを付与するタイミングや使用する時期は、飲食と物販、美容、宿泊など、各業界によってそれぞれ差があるものです。業界のニーズに合致するタイミングでポイントを利用できるかどうか、システムの特徴を踏まえて検討しましょう。
3.同業界での導入実績があるか
上記の通り、一口にポイント管理システムといっても、それぞれ求める機能や仕組みは業界ごとに異なります。同業界での導入実績が多いシステムであれば、全体的な方向性は合っていると推測できるため、絞り込みが容易になるでしょう。
4.外部システムとの連携ができるか
自社のみで完結するのではなく、ポイント交換サービスなど外部システムとのポイント連携が可能であれば、顧客の利便性は飛躍的にアップします。引いては顧客満足度の向上につながります。
例えば、ジー・プランの「Gポイント交換」では、Gポイントを経由することで、ユーザーが貯めた自社のポイントを100種類以上のポイント銘柄に交換可能。また、約150社と提携した「ポイント・コンセント」なら、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントなどに、ユーザー自身で直接交換できるため、ポイントサービスの訴求力が高まるでしょう。
ポイント管理システムでよくある3つの質問
質問①ポイント管理システムを導入する費用の目安は?
ポイント管理システムを導入する場合、大きく分けて以下2つの方法があります。
- ①自社でスクラッチ開発する
- ②ポイントASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ/クラウド型のポイントシステム)を導入する
①は、自社のニーズに応じた最適なシステム構築が可能ですが、その分コストがかかります。発注するベンダーにもよりますが、1,000万~3,000万円ほど想定しておいたほうがよいでしょう。技術レベルや対応可能な機能の幅はベンダーごとに差があるため、希望するシステムの内容と合計予算を照らし合わせて選定することが重要です。
②の場合は、比較的安価で導入することが可能です。おおよそ50万円~300万円程度を見ておくとよいでしょう。ただし、基本システムのままでは自社のニーズに合致しないことも少なくありません。どの程度カスタマイズが可能なのか、その場合の予算はどの程度になるのかなどを、事前にしっかり確認しておきましょう。
質問②ポイントの還元の仕組みは?
共通ポイントのポイント還元には、消費者と店舗、ポイント事業者の三者が関わっています。
ポイントサービスは、消費者が店舗でポイントカードを提示、または特定のアプリやクレジットカードで支払いを行った際、利用金額の数%を消費者に還元する仕組みです。このときポイントに相当する金額、つまり原資を負担するのは、多くの場合は利用店舗(ポイントに加盟している店舗・企業)です。
Yahoo!ショッピング、PayPayモールや楽天市場などの大手ショッピングサイトでも、消費者購入額のおよそ1%をポイント分として加盟店が負担し、ポイント事業者に支払う仕組みになっています。
この負担は加盟店舗にとってはデメリットと言えますが、ポイント原資分を差し引いても、ポイントサービス導入メリットの方が大きくなる理由は、前述した通りです。
また、例えばポイント10倍などのキャンペーンを行うケースでは、加盟店が1%を、残りの9%をポイント事業者が負担するといったケースも少なくありません。
ポイント事業者が原資を多く負担することで、加盟店の負担を軽減しつつ加盟店舗数及び購入額の増加につなげているのです。
こうした大手共通ポイントならではの施策を上手に活用すれば、自社の負担は最低限に抑えながら、効果的な販促キャンペーンに参加することが可能となります。
質問③ポイントサービスの利用率は?
ジー・プランが2023年に実施した「ポイントサービスに関する市場調査」によると、積極的にポイントを集めていると答えたユーザーは71%に上っています。
なかでも、「日常の買い物や行動の中で、貯められるポイントはなるべく逃さないようにする」と回答した「積極派」が54.9%と半数以上を占める一方、「意識的にポイントを貯める行為はほとんどしていない」とする「消極派」はわずか5.8%と、現代における消費者のポイントサービスの利用率の高さが窺える結果となりました。
また、一人のユーザーが一年間に貯めたポイントを金額換算した場合の平均額は25,710円ですが、「1,000円以下」が12.2%、「100,000円以下」「それ以上」が合わせて9.4%になるなど、ユーザーによって大きな開きが見られました。
各ポイントごとの貯めやすさが影響しているとすれば、ユーザーのモチベーションにも密接な関係があると言えるでしょう。
【まとめ】
ポイントサービスの導入は、販促マーケティングにおいて大きな効果のある施策のひとつです。
顧客の継続利用を促しリピーター獲得を容易にするだけでなく、新規顧客獲得や顧客情報の管理、分析にも効果的ですから、いくつかのデメリットを考慮したとしても、導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
現在では共通ポイントの普及が進んでいますが、独自ポイントには自社・自店舗のオリジナルサービスを付加しやすく、また事業に即した設定、展開が可能であるという大きなメリットがあります。
前述したジー・プランの「ポイントサービスに関する市場調査」によると、「ポイントが貯まることにより、その企業の情報やサービスが気になったり、興味が高まったりする」とした人は74%に上りました。ポイントサービスが企業のイメージやブランディングに大きな影響を与えているのです。独自ポイントであれば、その影響はさらに高まります。
ただし、その一方で全体の約1/3は「活用できていないポイントがある」と回答しており、貯めたポイントをどう活用してもらうか、その利用シーンの提供が今後の課題と言えそうです。
そこで、いま導入している自社のポイントプログラムがある場合は、独自ポイントの魅力を維持しつつ、共通ポイントとの提携を図るという方向性も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
例えば前述の調査では、貯めたポイントを他のポイントに交換するポイント交換サービスの利用経験率は75%と、非常に高い数値を示していました。こうしたユーザーの利便性向上施策を講じることで、ポイントの死蔵を避けることができるでしょう。
ジー・プランの提供するポイント交換ソリューション「ポイント・コンセント」「Gポイント交換」なら、独自ポイントの魅力を維持し、導入コストを最小限に抑えつつ、ポイント交換の利便性を顧客に提供することができます。
同時に、独自ポイントにはない利用範囲の広さや販促キャンペーンの訴求効果といった、共通ポイントならではの強みも取り入れることが可能になるのです。
共通ポイントが躍進するいま、こうした施策はマーケティング上非常に有効な手段のひとつと言えるでしょう。
Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。
おすすめの資料はこちら
関連記事