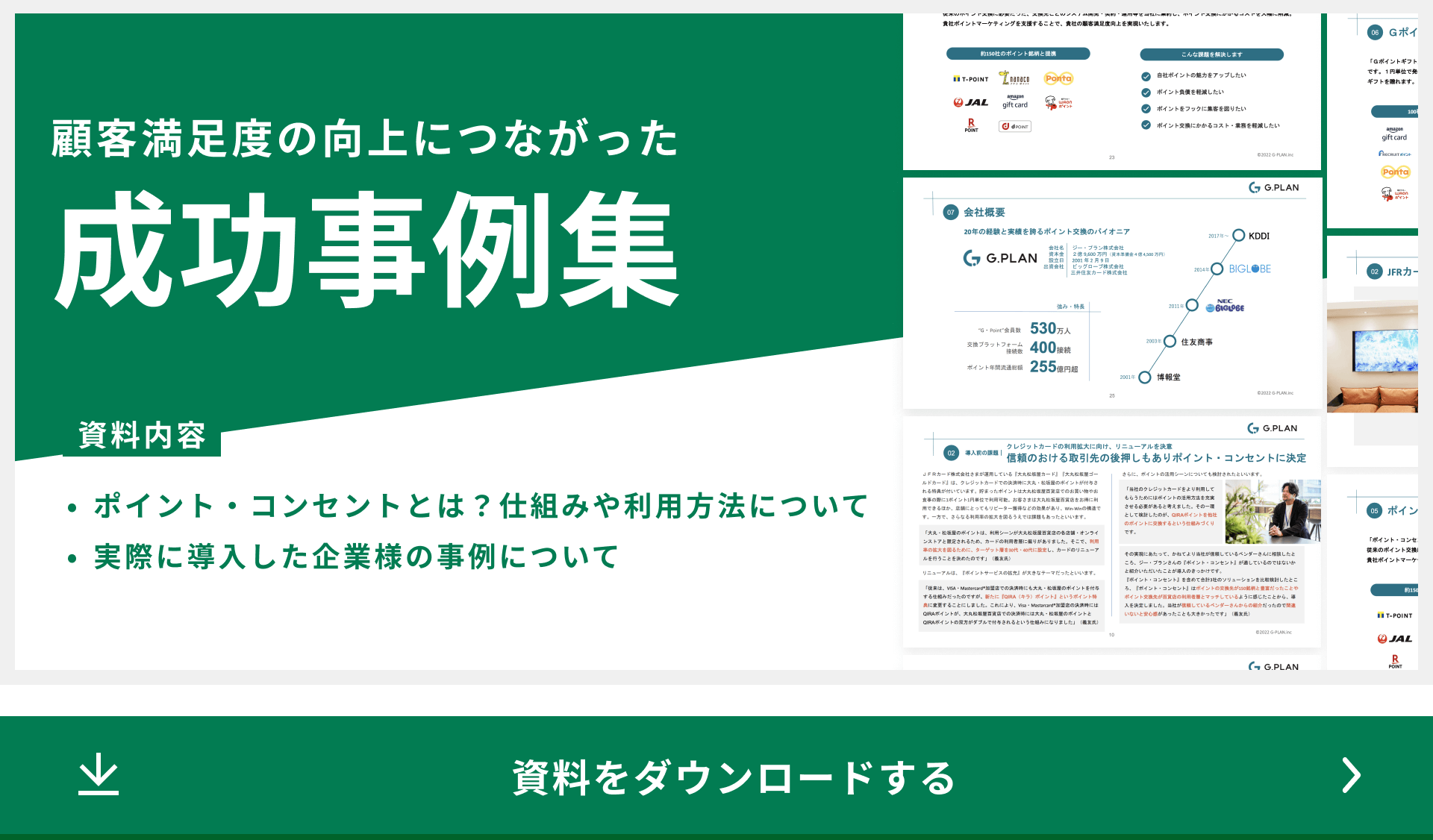【初心者向け】ポイントシステムの仕組みとは?導入する目的とシステムの比較ポイントを紹介します!
顧客に対してポイントサービスを提供するためには、「ポイントシステム」と呼ばれるITシステムを導入しなければなりません。
しかし、ポイント施策担当者のなかには、「ポイントシステムという単語を見聞きした経験はあるけれども、どのような仕組みなのかよくわからない」とお悩みの方もいるでしょう。
そこで、本記事では、ポイントシステムの仕組みや、導入する目的・メリット、注意点、システムを選定する際に比較するべき点をご紹介します。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 ポイントサービスを実施するためには、「ポイントシステム」が必要
✓ポイント2 コストはかかるものの、導入すればさまざまなメリットを享受できる
✓ポイント3 導入実績や外部システムとの連携が可能かを確認したうえで選定を!
目次[非表示]
- 1.ポイントシステムの仕組み
- 1.1.ポイントシステムとは
- 1.2.ポイント還元の仕組み
- 1.3.ポイント資金は加盟店の負担
- 1.4.加盟店の原資負担率
- 2.店舗がポイントシステムを導入する主な目的は4つ
- 2.1.1.顧客情報の分析に活用できる
- 2.2.2.間接的に来店プロモーションになる
- 2.3.3.顧客の単価アップにつながる
- 2.4.4.優良顧客の獲得につながる
- 3.ポイントシステムの導入で注意すべき3つのポイント
- 3.1.1.ポイントシステムの種類を選ぶ
- 3.2.2.ポイント付与のタイミングを検討する
- 3.3.3.スタッフの業務量増加に注意する
- 4.ポイントシステム選びで比較すべき5つの項目
- 4.1.1.ポイントの種類
- 4.2.2.機能の充実性
- 4.3.3.導入実績
- 4.4.4.外部システムとの連携
- 4.5.5.サポート体制
- 5.ポイントシステムの仕組みでよくある3つの質問
- 6.【まとめ】
- 7.おすすめの資料はこちら
ポイントシステムの仕組み
まず「ポイントシステムとは、どのようなものなのか」をご紹介したうえで、「ポイント還元の仕組み」や「ポイント資金が加盟店の負担になること」「加盟店の原資負担率」について順番に解説していきます。
ポイントシステムとは
ポイントシステムとは、ポイントサービスを提供するために必要となるITシステムです。
「ユーザーが何らかのアクション(来店、Webサイト訪問、資料請求、予約、商品・サービスの購入など)をした場合に、ポイントを付与する」「ユーザーがポイントを使用した場合に、ポイント残高を減算する」「有効期限が到来した場合に、ポイントを利用できなくする」といった機能があります。
なお、民間企業だけではなく、国や地方自治体、学校なども、ポイントサービスを提供するために、ポイントシステムを導入する時代になりました。
ポイント還元の仕組み
ポイント還元とは、会員用のカードやアプリを提示して商品・サービスを購入した消費者に対して、「購入金額の数パーセント分」をポイントとして付与(還元)する仕組みです。決済時にすぐ付与するケースのほか、後日まとめて付与するケースもあります。
なお、ポイントは、特定の企業・店舗でのみ利用できる「独自ポイント」と、さまざまな企業・店舗で利用できる「共通ポイント」(dポイント、楽天ポイントなど)の2種類に大別されることを把握しておきましょう。
「ポイント還元率や有効期限などを、自社・自店舗で自由に設定したい」という場合は独自ポイントを、「利便性を向上し、顧客満足度をアップさせたい」「他企業・他店舗の顧客を、自社・自店舗に取り込みたい」という場合は共通ポイントを導入することをおすすめします。
ポイント資金は加盟店の負担
付与するポイントの元手となる資金(原資)は、ポイントサービスを実施する企業・店舗が負担します。
基本的に「共通ポイント」の場合、「加盟店がポイントサービス提供事業者に支払う手数料」で原資がまかなわれています。なお、加盟店を獲得するために、ポイントサービス提供事業者側が原資を負担するケースもあります。
加盟店の原資負担率
加盟店の原資負担率は、ポイントサービス提供事業者ごとに異なるので、各業者の公式サイトで詳細をご確認ください。
ちなみに、大手ECモールでは、一般的に「1%程度」の原資負担率です。例えば、楽天市場の場合、税込10,000円の商品を販売すると、通常1%分に相当する「100円」がポイント原資として徴収されます。
なお、Yahoo!ショッピングの場合、ストアポイント原資充当分として「税抜販売価格の1%分」の負担のほか、キャンペーン原資充当分として「税込販売価格の1.5%分」の負担が必須とされています。
店舗がポイントシステムを導入する主な目的は4つ
ポイントシステム導入の主な目的・メリットは、「顧客情報の分析に活用できる」「間接的に来店プロモーションになる」「顧客の単価アップにつながる」「優良顧客の獲得につながる」の4つです。以下、それぞれについて詳しく説明します。
1.顧客情報の分析に活用できる
ポイントサービスを提供するにあたって、企業・店舗側は、ユーザーに対して「会員登録」を求めることになります。その際に、ユーザーの氏名や年齢、性別、住所、電話番号といった情報を取得することが可能です。
単に「氏名、年齢、性別、住所を教えてほしい」と要求しても、顧客は警戒し、教えてくれないケースが多いかもしれません。しかし、「会員登録すれば、ショッピングなどの際にポイントを付与する」というメリットを提示すれば、情報を提供してくれる可能性が高くなります。
企業・店舗側は、会員登録の際に提供された情報を分析することで、顧客の属性(年齢、性別、居住地など)に合わせて、きめ細やかなマーケティングを展開できるようになるでしょう。
2.間接的に来店プロモーションになる
来店を促すプロモーション手法には、直接的なものと、間接的なものがあります。チラシやダイレクトメール、テレビCM、Web広告などで、「〇月〇日から〇月〇日まで、〇〇を値引き」といったセール情報を周知し、直接的に集客するのも一つの手法です。しかし、頻繁に値引きセールを実施していると、店舗側の利益が少なくなってしまいます。
ポイントサービスを導入すれば、特にセールなどを実施しなくても、「ポイントが貯まるから、あの店舗で購入しよう」という気持ちを顧客が持ちやすくなり、「間接的な来店プロモーション」としての効果が得られるでしょう。
もちろん顧客が貯まったポイントを使用して商品を購入すれば、店舗側としては値引きと同様の負担が生じますが、「ポイントを使用しないまま有効期限が到来する」というケースもあるため、トータルではポイント付与のほうが値引きよりも負担が少なくなります。
3.顧客の単価アップにつながる
「購入金額が1万円以上の場合、還元率が〇%に上昇」「購入金額が~~円を超えたら、ボーナスポイントを付与」といった施策を実施すれば、顧客の単価アップにつながります。
購入金額にかかわらず同じ還元率の場合(ボーナスポイントが付与されない場合)、予算の範囲内でしか買い物をしない顧客が大多数です。しかし、上記施策を実施すれば、「ポイント還元率を上昇させるために(ボーナスポイントを獲得するために)、あと~~円分買い足そう」と考えるようになるでしょう。
4.優良顧客の獲得につながる
ポイントサービスを実施していない状態では、どの顧客が常連客で、どの顧客が一見客なのかを見分けるのは容易なことではありません。
しかし、ポイントサービスを実施すれば、会計の際に会員カードやアプリが提示されることから、「いつも利用してくれる顧客に対して割引クーポンを配布する」といった施策を講じやすくなり、優良顧客(ロイヤルカスタマー)の育成につながります。
獲得したポイント数に応じてランクやステージが上がっていく「ランク制度・ステージ制度」を導入し、ランク・ステージが高い顧客に対して特別なおもてなし(「限定イベントへの招待」「人気グッズの先行予約をする権利の付与」など)をして、満足度を高めることもご検討ください。
ポイントシステムの導入で注意すべき3つのポイント
以下、ポイントシステムの導入に関して注意するべきポイントを3つご紹介します。
1.ポイントシステムの種類を選ぶ
まず「どのようなポイントを提供するか」を決め、それに対応したポイントシステムを選定しましょう。上述したように、ポイントは、「独自ポイント」と「共通ポイント」の2種類に大別されます。
共通ポイント(dポイントや楽天ポイントなど)の場合、自由に還元率や有効期限などを設定できない代わりに、自社でポイント数などの管理をする必要がないため、導入するITシステムも簡素なもので済むでしょう。
独自ポイントの場合、自由に還元率や有効期限などを設定できますが、すべての情報を自社・自店舗で管理しなけれなばりません。そのため、複雑な処理に対応できるITシステムを用意する必要があります。
2.ポイント付与のタイミングを検討する
「どのタイミングでポイントを付与するか」も、ポイントサービスを提供するうえで重要な要素です。
例えば、ECサイトの場合、「注文時にポイントを付与する」というパターンのほかに、「出荷時にポイントを付与する」というパターンも選べます。
前者の場合、注文操作を実行したタイミングでポイントを獲得できるため、顧客が「ポイントを獲得した実感」を得やすくなるでしょう。しかし、「注文がキャンセルされた」「返品された」といった場合に、ポイントを取り消す作業が発生し、手間がかかります。後者の場合、キャンセルや返品の際のポイント取り消しの手間がかかりませんが、顧客が「ポイントを獲得した」という実感をすぐに得られません。
まずは前者のパターンを採用したうえで、あまりにもキャンセルや返品が多く、手間がかかるようであれば後者のパターンに切り替えてはいかがでしょうか。
また、商品購入時以外に、「顧客の誕生月」などのタイミングで特別ポイントを付与する施策もご検討ください。
3.スタッフの業務量増加に注意する
ポイントシステムは、「導入したら、それで終わり」というものではありません。スタッフがシステムの操作に習熟し、エラーやイレギュラーな事象が発生しても対応できるようになる必要があり、業務量が増加することにご注意ください。
しかし、システムの操作やエラーへの対応などに追われ、本来の業務(接客など)に支障をきたす事態は避けたいものです。「マニュアル・ルールの整備」や「オペレーションのトレーニング」によって作業を効率化し、可能な限り業務量を圧縮しましょう。
ポイントシステム選びで比較すべき5つの項目
ここからは、ポイントシステムを選ぶ際に比較しておきたい項目を5つご紹介します。
1.ポイントの種類
まず「システムが対応しているポイントの種類」をチェックしましょう。独自ポイントを導入するのであれば、顧客の氏名・住所・電話番号のデータベースへの登録や、付与・利用に伴うポイント残高の加算・減算、有効期限などを管理できるシステムを選ぶ必要があります。
また「アプリのみに対応しているのか」「物理的な会員カードにも対応しているのか」を確認することも重要です。高齢者を中心にスマートフォンを保有していない方も一定数存在するので、物理的なカードにも対応しているシステムを選択すれば、より多くの顧客を獲得できるでしょう。
2.機能の充実性
「どのような機能が搭載されているのか」を確認することも、ポイントシステムを選ぶうえで欠かせません。
単に「商品・サービスを購入した際にポイントを付与する」というだけではなく、「来店・ログイン時にポイントを付与する」「顧客の誕生月にバースデーポイントを付与する」「ランク・ステージが上がった際に、ポイントを付与する」など、多彩な機能があるシステムを選べば、顧客との接点を強化するのに役立つでしょう。
また、有効期限の設定方法には、商品を購入するたびに自動的に延長される「自動延長型」のほかに、年度ごとに失効する「年度失効型」がありますが、いずれのパターンにも対応しているシステムを選ぶほうが、施策の自由度が高くなります。
そのほか、「RFM分析やデシル分析などが可能かどうか」や、「会員数推移や発行ポイント数を集計するレポート機能」「メルマガ機能」が備わっているかどうかも事前にチェックしておきましょう。
3.導入実績
これまでの導入実績もご確認ください。業者の公式サイト上に掲載されていない場合(公式サイト上で発見できなかった場合)は、電話や問い合わせフォームで質問しましょう。
同じ業界・業種において、多数の企業・店舗が導入していれば、自社・自店舗でもスムーズに導入でき、運用開始後のトラブル発生頻度も低くなることが期待できます。導入実績が少ない場合は、運用開始後に予期せぬトラブルが発生する可能性もあるのでご注意ください。
4.外部システムとの連携
「外部システムとの連携が可能かどうか」をチェックすることも重要です。すでにCRMシステムやPOSシステム、ECサイトの管理システムなどを導入している場合は、連携できるポイントシステムを導入することをおすすめします。
また、独自ポイントを提供する場合、「ポイント交換システムと連携できるかどうか」もご確認ください。ポイント交換が可能な仕組みを用意しておくほうが、ユーザーの利便性が高くなり、集客しやすくなるでしょう。
なお、ジー・プランのポイント交換ソリューションを導入することも、選択肢のひとつとして検討してはいかがでしょうか。例えば、「PCT LITE」なら、ユーザーが、デジタルコードを利用して独自ポイントを手軽に共通ポイントに交換することが可能になります。詳細について知りたい場合は、以下のページをご覧ください。
PCT LITE
https://www.g-plan.net/service/solution/pctlite
5.サポート体制
システムには、トラブルがつきものです。突発的にエラー・不具合が発生することがあるので、「サポート体制が充実しているかどうか」を確認しておく必要があります。小売店など、土日・祝日も営業してる業種・業態の場合、問い合わせへの対応が「平日のみ」となっている業者は避けるほうが良いでしょう。
また、オンプレミス型(自社・自店舗の構内に機器を設置するタイプ)のポイントシステムの場合、東京にしか拠点がない業者を選んでしまうと、地方の店舗でトラブルが発生して修理を依頼した際に、訪問までに日数がかかる可能性があるのでご注意ください。
ポイントシステムの仕組みでよくある3つの質問
以下、ポイントシステムの仕組みに関する「よくある質問」、および、それに対する「回答」をご紹介します。
質問①ポイントシステムの導入にかかる費用は?
ポイントシステムに必要な費用は、「導入時にかかる費用」と「運用開始後に継続的にかかるランニングコスト」に大別されます。
導入時の費用は「1からスクラッチ開発するのか」「クラウド型サービスを利用するのか」によって大きく異なり、スクラッチ開発の場合、数千万円単位で費用がかかるケースもあるのでご注意ください。
クラウド型サービスの場合、ベンダーや規模(顧客や店舗の数)によって異なるものの、おおよそ数万円から数十万円程度が相場です。初期費用を抑えたいのであれば、クラウド型のサービスを利用するほうが良いでしょう。
運用開始後のランニングコストとしては、「ポイント還元のための費用(原資)」がかかります。クラウド型サービスの場合は、数千円から数万円程度の「月額利用料」のほか、店舗数に応じた追加費用がかかることもあるので、事前に各業者の公式サイトで詳細を確認しておきましょう。
質問②ポイントシステムの種類は?
ポイントシステムは、「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類に大別されます。オンプレミス型とは「自社の構内にサーバーなどの機器を設置し、システムを管理・運用するタイプ」を指し、クラウド型とは「クラウドサーバー上で提供されるシステムを、インターネット経由で利用するタイプ」を指します。
オンプレミス型の場合、「カスタマイズしやすい」という利点があるものの、初期費用が高く、保守・運用コストも高額になるのでご注意ください。クラウド型なら、カスタマイズの幅は広くない一方で、初期費用や保守・運用コストを抑えることが可能です。「運用に手間をかけたくない」「コストを抑えたい」という場合は、クラウド型を選ぶほうが良いでしょう。
質問③ポイントシステム導入のデメリットはありますか?
ポイントシステム導入のデメリットとしては、まずコストがかかることが挙げられます。導入コストはもちろん、多くの場合運用コストがかかり、人員も必要になります。ポイントを利用した支払いが発生することで、会計処理も煩雑になります。それらを上回るメリットがあるかどうか、精査をする必要があるでしょう。
また、顧客が貯めたポイントを使用することで、実質的な値引きが適用されることになることも留意しておきましょう。
【まとめ】
ポイントサービスを提供するためには、「ポイントシステム」と呼ばれるITシステムが必要です。初期費用やランニングコストがかかりますが、「顧客情報の分析に活用できる」「間接的に来店プロモーションになる」「顧客の単価アップにつながる」「優良顧客の獲得につながる」といったメリットを享受できるので、ぜひ導入をご検討ください。
なお、独自ポイントを提供するのであれば、「他社のポイント(共通ポイントなど)と交換できる仕組み」も用意することをおすすめします。例えば、ジー・プランのポイント交換ソリューション「PCT LITE」なら、ポイント交換事業者との交渉・契約・精算・システム連携が不要なため、手軽に導入することができます。
「PCT LITE」の導入で、ユーザーが独自ポイントを共通ポイントに交換することが可能になるため、ユーザーにとっての利便性が高まり、集客しやすくなるでしょう。
おすすめの資料はこちら
関連記事