
【初心者向け】クチコミマーケティングとは?成功に導くためのポイントやメリット、デメリットを徹底解説!
クチコミマーケティングとは、消費者自身が発信する自社の商品・サービスに関する情報を活用することで、自社商品の認知度向上や売上増につなげるマーケティング手法を指します。
SNSの普及などによりクチコミの影響力が増大するいま、企業はクチコミを上手に活用することで、自社商品・サービスの認知度向上や販売促進、新規顧客獲得につなげることが可能となりました。
そのため、特に一般消費者を対象としたBtoC事業を展開する企業においては、意識的にクチコミが発生しやすい状況を作り出し、好意的なクチコミを増やすことが、マーケティング上非常に有効な施策のひとつであると言えるでしょう。
一方で、ネガティブなクチコミが増えると、売上の低下のみならず企業のブランドイメージを損なうリスクも強まっています。取り扱いジャンルによっては、消費者のクチコミといえど薬機法の規制対象となることも念頭におかなくてはなりません。
また、2023年10月1日より施行される「ステマ規制」についても、十分な理解と対策が必要です。
本記事では、こうした点を踏まえながら、クチコミマーケティングを成功に導くためのコツや注意すべき点を広く解説しています。
<この記事のポイント>
✓ポイント1 SNSが普及したいま、クチコミマーケティングは非常に有効性の高いマーケティング施策のひとつ
✓ポイント2 好意的なクチコミを増やし販促につなげるためには、企業側の働きかけと環境設定が必要
✓ポイント3 炎上及び薬機法対策、ステマ規制等を受けたクチコミマーケティング手法の変化に注意
目次[非表示]
- 1.クチコミマーケティングとは?
- 2.クチコミマーケティングが重要とされる背景
- 3.クチコミマーケティングに取り組む3つのメリット
- 3.1.1.費用対効果が高い
- 3.2.2.認知度を広げやすい
- 3.3.3.信頼を獲得できる
- 4.クチコミマーケティングに取り組む2つのデメリット
- 5.クチコミマーケティングを成功に導く3つのポイント
- 6.クチコミマーケティングに取り組む際の3つの注意点
- 6.1.1.炎上のリスクがある
- 6.2.2.工数がかかる
- 6.3.3.薬機法に抵触する可能性もある
- 7.クチコミを2次利用する3つの方法
- 7.1.1.直接投稿者に連絡して許諾を得る
- 7.2.2.オリジナルハッシュタグを設定する
- 7.3.3.モニターサイトを活用する
- 8.クチコミマーケティングでよくある3つの質問
- 8.1.質問①「クチコミマーケティング」の言い換えは?
- 8.2.質問②ステマ規制とは何ですか?
- 8.3.質問③クチコミとレビューの違いは?
- 9.【まとめ】
- 10.おすすめの資料はこちら
クチコミマーケティングとは?
消費者が商品・サービスを選ぶときは、内容や価格だけでなく、他者によるクチコミが決定打となることが少なくありません。実際に利用、購入した人のリアルな感想や体験談は、提供側から一方的に打ち出されるプロモーションとは異なり、公平かつ中立であると判断されやすいからです。
また、ネットで話題になることで、いままで認知していなかった商品・サービスの情報に触れ、興味を持ったり購買意欲を刺激されたりする消費者も増加するでしょう。クチコミから流行が生まれることも、いまでは決して珍しい現象ではありません。
そうした点に注目し、消費者自身が発信する自社の商品・サービスに関するクチコミを積極的に活用することで、認知度向上や売上増につなげるマーケティング手法を「クチコミマーケティング」と呼びます。
クチコミマーケティングの手法には、大きく分けて「バズマーケティング」と「バイラルマーケティング」の2つがあります。
「バズマーケティング」とは、短期間で一気にクチコミを増大させ、意図的に「バズらせる」手法です。SNSでの大規模キャンペーンや、影響力のあるインフルエンサーを起用しての施策などが効果的です。
バズマーケティングが成功すれば、その瞬間的な爆発力によって情報の広範囲への拡散が可能となるため、認知度アップや新規顧客獲得につながるでしょう。ただし、一過性のもので終わらないよう、顧客との関係性の継続に配慮が必要です。
「バイラルマーケティング」もクチコミを活用する点では同様ですが、短期ベースのバズマーケティングとは異なり、こちらは中長期的なクチコミ効果を狙ったものです。
自社の商品やサービスに満足した顧客による好意的なクチコミが徐々に増えていけば、自然とブランドイメージ向上や新規顧客獲得につながります。
ここでは商品・サービス自体の品質はもちろん、顧客対応などの企業姿勢が大きく影響することになるため、開発努力に加え顧客満足度の向上施策も同時に実行する必要があるでしょう。
クチコミは本来、自然発生的に広がっていくものですが、ただ見守るだけでは効果的なマーケティング施策につなげることはできません。好意的なクチコミが増える流れを作り、施策に活かすためには、事業者の環境設定と適切な働きかけも必要なのです。
クチコミマーケティングが重要とされる背景
以前の広報宣伝戦略は、例えばタレントを起用してのテレビCM、雑誌広告など、主にマスメディアを通じた方法が一般的でした。
クチコミの効果自体は同様でも、従来は家族や友人、知人の間での情報交換に留まり、それ以上拡散することは滅多になかったのです。
しかしインターネットやスマホが普及した現在、誰でも気軽に情報発信可能なSNSやブログ、クチコミサイトなどを通じて、クチコミ情報量が飛躍的に増大。一般消費者による情報拡散力は、時としてマスメディアをも凌駕します。
消費者が商品・サービスを選ぶ際に、まずネットでクチコミをチェックするという行動は、もはや定着しているといってもよいでしょう。
さらに前述した通り、消費者は商品・サービス提供企業による一方的な情報発信よりも、一般消費者のクチコミの方を信頼する傾向があるため、単なる情報量だけでなく、その影響力、訴求力は非常に大きくなっているのです。
ネットで話題になったことをきっかけに大ヒット商品が生まれることがある一方で、悪評が流れれば、売上の低下だけでなく企業のブランドイメージにも傷がつきかねません。
こうした状況を背景として、現代におけるクチコミマーケティングは、より重要視されるようになっています。
クチコミマーケティングに取り組む3つのメリット
ここからは、企業がクチコミマーケティングに取り組んだ際の具体的なメリットを、3項目に分けてご紹介しましょう。
1.費用対効果が高い
まず言えることは、クチコミマーケティングは費用対効果が非常に高いということです。
どのようなメディアを利用した場合でも、一般的な広告宣伝には相応の時間と多額の費用がかかりますが、必ずしもそうしたコストに見合った結果が得られるとは限りません。
しかしクチコミマーケティングを上手に活用することができれば、一般消費者が自ら次々と情報を発信してくれるため、特にコストをかけることなく、雪だるま式に好意的な情報が拡散されていきます。
こうした流れを作るために留意すべき点については後述しますが、最初の設定と対応さえ誤らなければ、企業は最低限のコストで広告宣伝と同様の効果を得ることができるのです。
2.認知度を広げやすい
テレビCMであればテレビ視聴者に、新聞広告であれば新聞購読者にリーチすることが可能です。媒体の信頼度もあり、一定の宣伝効果は見込めるでしょう。
しかし、チャネルが限定されている以上、それ以外の消費者にアプローチすることは困難であることも事実です。
その点、クチコミは個人ブログ、各種SNS、クチコミサイトなど、インターネットを中心とした多種多様なルートで拡散されます。
リアル社会とは異なり、ブログやSNSでは、フォロー・フォロワーといった機能を通じて関係性の構築、拡大が容易なため、性別、年代、趣味嗜好といった属性要件の枠を超えた情報伝達がなされることになります。
その結果、従来のマーケティングでは届かなかった層へのアプローチが可能となり、潜在ニーズの発掘及び自社の商品・サービスの認知度向上につながるでしょう。
3.信頼を獲得できる
企業によるプロモーションは商品やサービスを売り込むためのものですから、ほとんどの場合、長所や美点にフォーカスして訴求します。消費者からすれば、欠点が分からないため公平な判断が難しいと感じることもしばしばあるでしょう。
クチコミは、実際に商品・サービスを利用した一般消費者が自発的に発信する個人の感想ですから、中立的かつ正直であるとみなされやすいうえ、なかには欠点についての言及や、批判的、否定的な意見も混在することになります。
それが逆に信頼度の高さにつながり、長所についても受け入れてもらいやすくなるのです。
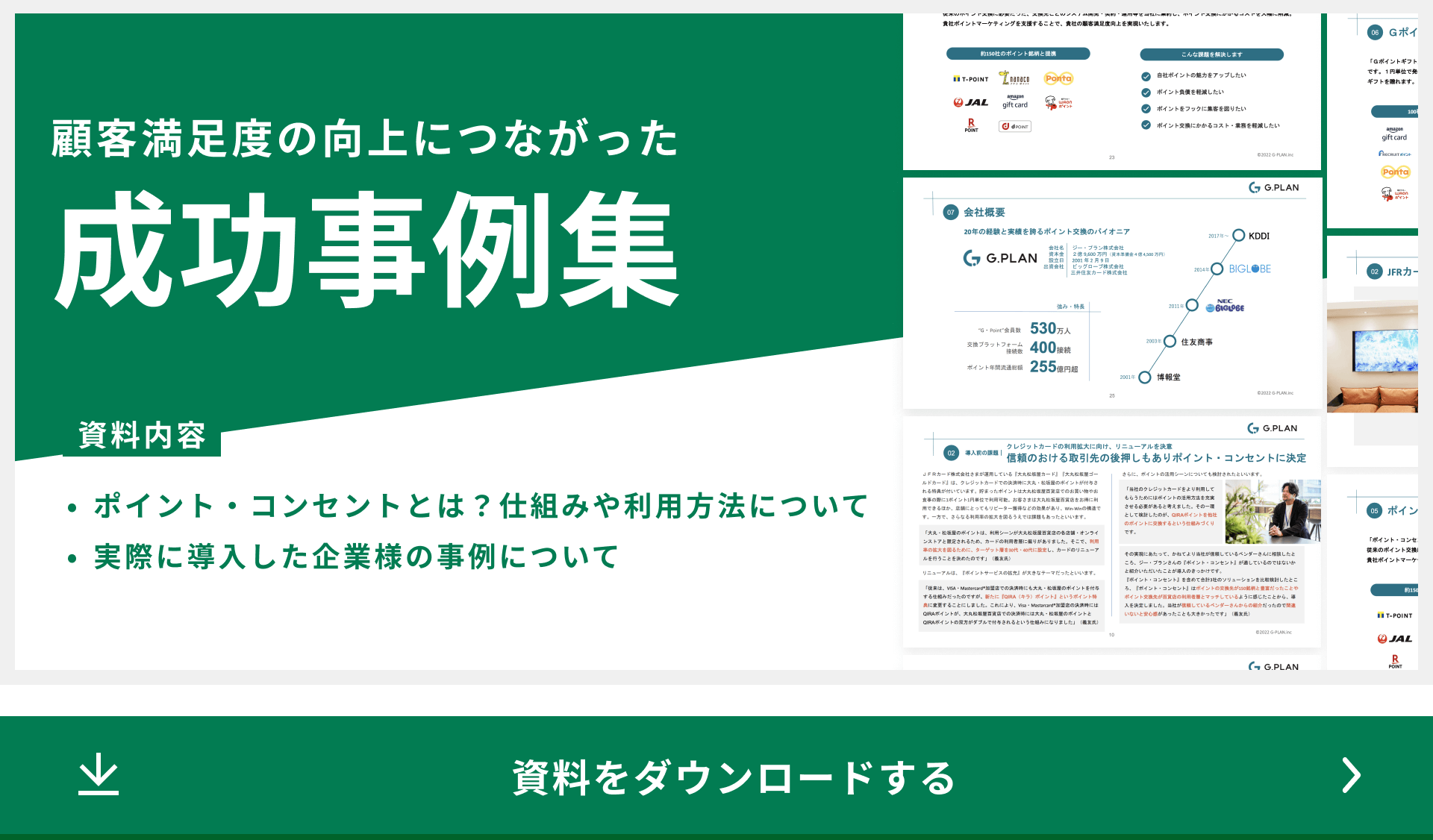
クチコミマーケティングに取り組む2つのデメリット
クチコミはあくまでも一般消費者が発信するものです。それゆえに信頼度が高いとみなされやすいことは前述のとおりですが、必ずしも利点ばかりとは限りません。
ここでは、クチコミマーケティングにおける2つの大きなデメリットをご紹介します。
1.コントロールができない
クチコミマーケティングを行う企業側は、さまざまな施策を通じてクチコミが増えるよう働きかけることになります。
しかし、クチコミ自体はあくまでも各消費者の自由意思で発信されるため、内容をコントロールすることはできません。場合によっては不都合な情報が拡散されてしまうこともあるでしょう。
ただし、このとき企業に都合のよい情報を書くよう強制したり、意に沿わないクチコミを削除したりすることは、多くの場合、逆効果となります。
後述しますが、企業側の依頼に基づいていることを隠して好意的なレビューを発信する「ステルスマーケティング」であるとみなされると、消費者からの強い反発を受けることになりかねないため注意しましょう。
2.ブランドイメージの低下につながるおそれがある
前項で触れた通り、クチコミには否定的なものも含まれます。
利用・体験に基づく適切な指摘であればまだしも、企業やその商品・サービスに反感を抱く層からの、悪意あるクチコミが発生する可能性もあることを念頭においてください。これらを放置するとブランドイメージの低下にもつながりかねないため、適切な対応が必要です。
ネガティブなクチコミに対しても真摯に対応することで、誠実な企業姿勢が評価され、かえって好感度が上がることは少なくありません。接客等に対する不満がベースにある場合は、沈静化させるだけでなく、抜本的な改善策を講じることも重要です。
こうした悪いクチコミはいつ発生、拡散するか予測できないため、対応策を事前にマニュアルとしてまとめておくとよいでしょう。
クチコミマーケティングを成功に導く3つのポイント
簡単にクチコミと言っても、手間暇かけてクチコミを書くのは、それなりにハードルが高いものです。
その後押しをして、さらに見た人の気持ちも動かすためには、やはりある程度の仕組みづくりや働きかけが必要になるでしょう。
ここでは、クチコミマーケティングを成功に導くためのポイントを紹介します。
1.明確なマーケティングコンセプトを設計する
まず商品・サービスを訴求する対象を絞り込み、マーケティングにおける企画コンセプトを明確にしておきましょう。
誰に、何を、どのように訴求していくのかを定め、その上でターゲット層に届きやすい企画を立案することで、クチコミを書こうという意欲が高まりやすくなります。
例えば若年層が興味を惹かれ話題にしたくなる企画と、子育て層の需要を喚起し情報共有を促す企画とでは、方向性が大きく異なることはお分かりいただけるのではないでしょうか。
企画のスタンスが不明瞭な状態ではターゲットに刺さりにくく、結果としてあまり拡散されないまま終わってしまうことになりかねません。
場合によっては、商品・サービスの本質的な価値はどこにあるのかをじっくり検討し直した上で、マーケティング戦略を練り直すことも大切です。
2.ユーザーがクチコミを拡散しやすい仕組みを作る
商品・サービスがいかに高品質でも、それだけでクチコミが増えるわけではありません。消費活動は、自身が充足したらその時点で一旦終了するため、クチコミ投稿という発信行為に導くにはそれなりの動機付けが必要です。
ここで、企業側の働きかけや、クチコミを投稿したくなるような仕組みづくりが重要となってきます。
一般的なものとしては、次回利用時のサービス券配布やプレゼント進呈など、クチコミ投稿に対して特典を設けることで消費者のモチベーションを上げるという方法があります。
とはいえ、自社で物理的な商品進呈を行うとなれば、商品選定や発送業務等による作業負担の増大は避けられません。電子ギフトを利用する、ポイントサービスを展開している企業であればポイントを付与するなどの方法が、もっとも簡単でユーザーのメリット感につなげやすいでしょう。
例えば、ジー・プランが提供する「Gポイントギフト」は、電子マネーや共通ポイント、航空マイル、現金など、100種類以上のラインナップへ交換できる電子ギフトサービスです。1円単位で発行できるうえ、低コストで利用可能なので、事業者にとって非常に利便性の高いサービスのひとつと言えるでしょう。
こうしたソリューションを活用することで、自社の負担は最低限に抑えつつ、ユーザーメリットを最大限に引き上げることが可能となります。
また、クチコミに対してオフィシャルアカウントで「いいね」をしたりコメントをつけたりして直接コミュニケーションを取り、親近感を醸成することも有効です。
商品・サービスの内容や目指す方向性に応じて、どういった拡散方法が望ましいか、十分に検討したうえで施策を打ち出しましょう。
3.拡散だけではなく、集客を目的とした設計をする
クチコミマーケティングを展開する際は、集客と拡散を混同しないよう注意が必要です。
もちろん情報の拡散は認知度向上につながる重要な要素ですが、それはあくまでも手段、通過点に過ぎず、最終目的は集客であるということを忘れてはなりません。商品・サービスを利用したいと思わせることができなければ、販促プロモーションとして成功したとは言えないからです。
そのため、情報を受け取った消費者が、それをもとにどう動くかを想定し、確実に集客するための導線を設定することが重要になってきます。
サービス紹介サイトに容易にアクセスできるよう工夫を凝らすと同時に、新規入会キャンペーンやサンプル配布、資料ダウンロードなど、初見消費者の行動を後押しするような仕組み作りを検討しましょう。
ポイントサービスを活用する場合は、新規登録でポイント付与といった施策が考えられます。消費者が情報を目にしたタイミングでこうしたキャンペーンが実施されていれば、新規会員の獲得に大きな効果が見込めるでしょう。
クチコミマーケティングに取り組む際の3つの注意点
うまく活用できれば非常に効果の高いクチコミマーケティングですが、拡散力が高い分、間違った運用をしてしまった場合のダメージも深刻です。
リスクを避けるため、特に注意するべき3点を紹介しましょう。
1.炎上のリスクがある
前述の通り、企業側がクチコミの内容をコントロールすることはできません。そのため、内容次第では「炎上」につながるリスクが生じます。
この場合、投稿した本人に悪気はなくとも、他のユーザーから問題があるとみなされて炎上する、といったケースが少なくありません。特定のクチコミを問題視するコメントが出始めたら、大きな騒ぎになる前に手を打つ必要があるでしょう。
また、後述しますが、実質的に企業の広告であるにも関わらず、それを隠し自主的なレビューと偽って投稿するといった「ステルスマーケティング」は、一般消費者を欺く行為と受け止められるため、発覚すると大きな反発を招きかねません。
影響力のあるインフルエンサーに依頼して、自社商品・サービスを紹介してもらう場合は、必ず「広告」「PR」などを表示し、消費者が広告とクチコミを混同しないよう配慮が必要です。
2023年10月からは、ステルスマーケティング規制(通称「ステマ規制」)の運用が開始されます。こちらについても後段で詳しく解説するので、参考にしてください。
2.工数がかかる
本稿で度々触れている通り、クチコミマーケティングは一般消費者の発信する情報を活用するため、炎上やネガティブなクチコミ、薬機法など、さまざまなリスク要因をはらんでいます。
そのため、細やかな管理が求められることになり、一般的な広告出稿とは異なる手間が発生しがちです。
さらに、個別のクチコミのチェックや返信、体験ユーザーの選定、インフルエンサーとのコミュニケーションなど、マンパワーが要求されるシーンも増えるでしょう。
通常の広告宣伝におけるコストは削減できますが、それ以外の面で新たな業務や工程が発生する可能性を念頭に置いておく必要があります。
3.薬機法に抵触する可能性もある
医薬品や化粧品を扱う事業者にとって、特に注意しなくてはならないのが薬機法(旧:薬事法)です。
薬機法は、過大広告や誤認情報の拡散を防止し、消費者を保護することを目的とした法律です。WEB広告のトラブル急増等を受けて2021年に改正が行われ、より規制が厳しくなりました。
企業が行う広告宣伝では、専門部署や知識のあるスタッフによるチェックが行われることが多く、問題が生じることは比較的少ないものの、一般消費者によるクチコミ投稿の場合、そうした知識のないまま商品レビューを行い、結果として薬機法に抵触してしまうケースが十分に考えられます。
消費者によるクチコミは同法の規制対象外と考えがちですが、マーケティングの一環としてインフルエンサーに商品・サービスの紹介を依頼した場合、インフルエンサーが発信する情報は事業者の責任範囲となります。
条件によっては、一般消費者の自発的なクチコミであっても薬機法違反とみなされ処罰対象になることがあるため、以下のジャンルに当てはまる事業者は、特に慎重な姿勢が要求されるでしょう。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品
サプリメントや健康食品は、それ自体は薬機法の対象外ですが、訴求方法によっては問題となりやすいジャンルですから、くれぐれも注意してください。
クチコミを2次利用する3つの方法
好意的なクチコミは、商品やサービスの魅力を消費者目線でストレートにアピールしてくれるため、企業側の宣伝に利用したいと考えることもあるでしょう。
ただし、一般消費者によるクチコミを自社のWEBサイトやSNS等に転載する場合は、投稿者本人に許諾を得る必要があります。
ここでは、投稿者から転載許諾を得るための方法を3つご紹介します。
1.直接投稿者に連絡して許諾を得る
もっとも確実かつシンプルな方法が、DMなどを利用して該当クチコミをした本人に直接連絡を取り、許諾を得ることです。
このとき転載する媒体や内容、利用目的、掲載形態などについてもきちんと伝えておくと、その後のトラブル回避策としても有効です。
ただし、個別にコンタクトを取る以上、時間と手間がかかることは否めません。特に2次利用したいクチコミが多数ある場合、それだけ負担も増大する点がネックと言えるでしょう。
2.オリジナルハッシュタグを設定する
事前に、クチコミを転載する可能性があることを告知し、許諾を得ておく方法です。
指定したハッシュタグを付けて投稿すると公式アカウントで紹介する旨を告知し、そのうえで投稿を呼びかけるといった方法が、よく用いられています。
こうすることで、指定ハッシュタグの付いたコメントは公式アカウント転載許諾を得たという意味になりますから、後日改めて連絡を取ることなく二次利用が可能です。
とはいえ、事前に告知した以外の用途は許諾範囲外となるため、他メディアでの企業広告に使用するなどの場合は、改めて使用目的に応じた許諾を取り直す必要がある点にご注意ください。
3.モニターサイトを活用する
ひとくちにモニター調査と言ってもさまざまな手法がありますが、ここでは消費者に自社の商品やサービスを利用してもらい、その感想やアンケート回答を回収する形式のものを想定します。
モニターサイトでは、こうしたモニター案件を数多く取り扱っているため、企業側が依頼することで多数のモニターを募ることができます。
投稿を二次利用することが可能なモニターサイトを活用すれば、まとめて大量のクチコミを収集できるうえ、個別に許諾を得る工程は不要となり、効率的にクチコミマーケティングを展開することが可能です。
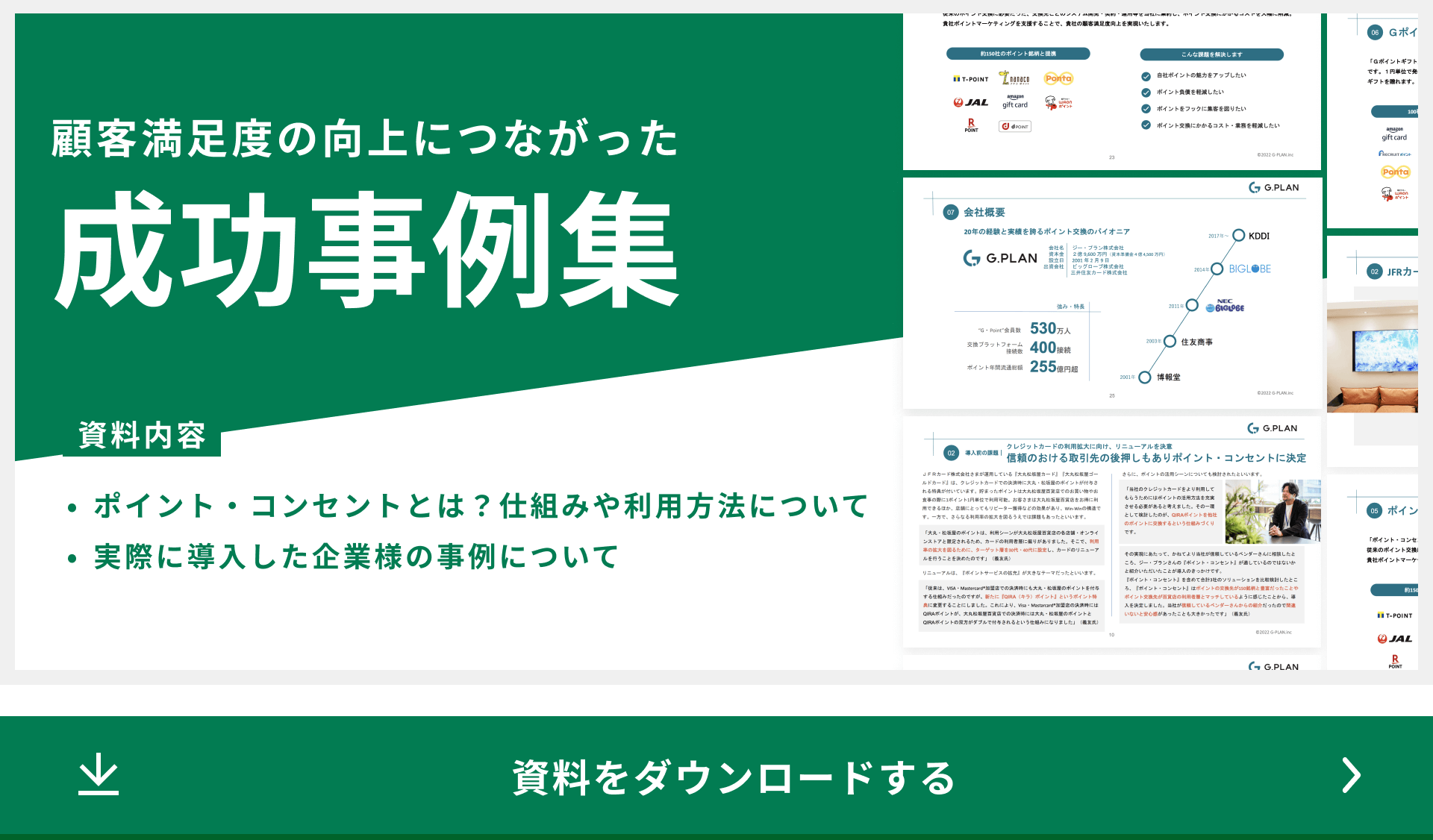
クチコミマーケティングでよくある3つの質問
質問①「クチコミマーケティング」の言い換えは?
クチコミマーケティングは、「口コミマーケティング」と表記されることも多々ありますが、もちろん意味は同じです。
一般的には、前述した「バズマーケティング」(短期間で一気にクチコミを増大させ、意図的にバズらせる手法)や、「バイラルマーケティング」(長いスパンで好意的なクチコミを増やし、ブランドイメージ向上や新規顧客獲得につなげる手法)が、クチコミマーケティングの同義として扱われることもあります。
ただし、解説した通り、正確に言えば「バズマーケティング」「バイラルマーケティング」はクチコミマーケティングにおける手法のひとつであり、定義する範囲は微妙に異なっています。
「ステルスマーケティング」も、クチコミを利用したマーケティング手法という点において同義とみなされるケースがありますが、こちらは消費者の反感を買いやすく、一括りに認識してしまうとリスクが生じる可能性もあるので注意が必要です。
施策を講じる際は、これらの内容を理解したうえで取り組むようにしましょう。
質問②ステマ規制とは何ですか?
先にも触れたように、一般的にステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に対し、企業が展開する広告、宣伝であることを隠した上で行う宣伝行為を指しています。
具体的には、社員など事業者側が一般消費者になりすまして特定の商品・サービスに好意的なクチコミ、レビューを行ったり、影響力のあるインフルエンサーに宣伝を依頼しておきながら、そのことを隠してインフルエンサー本人の感想であるように発信してもらったりする行為が当てはまります。
この場合、たとえ無報酬であったとしても、宣伝行為であることを隠している、という点でステマに該当する点に注意が必要です。
従来から、企業が行う広告表示の内容は景品表示法(正式には不当景品類及び不当表示防止法)で規制されていますが、ステマを完全に規制することはできず、一時期ステマが大きな社会問題として取り沙汰されました。
こうした背景のもと、消費者庁が規制の強化に乗り出し、2023年3月、景品表示法によって規制されている「不当表示」に、2023年10月1日よりステマを追加することを発表しました。これが「ステマ規制」と呼ばれるものです。
ステマ規制により、事業者がインフルエンサーを含むユーザーに好意的なクチコミを依頼した場合は「PR」「広告」と表示するなど、一般消費者から見て広告行為であることがはっきりとわかる状態でなければ違反となります。
社員など自社のスタッフ、もしくは広報宣伝を依頼した広告代理店などの委託先が、その関係性を明示せず、自社商品・サービスの販売促進につながるクチコミを発信した場合も、事業者が仕掛けたステマとみなされ規制対象となる可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。
さらに特筆すべきは、施行日である2023年10月1日以前の投稿であっても、ネットに現存する限り遡って行政処分の対象となる点です。過去のブログ、SNS等の投稿を洗い出しチェックしておくなどの対応が必要でしょう。
質問③クチコミとレビューの違いは?
「クチコミ(口コミ)」とは、噂や評判を人から人への口伝えで広めることを指した言葉です。「マスコミ(マスコミュニケーション)」になぞらえた造語「口コミュニケーション」が元となっています。
現在では、こうした噂や評判はネットを通じて広がることが多いため、伝達手段を問わず発信された個人の感想や噂、評判全般をクチコミと呼んでいます。
一方「レビュー」は英語の「review(批判、批評、よく調べる)」に由来したものです。言葉通り、実体験や事実関係に基づき批評的にまとめたものをレビューと呼びます。
クチコミが個人の主観に伝聞、噂などを加えた不確かな感想であるのに対し、レビューは人伝えではなく自身の実感や実体験をベースにした、比較的精度の高い情報を指していると言えるでしょう。
しかし、どちらも「感想」であるという点では同様のため、現在ではほぼ同義の言葉として使われることが多くなっています。
【まとめ】
SNSが普及したいま、クチコミの拡散速度は格段に上がりました。
その影響力は極めて甚大で、自社商品・サービスに関する好意的なクチコミは、販促マーケティング上、非常に強力な武器となります。
一般消費者にとって、同じ消費者である第三者から発信されたクチコミは、企業が発信する情報よりも公平で中立的と捉えられる傾向があり、かつリアルで参考になるとみなされやすいからです。
特に競合商品・サービスが多いジャンルであれば、情報の少ない店舗・企業のものよりも、好意的なクチコミの多い企業の商品を選ぶのは、消費者心理において自然な流れと言えるでしょう。
ただし、消費者からすれば、利用体験や使用感、感想を文章にまとめて投稿するという行為は、やはり少々ハードルが高いものです。いくら商品・サービスの品質が高くても、ただ静観しているだけで多数のクチコミを得ることは難しいため、企業側の適切な環境設定や働きかけが必要です。
例えば、クチコミ投稿に対して何らかのインセンティブを与えるといった施策が挙げられるでしょう。商品やサービス券の送付、次回利用時の割引といった方法もありますが、もっとも簡単かつ効果的なものが電子ギフトの利用です。
前述したジー・プランの「Gポイントギフト」であれば、初期費用や月額利用料、システム開発費用などは不要。電子ギフト利用金額に応じた料金のみとなるため、低コストで運用することが可能です。
すでにポイントサービスを導入している事業者の場合は、クチコミに対してポイント付与するなどの方法でも、手軽にクチコミ数を増やすことができるでしょう。
このとき、ポイント交換のソリューションが用意されていれば、消費者のメリット感はさらに強まります。クチコミ投稿によって得たポイントを、自分が貯めているポイントに加算することも可能となるためです。
例えばジー・プランの提供する「Gポイント交換」では、Gポイントを経由することで、独自ポイントを100種類以上のポイント銘柄に交換することが可能。また、約150社と提携した「ポイント・コンセント」なら、独自ポイントを複数の共通ポイントや大手ポイントなどに、ユーザー自身で直接交換可能です。
こうしたソリューションを上手に活用し、ユーザーのメリット感につなげながら好意的なクチコミを増やす施策を講じてみてはいかがでしょうか。
おすすめの資料はこちら
関連記事









