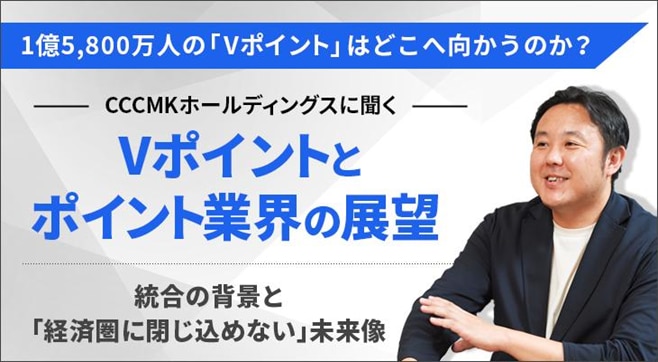
1億5,800万人の「Vポイント」はどこへ向かうのか? 統合の背景と「経済圏に閉じ込めない」未来像
CCCMKホールディングス株式会社
コンサルティング事業第1本部 本部長 鶴見聡史氏
2024年4月、新たな「Vポイント」が動き出しました。そのユーザー数は1億5,800万人。この巨大な共通ポイントサービスは、どのような考えのもとに生まれ、どこへ向かうのでしょうか。
サービスを運営するCCCMKホールディングス株式会社で、コンサルティング事業第1本部 本部長を務める鶴見聡史氏に直接話を聞きました。
<この記事のポイント>
- ポイント1 TポイントとSMBCグループのVポイントの統合で発行量が大幅に増加。利用範囲と利便性が向上
- ポイント2 購買データとキャッシュレスデータを統合することで、より精緻な顧客分析や販促施策が可能に
- ポイント3 「お得さ」だけでなく楽しさや自由度を重視したポイント体験を提供
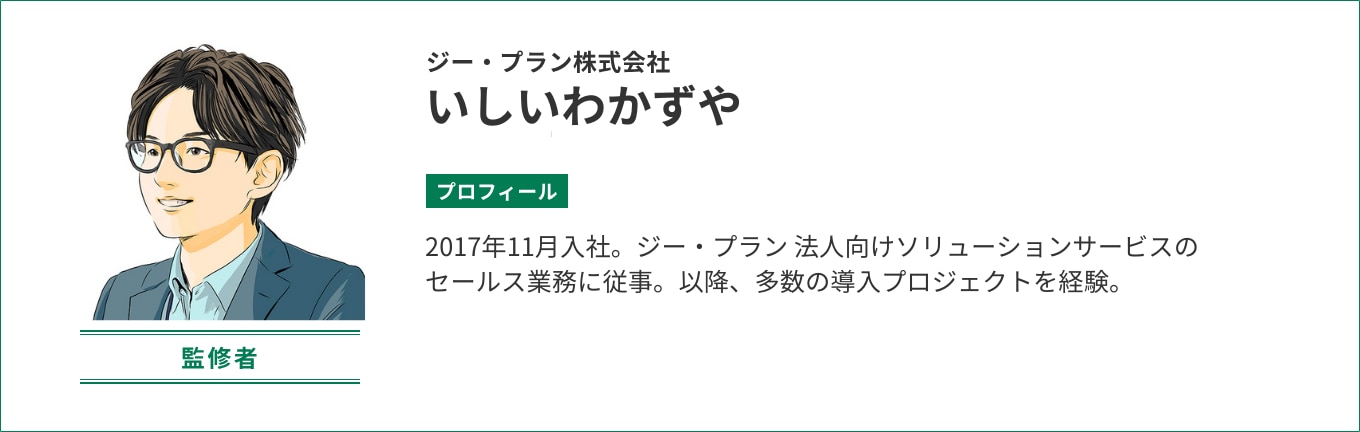
目次[非表示]
開発期間を1年半から2-3カ月に短縮! Vポイントが実現する効率的なポイント連携の新基準
現在のVポイントは、全国のコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストア、飲食店など約16万店舗で利用できます。TSUTAYAやファミリーマート、ウエルシアなど生活に密着した店舗から、ガスト、吉野家といった外食チェーンまで、日常のあらゆる場面でポイントが貯まります。さらに三井住友カードでは、特定店舗のスマホのタッチ決済で最大7%が還元される施策も行っています。
貯めたポイントは1ポイント=1円分として、Vポイント提携先の店頭で使えるほか、VポイントPayアプリを使えばVisa加盟店での支払いにも直接利用可能。Vポイント提携企業約3,200社、Visa加盟店約1億店という規模は、まさに日本最大級の共通ポイントです。
しかし、この統合は単なる規模の拡大だけが目的ではありませんでした。なぜ20年以上の歴史を持つTポイントは、SMBCグループのVポイントと一つになったのか。統合から1年以上経った今、どんな変化が起きているのか。鶴見氏が語る統合の真相と、Vポイントが描く未来像に迫ります。
「物理的なカードは何も教えてくれない」スマホ決済への課題
Tポイントは2003年のサービス開始以来、多くの提携先で利用できる共通ポイントとして成長してきました。しかし、スマートフォンの普及は大きな転機になったと鶴見氏は語ります。

「物理的なカードって、自分が何ポイント持っているかも教えてくれない、何もしゃべってくれないんです。それに、スマホ決済が広がる中で、カードとスマホを別々に出すのは不便ですよね」(鶴見氏)
CCCMKホールディングスは10年ほど前からモバイルシフトを進めており、モバイルTカードでのTマネー(現:Vマネー)を使ったコード決済機能も提供していました。ただし、PayPayなどスマホ決済に特化したプレイヤーが登場し、自社の決済機能だけで競争していくのは難しい、という壁に直面していました。
一方で、SMBCグループのVポイントは、グループの外にもっとサービスを広げたいという考えを持っていました。リアルな店舗網を持つTポイントと、決済インフラを持つSMBCグループのVポイント。それぞれの課題と強みが合致したことが、2022年10月の資本・業務提携に関する基本合意へとつながりました。
統合で起きた変化「ポイント発行量が大幅に増加した」
「サービス統合後、目に見える成果として、世の中でVポイントが新たに発行された量が大幅に増加しています。貯まる量が増えれば、使う量も増える。ユーザーのお得感は確実に増したと思います」(鶴見氏)

統合にあたって最も重視したのは、ユーザーに手間をかけさせないことでした。三井住友カードや銀行のIDと、従来のT会員のIDを一度連携するだけで、ポイントが自動で統合される仕組みを整えました。提携先側にもシステム改修などの負担はかけていないといいます。
「ユーザーにとっての魅力は、日常の買い物に加えて決済や金融サービスでポイントが貯まる機会が大幅に増えた点です。『VポイントPayアプリ』を使えば、VポイントをVisa加盟店での支払いに直接使えるので、使い道は飛躍的に広がりました」(鶴見氏)
強みは「深いID-POS」と「広いキャッシュレスデータ」の融合
提携先にとっての価値は、より深い顧客分析が可能になった点にあります。CCCMKホールディングスが元々持っていた「いつ、誰が、何を買ったか」という詳細な購買データ(ID-POS)に、三井住友カードが持つ広範なキャッシュレスデータが加わりました。
「我々のID-POSは『深い』データです。これに、より『広い』キャッシュレスデータが加わることで、提携先様は自社のお客様が、お店の外でどのような消費行動をしているかまで分析できます」(鶴見氏)
この分析から得られた気づきをもとに、商品開発や販促施策の立案、アプリを通じた送客までを一体で支援しています。
「お得さ」の先へ。「経済圏に閉じ込めない」Vポイントの未来

▲鶴見氏(右)と、ジー・プラン株式会社 プラットフォームビジネス部長 田中裕章氏(左)
今後の展望について、鶴見氏は「ユーザーを特定の経済圏に閉じ込めないようにしたい」という考えを強調します。その象徴が、今後予定しているPayPayポイントとの相互交換です。ユーザーがサービスを自由に選べる環境作りを進めています。
また、ポイントの価値はもはや「お得さ」だけではない、と鶴見氏は見ています。
「最近は『推し活のためにポイ活をする』という方も増えています。そういった新しい価値観に応えたい」
CCCグループの強みであるエンターテインメント領域を活かし、VポイントアプリのモバイルVカードの画面を好きなキャラクターのデザインに変えられる「Vキセカエ」を提供開始。ポイントを貯めて使う体験そのものを楽しんでもらうことを目指しています。
金融グループとの連携で利便性を高めながら、エンターテインメントの力で体験価値を深める。Vポイントは、独自の道を進み始めています。
ポイント交換の課題を解決する「ポイント・コンセント」
Vポイントのように、多くのポイントサービスが連携を強化し、ユーザーにとっての価値を高めています。しかし、企業が個別に他社ポイントとシステム連携を進めるには、多くの開発コストや時間がかかるのが実情です。
ジー・プランが提供する「ポイント・コンセント」は、こうした課題を解決するソリューションです。自社のポイントサービスを、Vポイントをはじめとする約150銘柄のポイントに直接交換できる仕組みを、低コストかつ短期間で導入できます。ポイントサービスの導入や改善を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。








