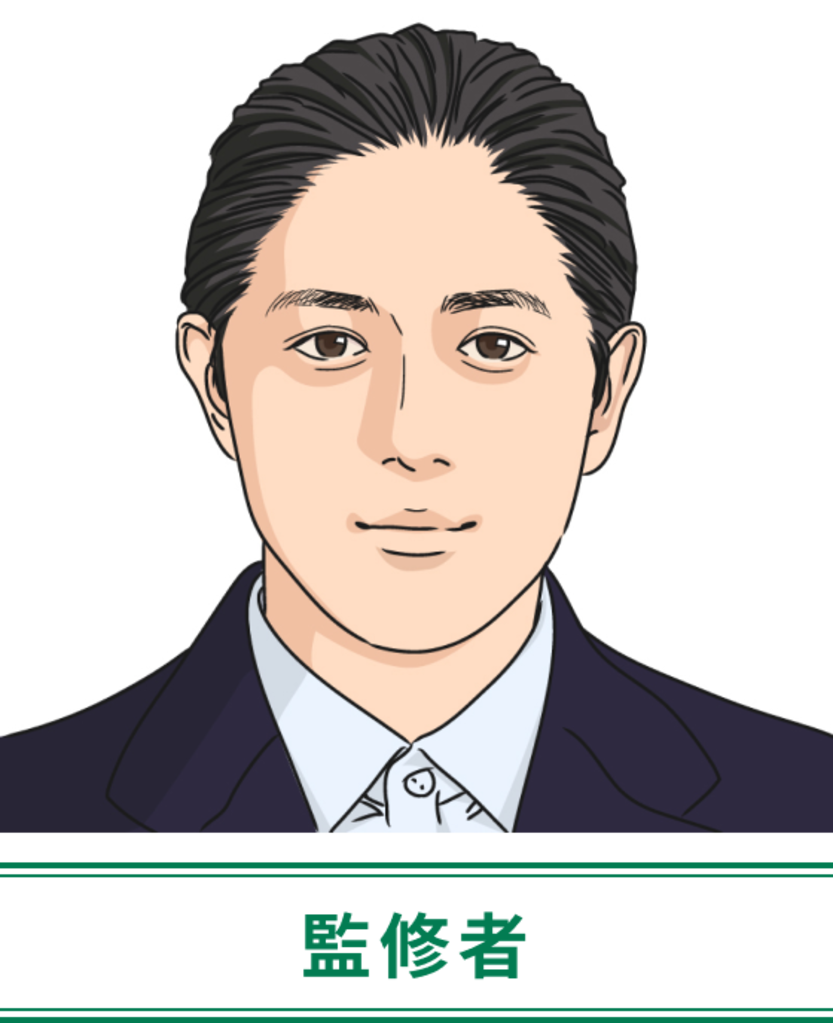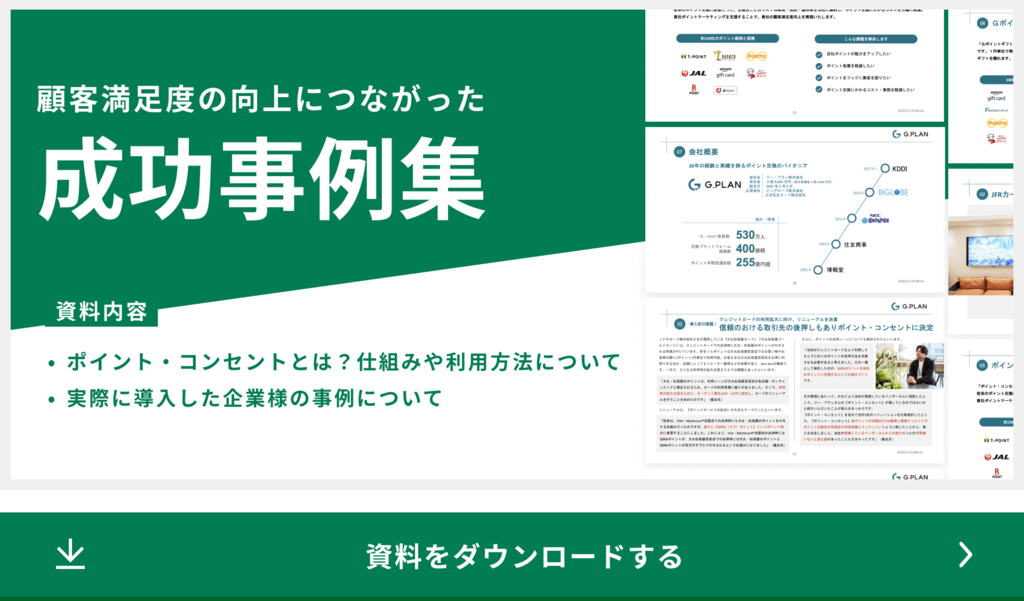顧客単価とは?
顧客単価とは、ビジネスの成功に直結する非常に重要な指標です。具体的には、一人の顧客が一回の購買で平均して支払う金額を指します。この数値は、事業者が自社のパフォーマンスを把握するうえで、欠かせない要素となります。
マーケティング戦略では、顧客単価を細かく分析することが大切です。たとえば、ファッションのECサイトなら、カテゴリーごとに顧客単価を算出することで、特定の商品群がどれだけ売れているかを詳しく知ることができます。
また、時間帯や曜日、シーズンなどによっても顧客単価が変動する場合があるため、そのような要素にも目を配ることが重要です。この数値によって、訪問者数が多くても顧客単価が低いと、売上は伸び悩む可能性があります。
反対に、訪問者数が少なくても、顧客単価が高ければ、事業を成功に導くことができます。従って、顧客単価を上げる戦略を考えることは、全体の売上を伸ばすために不可欠です。つまり、顧客単価はビジネス戦略を練るうえで、非常に有用なデータといえます。
顧客単価の定義
顧客単価の定義は「顧客1人が1回の買い物でどれだけの金額を支払ったか」を示します。ポイントとして、計算には購入が完了した顧客のみが対象です。つまり、店に訪れただけで購入に至らなかった人数は計算に入りません。
この指標は、目的によって計算方法が変わることがあります。たとえば、1人の顧客が複数回店を訪れる場合、そのすべてを「ひとり」としてカウントする方法もあります。このようなアプローチは、リピート顧客を対象にした一定期間の売上向上戦略において特に有用です。
さらに、デリバリーサービスやECサイト、ポイントカードを提供する店舗では、個々の顧客データが取得しやすいため、リピート率や購買履歴を詳細に分析することが可能です。例として、1年間の顧客単価を算出することで、顧客1人あたりの売上を具体的に高める戦略が考えられます。
このように顧客単価はさまざまなビジネス戦略に活かせるため、非常に重要な数値となります。
顧客単価の計算方法
顧客単価の計算は、具体的に「売上高 ÷ 購入者数」によって求められます。この計算方法は非常にシンプルですが、売上が存在する状態で初めて計算が可能です。
特に新規ビジネスを立ち上げる際には、顧客単価をどう設定するかという点は非常に重要です。この指標はビジネスプラン作成段階から考慮するべき要素といえます。
売上目標やビジネスコンセプトを策定する時点で、どれくらいの顧客単価を目指すかを明確に設定することが欠かせません。売上は「顧客単価×購入数」で算出されるため、この2つのバランスが事業成長の鍵です。
顧客単価を分析するメリットは、売上の増加に繋がること
顧客単価を定期的に分析するメリットは多く、その1つが売上の増加です。たとえば、年・月・週などの期間で顧客単価を把握することにより、商品価格が妥当か、また購入数が足りているかといった点を詳しく知ることができます。
ビジネスを開始する際、予想した顧客単価と実際の顧客単価が一致しないケースがあるため、定期的な分析が必要です。このように分析を行うことで、店舗の弱点を特定が可能となり、それを改善する施策を考えられます。
具体的には、「昼時に客数は増えるが、客単価は上がらない」という状況を把握したら、昼メニューの価格設定や提供する商品の見直しが必要かもしれません。さらに、時間帯や季節による顧客単価の変動を把握することで、ターゲットとする顧客層や売上促進キャンペーンの戦略も練りやすくなります。
繁忙期に合わせてプロモーションを行ったり、オフシーズンに特別な商品を提供をしたりすることで、売上をより効率的に伸ばすことが可能です。
顧客単価が低い主な原因は2つ
顧客単価の定義や計算方法、分析するメリットについて理解できたところで、次は顧客単価が低い主な原因について紹介します。主な原因は次の2つです。
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.商品単価が低下している
商品単価の低下は、顧客単価の低下の主な原因の1つです。特に購入個数を増加させるための施策として、安価な商品の取り扱いを増やす場合には、このリスクが高まります。
たとえば、安価な商品を多く取り揃えることで、購入個数は増加するかもしれません。しかし、顧客が高価な商品を購入するチャンスを減少させる可能性もあります。
安価な商品の導入は、顧客単価向上の一つの手段として有効ですが、それだけが目的となると逆効果となることもあるので注意が必要です。
安易な施策に走るのではなく、顧客の購買動機を深く理解し、顧客の真のニーズに応える形で商品ラインナップを考えることが非常に重要です。
2.購入点数が減少している
購入点数の減少も、顧客単価が低下する原因の1つになります。たとえば、商品単価を上げると、顧客は購入点数を控える可能性が高いです。
この現象は、「前に比べて高くなったから、今回は少なめにする」といった消費者の心理に起因します。同様に、繰り返しセールを行って安売りする商品を固定化してしまうと、顧客は「次回のセールまで待って購入すればいい」と考えるようになり、購入点数が特定の期間に偏ってしまいます。
これらの価格戦略には落とし穴が多いため、値動きをする際は顧客にその理由をしっかりと伝えることが重要です。原料費が上がってしまったという明確な理由がある場合、その情報を顧客に共有することで納得感を高められます。
また、価格を変更する際には、新たなサービスや付加価値を提供するなどして、顧客がその価格での購入に納得するような工夫が求められます。
顧客単価を上げる8つの方法
顧客単価を上げる方法として、次の8つが挙げられます。ここでは、それぞれの特徴について解説します。
1.商品価格を上げる
商品価格を上げることは、シンプルに見えて多くの戦略が必要とされるアクションです。単に価格を上げるだけでは、顧客の信頼を失うおそれがあります。
そのため、価格上昇には納得感を与える何らかの理由付けが必要となります。たとえば、高品質な原材料を新たに使用するといった付加価値があれば、「品質向上のために価格を調整しました」という形で顧客に伝えることが可能です。
また、価格を上げるタイミングも重要です。新製品のローンチ時や季節の変わり目など、顧客が新たな価値を感じやすい瞬間を狙うと、価格上昇がスムーズに行える可能性が高まります。
価格を上げることで顧客単価向上を狙う際は、その背後にしっかりとした戦略と説明が必要です。顧客が新たな価格に納得できるような付加価値を明確にすることが、成功の鍵となります。
2.アップセルを実施する
アップセルという手法は、顧客単価を効率よく上げるための有用な施策です。すでに購入を考えている商品よりも高機能・高価格の商品を選んでもらうことで、売上に貢献します。
たとえば、あるスマートフォンの基本モデルを見ている顧客に対して「新機能と拡張バッテリーが搭載された上位モデルはいかがでしょうか」と提案するケースが該当します。
ただし、ここで大切なのは顧客のニーズと感じる価値をしっかりと把握することです。単に高価な商品を勧めるだけでは、顧客は押し売りと感じる可能性があります。
そのような状況を避けるためにも、顧客の購入履歴や行動パターンを分析し、その人にとって真に価値のある商品を提案することが重要です。
また、サブスクリプション型のサービスにおいては、アップセルでより高いプランを提案する場合も、「何がアップグレードできるのか」を明確にし、その価値を顧客に理解してもらう必要があります。
3.クロスセルを実施する
クロスセルは、顧客が購入しようとしている商品に付随する関連商品を推奨することで、顧客単価を高める手法です。たとえば、コーヒー豆を買おうとする顧客に対して「この豆を挽くのに最適なコーヒーミルがこちらです」といった形でアプローチをかけます。
ECサイトではよく実践されており、「この商品を購入するお客様は、以下の商品にも興味をお持ちです」といった表示がこれに該当します。これは、単に売上を上げるだけでなく、顧客にとっても利便性が高いと感じられる場合が多いです。
しかし、重要なのはその推奨が顧客のニーズに合致しているかどうかです。押し売りのような形で行われると、顧客は不快に思う可能性があります。
クロスセルで推奨する商品は、顧客が実際に求めているもの、またはその可能性が高いものに限定し、その価値を明確に伝えるよう工夫が必要です。
4.商品に特典をつける
商品に特典をつけることは、顧客にとっての価値を増加させ、結果的に顧客単価を向上させる効果的な手段の1つです。お得感を演出することで、購入を迷っていた顧客も、その特典に惹かれて購入に踏み切ることが多くなります。
たとえば、「2点購入で次回使える割引クーポン付き」や「〇〇円以上購入で1000ポイントをプレゼント」などのキャンペーンは、消費者の購買意欲を掻き立てるのに役立ちます。
また、特にECサイトでは、購入金額が一定額を超えると送料が無料になるような設定をすることで、より多くの商品をカートに追加してもらえる可能性が高いです。さらに、購入に応じてポイントを付与することで、顧客の購買意欲を高められます。
このように、特典をうまく活用することで、顧客に更なる価値を提供し、結果的に顧客単価を上げることが可能です。ただし、特典の提供はコストもかかるため、適切なバランスを見つけることが大切といえます。短期的な利益追求だけでなく、顧客との長期的な関係性も考慮して特典を設計することがおすすめです。
ポイントマーケティングを実施して顧客満足度を向上させた成功事例を確認したい方は以下の資料がおすすめです。
ポイントマーケティングを活用して顧客満足度を向上させた事例集をダウンロードする
5.価格を3段階で設定する
この手法は「松竹梅の法則」とも呼ばれ、中間の価格帯の商品が選ばれるようになるという心理的効果を利用しています。たとえば、お土産屋さんでは、6枚入り、10枚入り、16枚入りといったように同じ商品を異なるパッケージで用意することが一般的です。
スーパーマーケットの精肉売り場や総菜売り場でも、よく見られる手法です。小・中・大というサイズが用意されていると、多くの場合、中サイズの商品が最もよく売れます。
この理由は、人が3つの選択肢を見た際に、中程度の価格のものを選びやすい傾向があるからです。この原則を活かすことで、顧客が最も買いやすい中間の価格帯を主力商品として展開することが可能となります。
この背景を考慮して、商品ラインナップを考える際には、顧客が比較しやすいように3つ以上の価格帯を設定することが大切です。これにより、低額商品に手を出すよりも、少し高めの商品を選ぶ傾向になります。このような手法を行うことで、顧客単価を意図的に向上させられます。
6.まとめ買いをおすすめする
顧客単価を向上させたいと考えるなら、まとめ買いをおすすめする戦略が有効です。多くの企業が「2つ以上購入で10%OFF」や「5,000円以上購入で送料無料」といったキャンペーンを展開しているのは、この理由からです。
特に消耗品や定期的に購入する商品であれば、まとめ買いのインセンティブは効果があります。はじめての利用者や購入意思が強い顧客に向けて、商品セットを提供するのも1つの手段です。
たとえば、プロテインの新規ユーザーに対して、プロテインとシェイカーを一緒に販売する「スタートアップセット」を販売することで、初めての購入であっても顧客単価を上げられます。
このようなセット商品は、消費者にとっても価値が感じられるため、購入意欲を高めます。同時に、企業側も複数の商品を一度に販売するチャンスを得るため、双方にとってメリットがあるわけです。
まとめ買いやセット商品の展開によって、顧客が少額の買い物から脱却し、より多くの商品を購入する動機を与えられます。この戦略をうまく活用することで、顧客単価の向上が見込めます。
7.決済手段を増やす
昨今では、オンライン決済が一般的になってきており、その流れに乗って決済手段を多様化することは、顧客単価を向上させる有効な手段といえます。
具体的には、クレジットカードやPayPay、Apple Payなど、さまざまな決済オプションを提供することで、特定の決済手段しか利用しないという理由により、購入を見送っていた層を獲得できるのです。
定期便やサブスクリプションサービスにおいても、多様な決済手段の提供は特に重要です。オンライン決済を選ぶことで、毎月の支払いがスムーズに行え、決済を忘れるリスクも低くなります。
このような便利さは、顧客が長期間にわたってサービスを利用するインセンティブにもなり、結果として長期的な利益を生む可能性が高まります。
8.優良顧客に特別な商品を提供する
顧客単価を高めるための1つの策として、リピート顧客に対する特別な商品やサービスの提供が効果的です。すでに何度も購入経験がある優良顧客に対して、メルマガや専用キャンペーンを用いて数量限定の商品や新製品を先行して提供することは、顧客ロイヤルティの向上だけでなく、高額商品に手を伸ばしやすくなる可能性が高まります。
具体的な手法としては、会員限定で特別な商品を販売する、または新商品の先行予約をメルマガ購読者限定で行うなどが考えられます。これにより、顧客は「特別な存在である」という優越感を味わい、更なる購入を検討する傾向が高いです。
また、このような施策は、SNSでのシェアを促し、新たな顧客を引きつけるきっかけにもなりえます。言い換えれば、優良顧客への特別な商品の提供は、新規顧客獲得と既存顧客の顧客単価向上、双方に対してプラスの影響を与える戦略として非常に有用です。
顧客単価でよくある2つの質問
顧客単価を上げる方法について理解できたところで、次はよくある質問を紹介します。
- 質問①顧客単価のデータは何に活かせる?
- 質問②顧客単価の目標を設定するうえで注意すべきポイントは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問①顧客単価のデータは何に活かせる?
顧客単価は、ビジネスの成果を向上させるための鍵となる指標の一つです。新規顧客獲得の際には、価格設定を行う基準として活用できます。具体的には、既存の顧客層から見た顧客単価を元に、新規顧客が魅力を感じるであろう価格帯を見極めます。
また、顧客属性に基づいて顧客単価を分析すれば、特定の層に対するマーケティング戦略を練るのに効果的です。このようにして新規キャンペーンの方向性をしっかりと定めることで、効果的なキャンペーン実施が可能となります。
加えて、顧客単価は顧客満足度の評価にも用いられます。たとえば、ある一定期間内で顧客単価が顕著に向上している場合、それは顧客が繰り返し購入を行っており、商品やサービスに対して満足していると解釈してよいです。このような情報は、長期的な顧客価値(LTV)を高めるためにも有用です。
つまり、顧客単価のデータは単なる売上分析に留まらず、新規顧客獲得から顧客満足度の向上、さらには企業成長に寄与する多面的な活用に役立ちます。
質問②顧客単価の目標を設定するうえで注意すべきポイントは?
顧客単価の目標設定は、ビジネスモデルや商品の性質に密接に関連しています。たとえば、家電や大型家具のような高額商品を扱っている場合、商品の価格設定がそのまま顧客単価となります。
ここで注意が必要なのは、原価と利益だけでなく、顧客の期待や「値ごろ感」も考慮に入れるべきです。製品の品質を向上させるか、独自の付加価値を設けることで、顧客が高い顧客単価に納得感を持つように工夫が求められます。
一方で、食品や日用品といった低額商品を取り扱う企業の場合は、単なる商品単価ではなく、購入点数も重要です。つまり、買い上げ点数を増やすための施策が必要とされます。
具体的には、バンドル販売やポイント還元などの手段で、顧客がより多くのアイテムを購入するインセンティブを提供することが有用です。
つまり、顧客単価の目標設定に際しては、商品の特性と顧客ニーズのバランスを取ることが非常に重要です。
まとめ
この記事では、顧客単価を分析するメリットや顧客単価が低い主な原因、顧客単価を上げる方法などについて解説しました。
顧客単価を分析して、データを有効に活用することで、価格設定の基準として活用できるほか、顧客属性に基づいて顧客単価を分析すれば、特定の層に対する効果的なキャンペーン実施が可能となります。
このように、顧客単価を分析して顧客のニーズを把握し、データに基づいた施策を実践することで、ビジネスを成功に導くことができます。今回紹介した施策のなかで実践していない施策があった場合、ぜひ実施を検討してみてください。